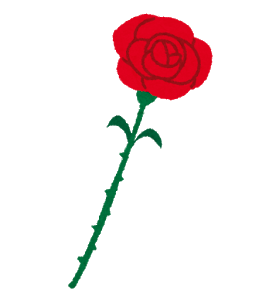所収:『虚像』(『赤尾兜子全句集』より )昭和57年 立風書房
「水族館の肥満家族」という語が持つアイロニカルな響きは「見る/見られる」というまなざしの逆転に関係しているように思われる。一面ガラス張りの水槽で構成された水族館というのはもちろん展示された魚や海洋哺乳類を観察するための施設であって、われわれ人間はその場において、いつだってまなざしを投げかける側であった。
しかしながらここでは「肥満家族」はまなざしを投げかけられる側であって、水族館の親子連れは魚を観察する一方、冷徹な観察をもって「肥満家族」と位置付けられる。見ている側のはずがいつの間にか見られる側へと転落しており、まずそこにおいてユーモアがある。そして観察の視線を受け入れたが最後彼らは暗喩となってしまうのである。
暗喩としての「肥満家族」というものが仄めかすものについて正確に語ることは困難ではあるが、この句集は1959年から1965年までという、まだ戦後の気分が濃厚でありながらも高度経済成長期である頃に書かれたということが、気分として充足している感じがする。つまり「肥満家族」というのは、第二次世界大戦の敗戦を忘却しながら、アメリカナイズされつつ経済規模を太らせてゆく日本の姿そのものであり、それに対してぶつけられるイメージの「陰惨なマカロニ跳ね」というグロテスクさは、対米従属する戦後日本に対する兜子のペシミスティックな態度を示すものだったのではないか。
ちなみに兜子が住んでいた神戸にある須磨水族館は、諸説あるものの日本の水族館発祥の地であるらしい。
神戸に着いてもう少し述べると、永田耕衣が近所であったり、金子兜太も神戸に赴任していたり、他にも鈴木六林男、林田紀音夫、堀葦夫、伊丹三樹彦らも関西であって、関西に前衛が割拠していた状況があったことも同時に思い出したい。あの時代こそが、文学青年が俳句に真剣に打ち込める最後の時代だったのではないか、と悲観的に思ってみたりもするが、果たして兜子の鬱にあてられてしまっただけなのだろうか。
記:柳元