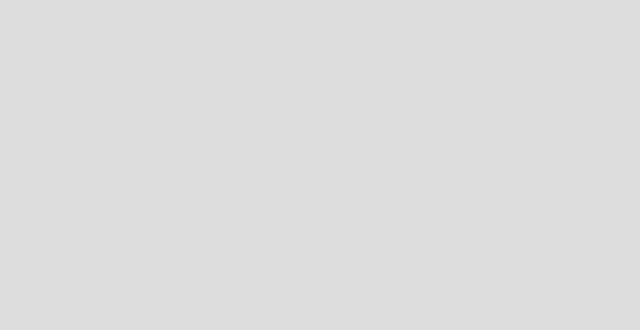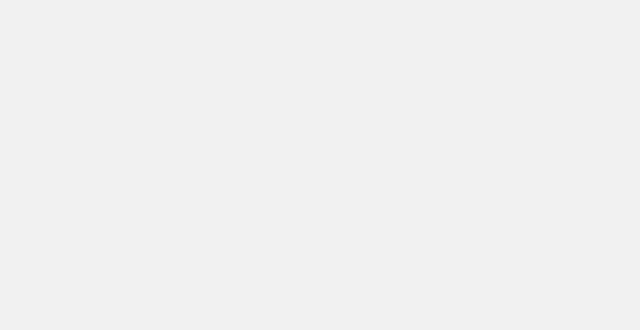所収: 小池正博編『はじめまして現代川柳』(書肆侃侃房、2020)
この句の可笑しさは、喋っている二人のその顔の方向にあると思う。
〇
この「いよいよ」が、どういう局面、状況において出てきた言葉なのか、という一番重要な想像については、読者それぞれに委ねたい。私は古い少女漫画の主人公をいじめるクラスメイトA・クラスメイトBが、主人公を最も追い詰められる方法を考えて、文化祭の当日にそれを決行する気でおり、その日がようやく来た、くらいのテンションで読んだ。とにかく、悪者たちだなとは感じた。「ネ」「ヨ」がありうるのは、私の中では悪者か老人か児童かだった。これをもっと健全な方向に、たとえば同僚と数か月かけて綿密に練ったプロジェクトがついに開始する日が来ただとか、部活の成果を発揮する高校最後の大会当日だとかに読むことも出来るだろうとは思う。ただし、そうなると「ネ」「ヨ」なのが、ふざけすぎて面白いものになってしまう。
○
この句では、「と言えば~という」という分かりやすい型が示されている。
親が子供に、何食べる?と言って、子供が親に、ハンバーグと言う。
Siriに明日の天気はと言うと、Siriは雨ですと言う。
思いつくままに型に当てはめてみた(この代入は正確ではなく、それについては後述)。今挙げた二つは、最初の「言えば」要素は「聞けば」に言い換えられる。何食べる?と子どもに聞いて、子供は回答を親に返す。Siriは投げかけられた質問に対して忠実に答える。
これは、会話している(会話になっている)例である。
「いよいよネ」に対して、「いよいよヨ」。これは果たして会話は成り立っているのか。
ここで読みが二つに分かれる。最初に述べた、これはどういう状況なのかという想像に関わる大きな分岐である。
二番目の「いよいよヨ」と言った側が、話が通じている場合(会話できている)と、話をしてはいない又は話が通じていない場合の二つである。
話が通じていないとなれば、「と言えば」「という」と最初の「言」だけが漢字になっているのも納得ができるような気もする。こちらは確かに言っているので、発言したことが漢字で強調される一方、向こうは通じず機械的に返しているだけなので「という」とニュアンスが柔らかくなっている。入力に対してそれをほとんど変えず出力する、計算器みたいな相手(機械かもしれない)が喋っているようにも見えるし、寝ぼけていて何が「いよいよネ」なのか全くわからず適当に「いよいよヨ」と言っている人間の光景も見えてくる。インコが飼い主の声をバグったようにリピートして発声しているようにも考えられる。
話が通じていない、という可能性は十分に魅力的だが、この句に関しては私はそちらでは読まず、話は通じているとして読みたい。なぜなら、もし通じていないのなら、「いよいよネ」に対して「いよいよネ」と言っていた方が自然だからである。そういう句なら大量に見たことがある(俗に小泉進次郎構文と呼ばれるものもそんなものだろう。「今のままではいけないと思います、だからこそ日本は今のままではいけないと思っている」的な)。全く同じ言葉を返すことでのおかしさや怖さや機械感の演出。
もし、友達に突然「いよいよね!」と大声で呼びかけられたとしたら、「いよいよだね」と受けながら返すか、「何が?」と疑問にするか、「うん」と簡単に返すかするだろう。ここで「いよいよヨ」という言葉が出てくるのは、シンプルな反復に見えて、案外そうでもなさそうである。
○
話が通じていて、なぜここまで会話っぽくない返し「いよいよヨ」が出てくるのか。それは、最初に述べた、喋っている二人の顔の方向にあると私は考えている。
ここでまた違う会話を考えてみる。
(お化け屋敷のなかで二人)A「怖いね」、それに対しB「怖いよ」
(旅行を明日に控えて二人)C「楽しみだね」、それに対しD「楽しみだよ」
どうだろうか。「いよいよヨ」とは違う、会話感が伝わるかと思う。二つの文とも「いよいよ」の雰囲気も、同じような言葉を繰り返すのも同じだが、二人が向き合って会話しているような印象がある。
「怖い」「楽しみ」と「いよいよ」との違い。それは、感情そのものであるか、その裏に感情を持っているものかの違いである。
怖いに対して怖いと返すとき、「私も」怖い、が成り立ち、同じ言葉が繰りかえされたとしても、それぞれの感性に基づいているから、全く同じではない。恋人同士が「好き」「好き」と言いあっていても、それがきちんと会話になっているように。
一方「いよいよ」は、それを言った瞬間の感情は直接表してはいない。「いよいよ何かが起こる」、その到来の確実さを言っているだけであり、「いよいよ」起こるからどう思っている、とまでは言い表さない。感情ではなく、事実の言葉である、ということである。
だから、「いよいよ卒業式が明日に開催される」として、Aさんは悲しく思い、Bさんは嬉しく思うかもしれない。このとき「いよいよだね」とAさんが言うとき、Aさんの顔は悲しそうで、それにBさんが満面の笑みで「いよいよだね」と言うと、これはあまり良いコミュニケーションではない、ということになる。
〇
つまりこの句は、「いよいよ」という語を用いるときふつう浮かび上がってくるはずの「いよいよ起きるからどう思うか」という感情の部分が隠されたまま、「いよいよ起きる」という空気感だけが反復されることで、およそ会話らしくないものになっているのである。
「いよいよね」と言われれば、その裏にあるたとえば「わくわくするね」という感情を拾って、「わくわくするね」と返すのがスムーズである。このように、繰り返すとしたらその裏にある感情の方なのである。
ここで序盤に触れた「言えば」の処理に戻る。親が子に何を食べたいか聞く例を挙げ適切な代入ではないと述べた。それは、親と子がお互いの方を向いているからである。親は子に向かって尋ね、子は親に向かって答える。
「いよいよネ」と「言」う、この段階では二人が向き合っているようにも見えるが、もしそうだとすれば、面と向かって「いよいよヨ」と返してくるのはなかなか恐怖である。「そうだね」くらいの返事が欲しくなる。
この返答の仕方、かつ「言えば」を考えたとき、私の中でくっきりと像をもって浮かんだ光景は、「二人がお互いの方を見ず、真っすぐを見つめている」ものだった。
よくある学園ドラマの、部活終わりの生徒が屋上や河川敷で二人並んで、「夕日の方を見ながら」話している光景に似ている(学園ドラマみたいな句だとは思っていないが)。
そうすると、「言えば」は真っすぐに前を向いて言ったもの(でも「ネ」だから会話の上では相手の方を向いている)で、言われた相手は目を合わせているわけではないから相手の感情に答える必要も減り、自分のなかの「いよいよ」を消化しようとして、「いよいよヨ」という不思議な返答になった……と考えることが出来る。
サン=テグジュペリが「L’expérience nous montre qu’aimer ce n’est point nous regarder l’un l’autre mais regarder ensemble dans la même direction.(経験は教えてくれる、愛とは、お互いを見つめ合うことではなく、ともに同じ方向を見つめることである)」と書いていたのをなんとなく思い出す。一見会話としておかしな句だが、その顔の方向と、深くでの感覚や空気感の共通を考えれば、自然に見えてくる。
〇
言葉のラリーとしてのおかしさだけを取り上げた句のように見えるが、「ネ」と「ヨ」という終助詞での方向付け、「いよいよ」という言葉の繊細な選択、「という」と開くことによって会話が起こったことを指示するなど、細かく見ていけば正確に作られているなと感じる。
松永の他の句を見てみても、「死にながら泣くから部屋を出て行って」「どこからでも見えてだあれも見ない家」「これ以上もう父さんは削れない」など、方向や主体の見えなさ(いるとしても感情がまったく見えてこない)に特徴があるように思う。
二人には「いよいよ」何が起こってしまうのか。そして二人は、どう思っているのか。そしてお互いがどう思っているのかをどれくらいわかっているのか。
私には、この二人の背中を見ることしかできない。
〇
蛇足としていくつか書いて終わりたい。「と言えば~という」の形を見て、瞬時に思い出したのは金子みすゞ「こだまでしょうか」と、〈つま先を上げてメールをしていたらかかとで立っていたと言われる/土岐友浩〉だった。会話には本当に色んな形があり、こだま、山彦、伝言リレー、噂、拡声器……。誰かが何かを「言う」とき、それがどういう形であるのかから想像したい。
私はよくこの鑑賞コーナーで、主体が機械である可能性や、語られている世界が現実ではない可能性について触れている。一応そういうこともあるかもしれないよ、くらいの雰囲気で書いているが、私自身はかなり本気でその可能性について考えていたりする。「いよいよネと言えば」と書かれていれば、言ったんだなと読むしかない(それが本当であると信頼して読み進める以外手はない)が、もしそれが言ってなかったら。言ったのが宇宙人だったら。
人によっては、そういう作品世界を急激に(意味もなく)拡げてしまうのは読みとして面白くない、と思われるかもしれない。
その作品にとって一番いい読みを、と思ってそういう可能性について考えているわけだが、そもそも「作品にとって一番いい読み」とは何なのか。未だに分からない。
○
私は中学生のときに出会った一冊の推理小説にはまって、それ以来ミステリに耽溺してきた。そして高校で俳句、大学で短歌、川柳、現代詩に出会った。
そこで思ったのは、あまりにも「地の文」への感覚の違いがあること。「信頼できない語り手」や「叙述トリック」などの用語があったり、後期クイーン的問題が考えられていたりがそうだが、地の文をそもそも信用してしまっていいのか、登場する主人公の視点、探偵の情報を確かなものとして受け取っていいのか……。
短歌では私性の問題が前衛短歌以降定期的に話題に上がっているし、石井僚一の「父親のような雨に打たれて」の一件も記憶に新しい。が、それは作者/主体の次元であって、語り手が真の情報を語っているかどうかなどという語りと語り手の問題にまではまだ深く到達していない印象がある(このあたりの短歌の文献をきちんと当たっているわけではないので、実は進んでいるのかもしれませんが)。
俳句にいたっては、虚構かどうかのような次元で永遠に止まっている(語り手がどうこうに到るほどの文字量が与えられていない/そういうことを企むのは俳句の面白さの範疇を越えている というような雰囲気もあり)と思う。
短歌も俳句も、テクニック自体はまあまあ飽和しかけてきた今、誰がそれを語るのか(語っている人(作者)の方に重きがおかれる)、という段階になっている(戻っている?)と私は体感で思っている。そんな時だからこそ、逆に語りの部分を考えていきたい。「連作」という機構の力は、そこに眠っていると私は信じている。
〇
評から離れて所信表明のようになってしまったが、この「いよいよ」の句はそういう点で言えば、語りだけが浮き上がったような形をしている。これを言っているのが誰なのか、何故こんな事を言っているのか、何故そんなことを言い返すのか。
川柳は、そもそも、すっと主体に同化して読める短歌や俳句とは性質が違う。そこに世界が生の形で(あるいは異常なまでに精密に構築された形で)存在する。その世界が現実なのかどうか、主体は作者かどうか、から話が進むわけではない。その世界を受け入れるかどうかから強引に始まる。どんな声で、どんな顔で、主体は喋って、思って、それを語り手はどう記述しているのか。語り手は迫られて書いているのか、余裕をもって冷笑を浮かべながら書いているのか。
それらを短詩で考えていくヒントが川柳にあると、私は確信している。
〈みんなは僕の替え歌でした/暮田真名〉、〈小雪降るときちがう声で言うとき/八上桐子〉、〈手紙ソムリエ手紙ソムリエおまえは幸せになる/柳本々々〉。
記:丸田