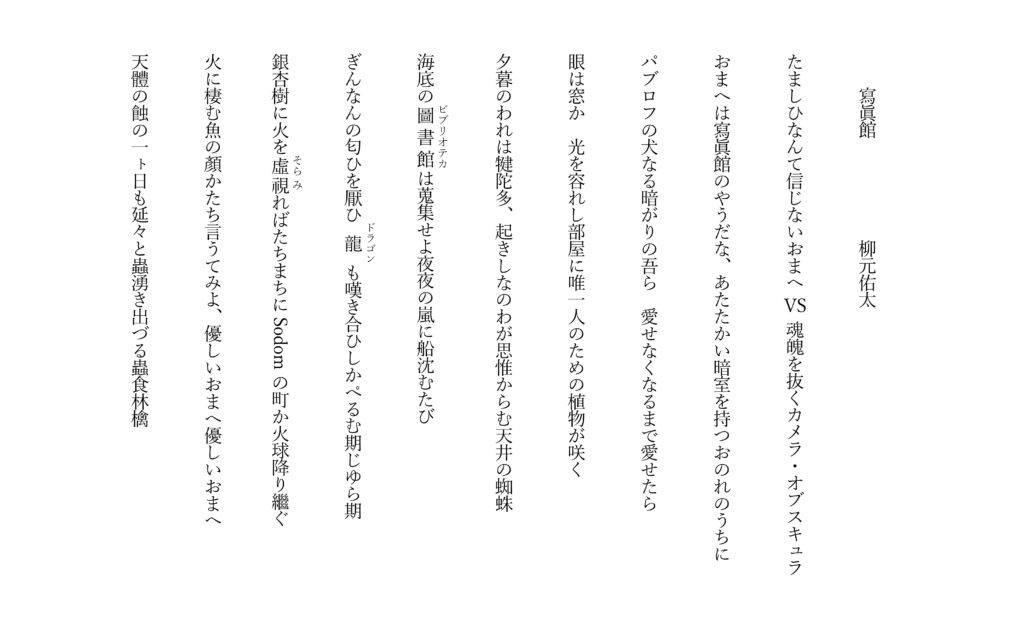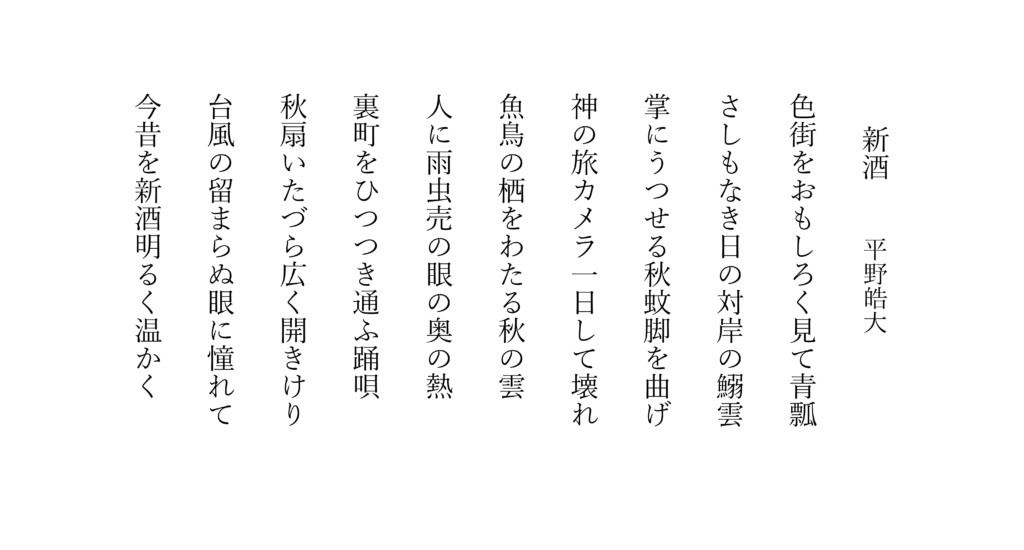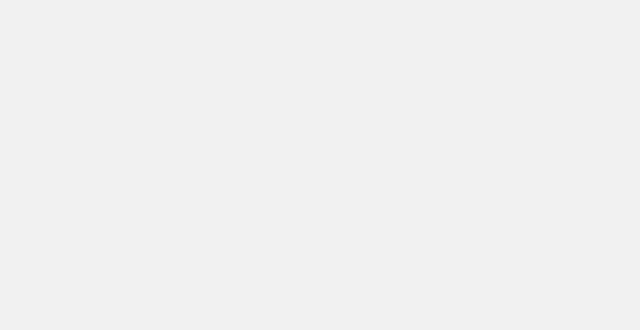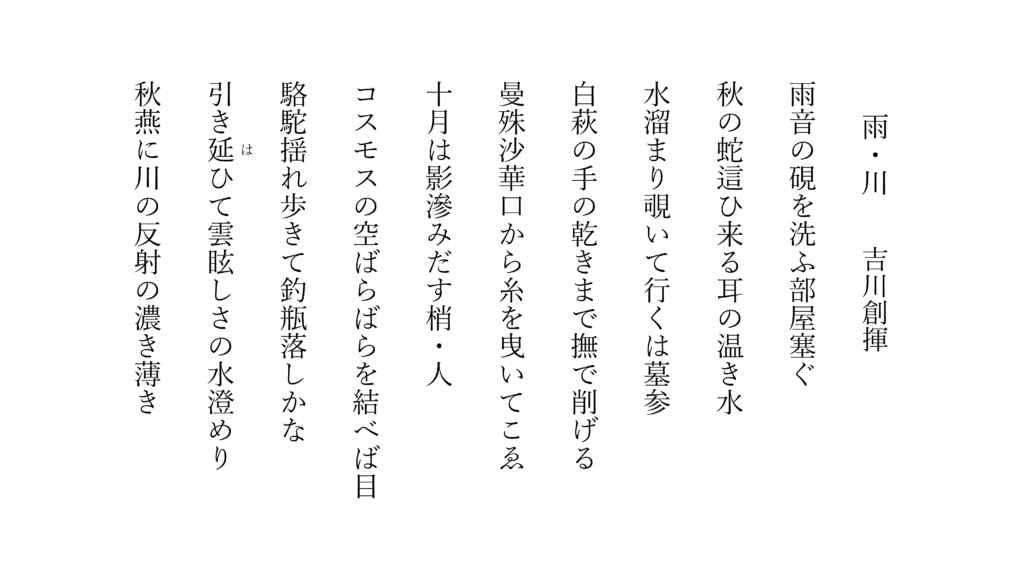参考:夏石番矢『超早わかり現代俳句マニュアル』(立風書房、1996) *
曖昧だなあ、という感想を持った。宿屋が在ったような気がして、そこに千枚漬けといろいろがあったような気がする。それくらいの句ではある。
この句の面白いところを三つ挙げるとすれば、まず「あいまい宿屋」の言い方。「ふれあい動物園」「二十世紀梨」のような感覚で、「あいまい宿屋」という宿屋があるような聞こえ方になっている。宿屋に関する記憶が曖昧で、そんな宿屋だ、ということをこのように省略すると、「あいまい宿屋」というポップな面白い響きを持つフレーズになる。「あいまい階段」「あいまい天体」「あいまいカフェ」……いろいろ他のものも考えてみるが、(他のものには他の雰囲気があるにせよ)宿屋とは確かに、あいまいだなという気がしてくる。細部を部分的に、全体をざっくりと、見たような記憶は残っているが、だからと言ってそれ以上の情報は記憶していないような気がする。むしろ宿屋へ誰と行ったか、そこで何をしたかというエピソードばかりが重要で。宿屋自身のことは確かにあいまいだと思わされる。変なフレーズに納得させられるのが面白い。こういう芸風のお笑い芸人を見たことがあるような気がする。
二点目に、「千枚漬」の部分。「あいまい宿屋」とあいまいな記憶の中で色濃く存在しているのが千枚漬けなのか、という面白さ。これは普段から千枚漬けにどういう気持を持っているかで味わいは変わるが、私は千枚漬けは結構好きだがあまり食べない、ややシブめのチョイス、というイメージであるため、「あいまい宿屋」のなかで唯一取り上げるのが風呂や景色やメインディッシュではなく「千枚漬」であるという点に、ものすごく惹かれる。よほど美味しかったのか。もしくはよほど変な味がしたのか。曖昧な記憶のなかで千枚漬だけが具体性を付与されていることが、なんだか面白い。
一応補足として、先ほどから私は記憶記憶と言っているが、これは過去を回想しているのではなく、現在進行形で「あいまい宿屋」に泊っていて、その中に居る私もなんだか曖昧になってきた、という句とも読める。それもひとつの魅力的な読みかもしれないが、その場合「千枚漬」の良さがやや減るかと思う(今目の前にあるから言った、というより、回想の中でなぜか千枚漬けだけが浮かんでくる異様さ、変てこさの方が、「あいまい宿屋」のフレーズに近い面白さがあると判断したからである)。私は回想の方で読みたい。
最後、三点目に、「とそのほか」の暈かし方の面白さがある。「あいまい宿屋」のなかのもの(装飾とか、外装とか、他の料理とか)は、「千枚漬」かそれ以外かに分けられてしまう。そんなことないだろう、とも思うが、そんなことがあったのだろう。「そのほか」なんて曖昧で適当な言い回しだなあと一見思えるが、あきらかに意図された面白さがここにある。
加えて言うならば、「あいまいやどやの/せんまいづけと/そのほか」というテンポのいいリズムも好みである。これがもし定型だったら、それはそれで面白かったのかもしれないが、これはこうでないといけなかっただろう。一応「千枚漬」という季語・名産品から、もしかしたら京都かな、とか、もしかしたら冬かな、と想像することも可能だが、なんとなく、「あいまい宿屋」はそうしていっても辿り着かないところにある気がしてならない。
*本来、所収されている句集を引くべきですが、この句が収録されている一碧楼の句集を把握することができず、私がこの句を発見した夏石番矢の本を一応参考として記しました。一碧楼の句集を確認することが出来たらまた変更・追記等したいと思います。
追記︰「曖昧宿」(また、「曖昧屋」)という名詞があることを指摘いただきました。完全に私自身その単語を知らず、「あいまい」という言葉の面白さ中心に読んでいました(これもまた一つの読みかと思いますが)。曖昧宿とは、表向きは茶屋や料理店で、実際は娼婦を構えて客をとる店を指すようです。これを考慮すると、「千枚漬」という表側の記憶が残っていること、本当の目当てを「とそのほか」とぼかしているお茶目さ(?)が見えて、面白みのある句に読めるかなと思います。曖昧宿、という単語そのものの、「あいまい」というネーミングが、この句の空気感とそのまま同じなのではないか、と思います。(2020年10月21日)
記:丸田