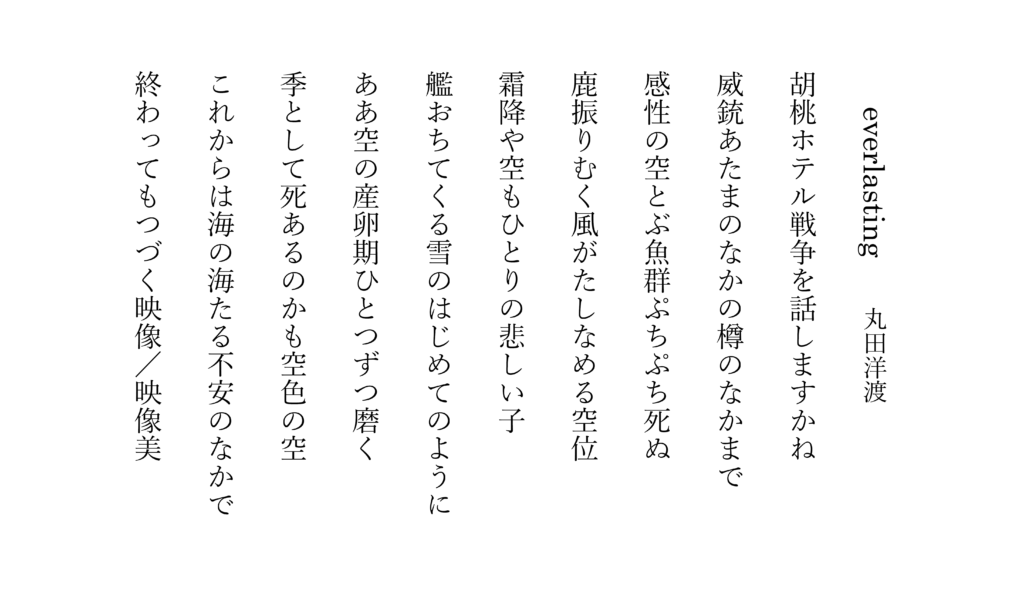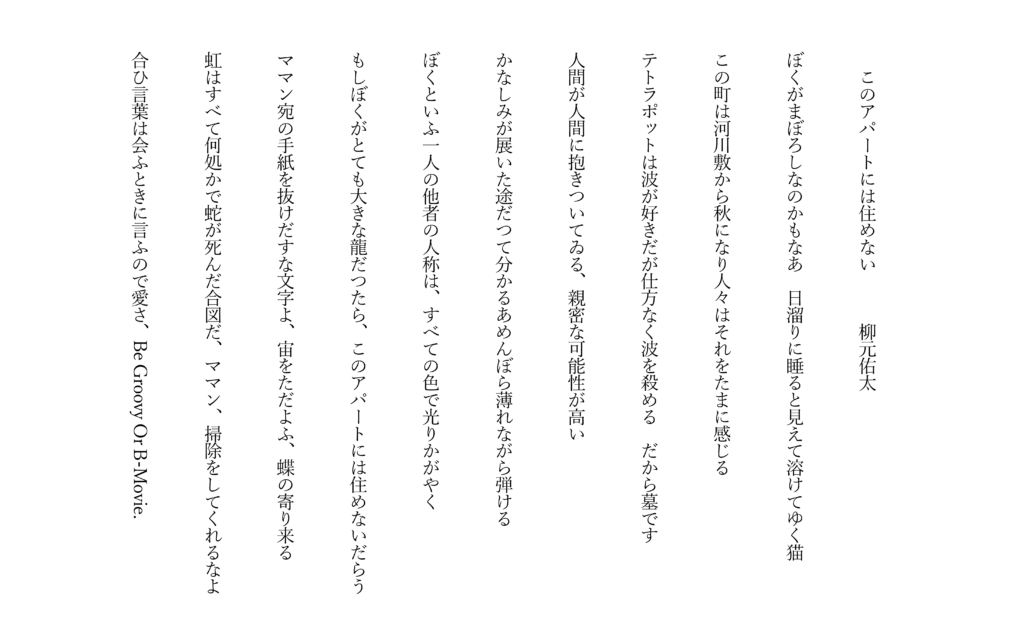2020年8月27日、「帚」内で生駒大祐『水界園丁』(港の人、2019年)についてZoomにて座談会を行いました。各者ともに10句選を事前に行い、その上で『水界園丁』を出発点として多種の話をしました。以下、その模様になります。
〈各10句選〉
柳元佑太選
物憂さも冬の渚へ出る程度
目逸らさず雪野を歩み来て呉れる
鳥すら絵薺はやく咲いてやれよ
五月来る甍づたひに靴を手に
あやとりに橋現るる夕立かな
真白き箱折紙の蟬を入れる箱
汝まるで吾白小泉匂ふしづけさの
雁ゆくをいらだつ水も今昔
秋淋し日月ともにひとつゆゑ
秋深む充実の緋を身にまとひ
平野皓大選
芹なづな小雨ながらに傘の紺
雨多き梨の蕾となりにけり
疼痛のたとへば花の水面かな
来て夜は沖のしづけさ蟬の穴
流されて靴うしなへる氷旗
秋草を経てくつきりと丘にゐる
擦りへりて月光とどく虫の庭
里芋が滅法好きで手を叩く
秋の皿葉書の隅のはるかな帆
烏瓜見事に京を住み潰す
丸田洋渡選
枯蓮を手に誰か来る水世界
松の葉が氷に降るよ夢ふたつ
水の中に道あり歩きつつ枯れぬ
疎密ある春の林の疎を歩く
水動き止まず止むとき月日貝
白昼を鯉にまみえし泥煙
雲は雨後輝かされて冷し葛
夕暮は金魚の旬と昔昔
暇すでに園丁の域百日紅
ゐて見えぬにはとり鳴けば唐辛子
吉川創揮選
鳴るごとく冬きたりなば水少し
帆畳めば船あやふさの春の闇
鳥たちのうつけの春をハトロン紙
雨は野をせつなくさせて梨の花
芍薬の夢をはなれて雲平ら
真白き箱折紙の蟬を入れる箱
十月を針の研究してゐたり
窓の雪料理に皿も尽くる頃
松の葉が氷に降るよ夢ふたつ
雲は雨後輝かされて冷し葛
〇はじめに
柳元:今回の企画の意図を説明しますと、生駒さんの『水界園丁』という句集を読みましょう、というものです。もともと「帚」がスタートしたときから企画としてぜひ話したいねという話はしてたんですけど、なかなか時間もなく、それ以上に怠惰なのでのびのびになってしまいまして……。しかしその『水界園丁』が田中裕明賞を受賞して、これはいいタイミングだということで、今回『水界園丁』を読むという機会を「帚」で設けようという感じになりました。
それで、臨むにあたって4人それぞれ10句選してきたわけですが、zoomに4人集まるまで、平野とお互いの選を見てたんですけど1句も被らなかったよね。
平野:うん。いい具合にばらけました。
柳元: 吉川と洋渡くんの選をまだちゃんとは見れてないけど、多分四人とも結構バラバラだったのかなと思う。だから『水界園丁』には四者四様の好きなポイントがあったりするのかなと何となく思うんですが、その辺、最初『水界園丁』を読んだ感想を軽く話してから本題という感じでいきましょうか。と、その前にまず装丁のお話を。
〇装丁
丸田:まず僕から簡単に、装丁について触れておきたいなと思います。この装丁の綺麗さ・仕上がりはツイッター等でも話題になっていましたが、本自体への気持ちの入れ方が明確に見えていいなあと思いました。手触りにこだわりがあるのが大きいなと思います。つるつるのページとざらざらのページが交替するっていうのはインパクトがあるし、その特徴が句集の句の印象ともマッチしていました。
フォントも、昔の句集を思わせるもので、リスペクトというかどこに自分を立たせるのかという姿勢を感じます。表紙の厚み(角のある方の……)の部分にもタイトルと筆者名が書かれてるし、裏表紙にも彫られてるし、すごいタイトルと名前がアピールされているのは少し不思議でしたね。愛着でしょうか。全体としてまた開きたくなる句集って感じがします。句を見るためだけではなくて、「紙」をもう一度開きに行くような。
柳元:思うのは、生駒さんの句集に力が入ってるっていうのは、「残っていくこと」を肯定してる感じだと思うんですよ。自分が読んできた句集と同様に、自分の句集も同様にその1冊になればいいなという気持ちがある気がしていて。本として残っていくことに対するわりあい素直な感情があるんだなと。福田若之の『自生地』とか、歌集だと千種創一の『砂丘律』とかあるじゃないですか。『砂丘律』の後書きには、砂のようにぼろぼろになってほしいみたいなことが書いてあるし、福田さんの『自生地』も日に焼けることを望んでる本だと思っていて。そういう一回性の志向は、どちらかというと生駒さんの句集には希薄かなぁ、というのが装丁から感じられますね。
丸田:句集って、まだまだ装丁が適当なものって多いじゃないですか。適当というか、そういうとこに力を入れずにシンプルにするのが俳句なのかもしれないけど。最近は凝っているものが増えてきたように思いますが、こういうパターンはいいなって思いますね。内容と響き合っているし、魅力的です。
柳元:ふらんす堂の洋装も好きだけど、画一的なのはやはりつまらないからね。句集の装丁はもっと凝っていいなとは確かに思いますね。アンカットとか。そういう点で、港の人から出ている詩歌集はとてもよい感じがします。
〇『水界園丁』全体の感想
柳元:さて、ではまずざっくりと句集全体の印象について、自分の10句選あたりを手がかりに触れていきますか。平野あたりから、どうでしょう。
平野: 10句選がかなりやり辛かった(笑)。他の句集だったら同じラインの句で見比べながら、こっちの句の方がいいかなとかできるんですけど、『水界園丁』の場合は、句の作り方が多様で読み筋がいろいろあって……過去に書かれた句の、どこの文脈を使って読むべきか定めにくいし、その点で自分が分からない句も多くありました。この多様さは特徴として面白いと思う。
柳元:ふむふむ。僕は自分の10句選の中では、わりとこう、ヒューマニズムが出てきてる句が好きだなぁという印象ですね。気象の動きとか天体とか植物に気持ちを寄せながら、助詞でレイヤーをいじって作っていくみたいな作り方の句が多いけれども、結構ヒューマニズムを感じるんですよね。俳句を信じるというメタな意味でもそうだし、もっと直接的には、人称や呼びかけにしても、「あなた」とか「汝」とか「吾」とか色々ありましたけど、人が出てきて、その人への感情が読み取れるような句が僕は割合好みでそういう句を多めにとった気がします。洋渡君はどうでしょう。
丸田:はい。僕はだいたいの句集が、全体で見ると良い句の数は少ないような気がしてて(そこを魅力としていないものが多いというか)。でもこの句集は全体的に平均点が高く、良い句が多い印象でした。あと、先に触れたとおり、ページの肌触りとか、 句の空気感とかが全部合っていて、読んでいて凄く心地よかった。ざらざらとつやつやのページみたいな感じで、ぼんやりした句もあればはっきりした句もあって。ちょうどよくまた見たくなる感じで。
柳元:ぼんやり、はっきりって話が出たけど、読んでみたら花筏の写生の句とかがあったりして、意外と写生の句もあるよね。ぼんやり一辺倒ではないというか。ふむふむ。吉川君どうでしょう。
吉川:はい。なんだろう、そのぼんやりって話といっしょで、なんか一読では読者が100%この句のことを掴めたとは思えないんだけど、思えなくて大丈夫というか、思えなくても良い心地よさがあるというか。
柳元:うんうん。
吉川:そういう、良いぼんやりってのは確かにあるなぁっていうのは洋渡くんと同じ意見かなと。句集をたくさん読んできたわけではないけれど、句集を通して読んで『水界園丁』というタイトルが凄くしっくり来るっていう点で句集してのまとまりを自分の読んできた句集と比べて感じました。
柳元:ありがとう。そうですね、句集としての完成度とか一冊としてのまとまりというのはすごくありますよね。えー、まああの、4人とも、まだエンジンかかってない感じがするので、読者の方もう少しお付き合いください(笑)。
〇個々の句について
柳元:さっきも言ったけど、ヒューマニズムが出ている句が好きだったという感じですね。もちろんそうそうじゃない句も好きで、選んでない句で言えば吉川が挙げてくれてた〈帆畳めば船あやふさの春の闇〉とか。第4回芝不器男俳句新人賞の一次選考通過作品に入ってた句で、ネットで見てた高校生の当時から好きでしたね。でも、これは技術というかレトリックが前景化している感じがする。繰り返しますけど、好きではあるんですよ。
でも、そうではなくて、もっと何かを信じている感じのする句というか、もっと暖かさが出ている句というか。鋭利なものというよりも、まるまった鉛筆で書かれた、不器用さのノイズがある句というか。しかもそれがレトリックを抑えて書かれたわけではない、というのが凄いなと。
具体的に言えば〈五月来る甍づたひに靴を手に〉なんか、その世界線がパーマンみたいな感じで凄く好きですね。あと〈汝まるで吾白小泉匂ふしづけさの〉とかも非常に好きでした。操作は複雑なのだけど、書き味があります。それから、抽象的な書きぶりも凄く好きで。〈秋淋し日月ともにひとつゆゑ〉〈秋深む充実の緋を身にまとひ〉とか。ざっくりですが。平野君どうでしょうか。
平野:うん。そんな自分の中で基準を決めて選をした訳ではなかったんですけども、例えば〈秋草を経てくつきりと丘にゐる〉とか、周囲の世界を自分がどう感じているか、捉えているのか、がよく分かる句が好きでした。体調や天候、直前に聞いていた音楽で、世界の捉え方ってまったく変わるから。秋草を経たことで自分自身を「くっきりと」感じられる感覚が面白いなあ。でも、なんとなく分かるなあと思ってみたり。
〈擦りへりて月光とどく虫の庭〉も、虫の音を聞いているうちに月光が擦りへって見えてくる、と知覚が変化していて。これは実景というより内面的に景が描かれています。けど本人にとってはあくまで実になるし、焦燥感も見えてくる。
柳元:平野の選、僕と比べたらかっちりとした句作りの句が多い気がするな。
平野:確かに。自句の推敲も妙にかっちりさせてしまう。
柳元:脱線させてしまいました。じゃあ洋渡くんどうでしょう。
丸田:はい。柳元くんとは逆に、僕はレトリック重視で選びました。この句集の10句選ではこういう句も入れた方がいいかなぁと思いながら選びましたね。〈水の中に道あり歩きつつ枯れぬ〉とかは、その写生の句とかと並んであることによって、いかにも本当にあったかのように話しているみたいな感じがして。「歩きつつ枯れぬ」にはちょっとふざけてる感じも思うんですけど、それもちょっと納得できるような世界観、空気感の作り方みたいな。〈枯蓮を手に誰か来る水世界〉も、さっきの「枯れ」と「水」のイメージで、句同士の共鳴のさせ方みたいなのが他の句集よりも見えやすく、しかも良い方に行ってるなと思って敢えて選びました。〈疎密ある春の林の疎を歩く〉、〈水動き止まず止むとき月日貝〉とかのてんこ盛りのテクニックも僕は好意的に受け止めて、 かっこいいなあと思いました。あとシンプルに表題の〈暇すでに園丁の域百日紅〉が個人的にとても好きで。かっこつけてるようでいて、気取っていない。気取ってないようでかっこつけてる。文字面もかっこいいし。成功している表題句だと思って今見ても凄いなと思います。
柳元:うんうん。吉川はどうですか。
吉川: 自分は明確な基準は設けずに、句集を読み返しながらとっていきました。皆が挙げてない句で言うと、〈鳥たちのうつけの春をハトロン紙〉、〈芍薬の夢をはなれて雲平ら〉とか一句の中で切れを明確に設けずに助詞で繋ぎながら「鳥」、「うつけの春」、「ハトロン紙」と少しずつずらされながらイメージが展開されていって、読者からすると意外な広がり方をするというか、最後に意外なところに来てしまう感じが好きでしたね。
柳元:うむ。よいよね。
丸田:吉川チョイスな感じがしますね。〈雨は野をせつなくさせて梨の花〉とかは多分僕はとらないだろうし。
吉川: 確かにこれはみんな取らなそうだなと思いながら、ですね。
〇『水界園丁』の句に見る筆者の手つき
柳元:句を見てると凄く分節化されてる感じがするというか、コントロールが行き届いてない空白のところとかが、限りなくない感じがする。初学のころって、俳句を作るときって多分3分割ぐらいから始めるじゃないですか。5音、7音、5音の3つに分けた部分をどう埋めようってところから始まると思うんですよ。3分割に分けて作ったり、慣れてきたら5分割くらいに分けて作ったり。でも生駒さんの場合はこうもっと、それこそ15とかのブロックに分節することができていて、そのブロックを分節する中で、抽象度が上がったり下がったり、その中で処理している感じがあるかなというのは、見ていて思うというか。
例えば、〈汝まるで吾〉みたいな入り方は、普通に書いていたら絶対にできないと思うんですね。こういうの凄いなって思いますね。凄く細かい区切り方、凄い小さな拍を刻むことができる人なんだなあという感じがする。4拍子とかじゃない感じ。もうほんとに16分とかもっと細かい形でもちゃんと刻めるし、あと〈鳥すら絵薺はやく咲いてやれよ〉みたいな、変拍子っぽいリズムもちゃんとノリながら作れる感じ。そういうのが好きですね。
平野:それは型とも関係があるんじゃないかな。型が最初にあって、型に何の語をどこに当てはめるかを考える。そのとき、型を何拍子に区切って使おうかみたいな話が出てくるんだと思います。でも、その型を型どおりに使うんじゃなくて、かなりずらして作ってるのが凄いと思うんだけど。
柳元:そうだね。型を想定して、そこからノッたりソッたりを繰り返しながら一句に書きつける感じ。
平野:例えば〈来て夜は沖のしづけさ蟬の穴〉の「来て〜」って入り方は〈来て今し冷たかりける蠅の肢〉という句が三橋敏雄にあるんだけど、その上五を分節しているのかなと思った。蟬の穴が三橋敏雄っぽいせいかもしれないが。
柳元:ほほう。そういえば、週刊俳句の上田信司の記事の孫引きになりますが、生駒さんは〈里芋が滅法好きで手を叩く〉は「滅法」から作ったと生駒さんが言ってるらしいですね。生駒さんは明らかに、語からスタートするタイプだよね。しかも、ただの語からスタートするタイプじゃなくて、語の意味だけでなく、語のアドレスというか、住所まで勘定に入れながら、面白がるというか。〈来て夜は沖のしづけさ蝉の穴〉は、〈来て〉が句の頭だから、面白い。
平野:あぁ。よく分かる。
柳元:憶測でしかないけれど、ほとんどの場合こういう句の作り方をしているんだろうなという感じがしますね。言葉がどの位置に入ると一番こう言葉としてうまく活きるかを他の言葉との兼ね合いの中で、四則演算をしながら決めている感じというか。
丸田:その器用過ぎるところがちょっと怖いなと思ったりもしたけど。
柳元:というと?
丸田:なんか、ラッパーが上手い奴に対してアイツ上手すぎて恐いわーっていう時の怖さというか。
一同:(笑)
丸田:ビートが鳴ってすぐ乗れるタイプのあの恐怖というか(笑)。
吉川:畏怖?
丸田:うん。まあ全然的を射てない喩えかもしれないんですけど。俳句について博学で大量に型を持ってて、こう、「滅法」とかも一個単語を思いついただけで、どの型使えばいいか分かるんだろうなあっていう。そこが凄い。そうですね、畏怖です。
柳元:うーむ、ぼくはわりと生駒さん、R指定みたいな感じかなぁとおもう。ゴリゴリの意味で通す呂布とか、天性のフロウの感じがある鎮座とかじゃなくて、わりと蓄積型っぽい。正解の型を一つ持っててその正解にすぐ辿りついてる感じじゃなくて、書きながら考えてるんだよ、なんか。
平野:うん。
柳元:なんだろうな。計算してる時間が、句の中にメタ的に書き留められてる感じがするというか、「滅法」って言葉からスピーディーに決まるんじゃなくて、もっと時間がかけられてる感じがする。中山奈々さんの〈バンダナで縛るカーテンほととぎす〉という句について堀下翔さんがスピードの速い取り合わせ、という様なことを言ってたんですけど、それでいうと『水界園丁』のスピードは、概してかなり遅いのかなと思いますね。
丸田:さっき拍の話があったけど、語がすごい刻まれることでスピードが遅いように錯覚するっていうのはあるよね。「カーテン」みたいな単語のスピード感はなくて、〈来て夜は〉みたいな作者の考えが見える書き方が、相対的にスローに見える。
柳元:うんうん。句が立ち上げようとした景を読み取る、というのが写生句の読み方になるけど、生駒さんの句の場合は意味とか景の立ち上げと同時に作者の手つきにも気を配らないと読めないというか。メタな視点が句に織り込まれてるから、それを読み取ることが前提となっているというか。句の意味や景とは別に、生駒さんの書いている手つきを鑑賞するみたいなところがある気がする。それを含めて俳句を読むということなのかなと。生駒さんのは、むしろ、その手つきの方がおもしろいというか。
平野:多作多捨みたいなことではないよね。
柳元:そうそう。波多野爽波は、写生をする時に余計な主観が入り込まないように、つまり無意識に言葉が一番良い形で出るから、という理由で俳句のデータベースを使っていたけれど、生駒さんの場合は違うよね。
平野:一句にならない段階ですごい捨ててるような感じがする。型がいくつか自分の手元にあって、試行錯誤しながら当てはめ当てはめ、途中まで作ってみても「うーん、この型じゃないな」って捨てるっていう、型の多捨をしてると思う。
柳元:なるほどたしかに。すごい数の分岐があったんだろうなって感じするよね。
平野:そうそう。
柳元:一つの分岐の結果から、捨てられた分岐の面影が見える感じがする。うまく言い留めれていないけど。
〇引用とその態度
吉川:『水界園丁』を一読した時に、この句集が今までの俳句が詠もうとしてきた世界観の中にあるんだってことはなんとなく感じてたんだけど、週刊俳句の記事であるとか、他の人の感想を読んではじめて、過去の句を参照しているであろう句が多くあることに気づいたのね。そういう句をどう皆は読んだというか鑑賞したのか気になりました。
平野:過去の句を参照してるって気づいた句はそう読んで、その句を踏まえることでどう良くなっているのかを一応考えはしたけど、深く掘り下げはしなかったかな。
吉川:なるほど。
平野:それよりも俳句の空間があるなーという感じで。確かにこの句があの俳人のあの句を参照してる!いいね!っていうのは目立つけど、それだけじゃなくプレテキスト……過去の俳人たちが練り上げてきた俳句空間の中で、自分が持てる知識を総動員して書いている感じがした。
吉川:あー分かる。
平野:単体の句これを参照してる!ってだけの話じゃないよね。
丸田:僕は昔の句、写生の句とかの知識があまり深くないので、ぼーっとしながら読みましたね。気づくとかが起こりにくいから、その一句がかっこいいかどうかで見てました。分かる人には分かるんだろうな、とはびしびし思いました。
平野:そう、だから勉強すればするほど面白くなる感じがする。この句があの句と繋がっているというよりかは、俳句という空間みたいなのがあって、それを引き継いでる感じがするという話。
吉川:この句集自体がそういうもの。
柳元:うん。引用ってプラグマティックというか、その元になっているものに対する愛情ゼロで道具的にされる引用と、そうじゃない引用ってあるじゃないですか。それへの愛着を示しながらそれが大好きなんですみたいな身ぶりの中で行われる引用と。で、生駒さんの場合、めちゃめちゃ後者だなと思うんですよね。例えば、季語を入れて作句しますってなった時の、その季語を入れるっていうのは前者というか。いやまあ、季語を好きな人はいっぱいいると思いますけど、季語を引用すること自体に深い意図はなくて、透明なかたちで行われていると思うんですけど。
生駒さんの引用は何か引用すること自体が一つのめちゃめちゃ大事な行為というか、先行句がこれです! というよりは、その引用するという行為自体の方法論的な位置づけをもう少し考えたい感じがしますよね。俳句というものに対して愛情を示している気がするから、俳句の全体が見えるみたいな評は、僕もそんな気がしますね。
丸田:道具的か愛着があるかっていうのは、俳句をやればやる人ほど分かっていくというか、これが引用だなって気づく回数が多いほどその態度に気づきうる話で。僕とかはあんまり知識がないからどれぐらい汲んでいるのかはあんまり分からなくて。生駒さんは結構その道具的な操作で句を作れるタイプだと思うので、どこまで愛着を持ってやっているのかっていうのは、ツイッターで皆さんが「この句はあの句を引いてるね」って言ってるのを見てやっと分かったぐらい。根本的な話ですが、やっぱり、引用って、分かる人にしか分からないみたいな問題はずっとあるなぁって思いましたね。
柳元:プレテキストを厚くするって、どちらかというと閉じていく方に書かれていくってことですよね。なんかそういう問題は考えたい感じが凄くしますね。俳句と短歌、なんでこんな人口が違うんやみたいな話、やっぱその短さとかも勿論ある思うけど、プレテキストが厚すぎるってのはやっぱりあると思っていて。季語とか勉強しないといけない、元々内輪で共有されているものを理解しない者は拒む、っていう態度がやっぱり俳句にはあると思う。プレテキストが厚いというのはさらにそれを加速させるわけじゃないですか。
平野:怖いところ。
柳元:その引用先が分かんないと、面白みが半減ですよみたいな句作りは、対象とされる層、生駒さんが読まれたい、想定する読者の数はどうしても少なくならざるを得ないんですかね。
丸田:うん。でも圧倒的にサンプリングするっていうのは、その俳句への態度の一つの解になってるなとは思いますね。
柳元:うん。
丸田:他の句集ではここまで俳句空間を引用してる空気感を感じてこなかったことを思うと、(自分が先行句に気づくタイミングが増えたというだけのことかもしれないけれど)一つの大きなパワーを見せられた、という感じがします。
〇俳句にある母子関係
柳元:引用というか、そういう俳句のプレテキストの話に関連して、外山一機さんが最近noteを更新されてて、それが生駒さんの句集などを主に論じている感じ(note「第二句集の季節」)なんですけど、僕はこれが生駒さんの世代を言い当てているなあという感じが凄くしましたね。
まど・みちを「ぞうさん」の歌詞を引いて、『自分の鼻が長いのは母親が長いからであり、その母親が好きなのだ、という全肯定で多幸感に満ちていて依存的な母子関係は、俳句形式とそれに携わる若手の姿とよく似ている気がする。』と指摘して、『書けるのはいつも、少し余裕のある、俳句形式で書くことをすでに自明視しているかのような、そんな句である。』って言ってるんですけど。
この母子関係っていう比喩はなるほどなと思ったんですね。俳句という母があってその子であるという。出藍の誉れ、のように、子供が親を超えるってことはもちろんあるんだろうなって世界線なんだけれども、でもその親があること自体は自明視しているというか。藤田哲史さんの『楡の茂る頃とその前後』って句集を読んでいて、句末のかな切れが「です」になってる100句があったじゃないですか。その試みっていうのはどちらかというと、母子関係を断つ方だったんだなあっていうのは何となく思いました。母子関係を否定する試みで、生駒さんの句集は母親の愛情みたいなものの中でこう書かれていたんだなあという感じが何となく。
丸田:母子、っていうのはちょっと危うい例えだと思うけど、分からなくはない。守られているのを分かってて、それを承けてちゃんと書いてるオーラみたいなのはありますね。楡の方はロンリーというか、『水界園丁』のオーラ感とはちょっと違いますね。
柳元:そう、だけど、藤田さんの句集は、結局はその母から離れられないみたいな、そういう痛みの句集だった感じがするけど。『水界園丁』はもうその母親どっぷりの中で、いかに書くかみたいな感じ。
平野:どっちもどっちな感じがする。例えば、郊外ってあるじゃないですか。千葉皓史の句集じゃなくて、普通に郊外。
柳元:都市の外に広がる、あれ?
平野:そうそう。消費社会を進めるために土地の個性がはぎ取られて、どこも均質化されていくんだけど。かつての個性をはぎ取った反省から、そこにまた土地の個性を活かした建物を建てますとなった時に、本当の意味でその土地の個性を持ってこれるのかみたいな話になる。つまり俳句という空間が広がって、それが郊外みたいなものとして、その中でなにかを断ち切ろうとしたところで、それは本当に断ち切ることになるのか。ただ均質的な広がりの中で、情報をいじくっているだけじゃないのか。しかも均質的な空間はこうしたいじくりがやりやすい。土台が出来上がってるところで何やっても仕方ない……
丸田:うん。もうあとは姿勢の問題だよね。断ち切ろうとしているかどうかみたいな。
平野:そう、姿勢で見せるしかない感じがする。ただ、姿勢の違いでしかなくて本質的なところはあんま変わんないんじゃないかって。悲しいところだと思う。
〇平成俳句の限界
吉川:平成俳句の限界、みたいな話の方向になってきたね。
柳元:限界っていう話だと、外山さんが言うように第一句集を持ちえない世代になってきてるわけじゃないですか。わけじゃないですか、っていう言い方は、断定的でよろしくないけど。
平野:持ってるように見せかけることはできるけど根本的なとこで持ってないよね。
柳元:うんうん。そう、前、お酒飲みながら平野とも話したんだけど、安里琉太さんの『式日』とか、岡田一実さんの『記憶における沼とその他の在処』、藤田哲史の『楡の茂る頃とその前後』とかは、(岡田一実さんのは数としては第3句集だけど)外山さんが言う意味での第2句集にあたるのかなというのが思うところで。でもだからといって、第一句集を書くことには戻れないというか、帰還不能点をもう超えちゃってるじゃんと思っちゃう。
飛行機があるじゃないですか。で、離陸する空港と着陸する空港があって、あるポイント超えたら燃料の関係で、前の空港にはもう引き返せないポイントがあるわけですよ。第二句集スタート問題は、もうそれを越えちゃってる感じがする。第二句集しか書けない中で、いかに書いていくかみたいなところがすでにあると思う。僕はすぐデータベースって言っちゃうけど、そのデータベースの話も一回ちゃんとまとめないといけないという気がしていて、それはまあいつか文章書きますけど。
1970年ごろには、野村登四郎が「伝統の流れの端に立って」という俳論を書いてて、草間時彦が「伝統俳句の黄昏」と言ったりしてるわけですよ。この時期、もう伝統俳句の終わり側にいるんだみたいなものがあった。80年代ではもう完全にその龍太と澄雄の時代みたいになったけど、でもイデオロギーとしての伝統俳句っていうものはなくなって消費社会的な俳句のありようにだんだんすげ替わってるような感じがしていて。上手い俳句は書けるけどそれがイデオロギーを伴っているわけではないみたいな状態が80年代ぐらいからずっと続いてるんだろうなあという感じがします。現代詩も結構似たような動きしてる気がするんですよね。短歌はライトヴァースという「やること」があったので、まだイデオロギーを伴えている感じがするけど。
平野:そう。柳元が昭和30年世代と渋谷系音楽は似ているとよく言うことをふまえて、俳句に関係ない本を読んで思ったことなんですけど、80年代にパルコが渋谷をつくったじゃないですか。その時に、3つの外部を隠蔽したって北田暁大が『広告都市・東京』(筑摩書房 2011)で言っていて。
説明しづらいけど、1つ目は〈資本〉という外部=リアル、これは資本を季物に置き換えると分かりやすくて、季語がリアルな季物と密接に繋がるというより、ただの言葉になってしまった部分がある。それで次の1つは「批判」という外部、ここが多分、詩の中で批評家がいないの話だったり、平成無風と繋がりそう。あらかじめ、向けられるだろう批判を古くさいものとして記号化しておく、すると全てが記号になってしまい批判までもが方法論として受容されていく。角川俳句の話に疎いから何とも言えないけれど、どうなんだろう。それで後1つが「記号には汲み尽くされない私」が隠蔽された。って言ってる。これは確かに俳句とリンクするなって考えてたのね。
柳元:ふむふむ。
平野:引用しちゃうと『以上のように「資本というリアル」「批判」という外部が構造的に隠蔽されると、広告=都市に内在する人びとは、その外を眺めることができなくなってしまう。つまり、広告=都市が提供する記号から距離をとり、外部に目を向ける起点としての〈私〉が禁じられるのだ』(p. 93)。
つまり、広告=都市を前に話した俳句の空間みたいなものとして、そこでは季語が季物に繋がらないし、批判もない。波郷みたいな「俳句は私小説」はありえない。私小説的な「記号には汲み尽くされない私」はもう存在せず、記号をどう「私」が身につけるか、っていう「私」のあり方になってくる。そんなアイデンティティのあり方、ここらへん『なんとなく、クリスタル』でよく言われる話で。『水界園丁』の「私」の出し方も似ていると思った。
柳元:それは普通に面白いね。たしかに、明らかに80年代以降の流れで生駒さんは書いてる気がする。『水界園丁』は平成俳句の集大成みたいな感じで言われがちですけど、平成っていうよりは80年代以降のものの集大成という感じがどちらかというとする。小川軽舟が言う昭和30年世代の蓄積がさらに一歩進んだ形で現れている句集というか。
平野:うん。
柳元:昭和30年世代の岸本尚毅とか田中裕明の句のデータベースを生駒さんは使ってるわけだしね。
平野:これはまた別の本(細間宏通『浅草十二階』青土社 2011)を読んで教えられたことだけど、パノラマってあるじゃないですか。
一同:うん。
柳元:平野、さいきん都市論ばっかりやってるのね(笑)
平野:そうそう(笑)。その本の中で、パノラマが「臨場感」をもたらすならば塔は「一望」をもたらすと言ってる。まずパノラマ館と塔の違いがあって、パノラマ館はその館の中に入ると、ぐるりに絵が飾ってあって、戦場の絵だったら自分が戦場に存在しているような臨場感がもたらされる。一方で塔は最上階に上ると、眼の前に景色が広がってはいるけれど、遠さとか大きさの手がかりが乏しい。それで、ただの景色の集積として見えてくる。そこに自分が存在しているような臨場感はないんだって。
昭和30年世代と現在の違いって、パノラマと塔みたいだなって最近思ったのね。つまり昭和30年世代はまだ俳句の空間がまわりにあって、自分がその中にいて句を詠めるんだけども、生駒さんとかは塔に登って色んなものを俯瞰して見てるようなだなって。
柳元:それはあると思います。だって昭和30年世代の人たちは、小林恭二の『俳句という遊び』とかを読んでて思いますけど、まだ飯田龍太と実際に句会をできた世代なわけで。俳句の凄み、みたいなものはあったんだろうな。
でも、僕らが俳句を始めた時にはもう飯田龍太は亡くなっていて、俳句が終わった後に俳句をいかに延長させるかみたいな。延長させるって言い方はアレなんですけど、俳句という枠組みをいかに延命させながらやっていくか、みたいのがある気がする。現代美術とかとも似てますよね。デュシャンの『泉』はレディメイドの便器をそのまま出したものだけど、美術って美という価値が自体が成り立たなくなっているときに、美術作品ですらないものを美術作品という枠に当てはめることで、美が終わってるのに美術という現象自体を延命させようとする。そういう遊びを、作者と鑑賞者の間で成り立たせているのが現代美術の空間だってことを、ボードリヤールが言ってるんですけど、それと俳句は似ているなあと。
俳句という遊びを皆でやることによって俳句は延命しているけど、実際は俳句というイデオロギーを伴ったものは、こと切れてしまってるような気もしなくもないというか。そう思った時に子規って凄いなと思った。1回終わってるものを強制的に蘇生したわけでしょ。全然違う写生っていうパラダイムをもって、俳諧と全く別のパラダイムでやりましょう!今日からいっしょにこれやろうぜ!って言って、それを今我々がやってるわけだから。そういう強制蘇生的な何かをしないと。これからもずっとこういう、それこそ生駒さんみたいな形で俳句を延命させる遊びをするしかないのかと思うと。いやまあ、たかが俳句を数年やってるだけの大学生が何言ってんだ(笑)という感じですけどね。
丸田:まぁ大学生だからこそ言える、みたいなものもあるでしょう。
平野:蛮勇ですよ。
柳元:野蛮ですね。
丸田:でも言わないといけないことですよ。
柳元:そういう意識で書いてくしかないんだろうなぁ。
丸田:意識的にならないと、我々が『水界園丁』をもう一度書く可能性があるわけだからね。
柳元:クオリティの問題はもちろんあるけど、そう。洋渡くんだって意地悪な言い方をすれば、現代詩や短歌などの別のデータベースを参照してるに過ぎないのかもしれないしね。
丸田:間違いない。
柳元:僕は岸本尚毅、田中裕明、宇佐美魚目、赤尾兜子と、生駒さんと参照データベースが被ってるわけです。そうなると『水界園丁』好きだったけれども、そういう意味でのきつさはあったよね。『式日』とかでもそうですけど。
平野:あのレベルで書けるってのが凄いけどね。
柳元:そうだね。レベルバトルになる。
吉川:戦う次元が枠組みの中で上手さを競うことになっちゃう。
柳元:外山さんのnoteに話が戻るけど。俳句を選ぶのがどういうことなのかという問いがないっていう風に外山さんは言い直してるけど、たしかに僕も俳句というものを選んだっていうことに対する意味とかは特にないな。俳句を選ぶきっかけがあったから俳句をやってるにすぎないから、それに対して外山さんがこういう苛立ちを抱くってことが一番面白かったかもしれない。でも、外山さん流に最終的に『水界園丁』を肯定する文章になってるんだけど。外山さん的にも80年代以降の流れを引き受けない形の成果はないんだろうな。『水界園丁』自体から話が遠くなってきたけど。
一同:(笑)
〇「書けなさ」と不安
柳元:オルガンをきちんと読んでないから、読んでからちゃんと言いたいんですけど、書けなさについてっていう座談会がありましたよね。そのタイトルだけみて思ったのだけれど、向き合うべきは書けなさというよりは、書けることについてもっと向き合った方がいいよなぁという気もしますよね。
丸田:間違いない。
柳元:俳句は簡単に書けるっていう言説は色々流布してるし、インスタントに俳句が作れますよみたいな入門本もあったりして。もっと話を広げて言えばAI一茶くんってのが北大でやられてるわけじゃないですか。あれだってデータベースなわけで。勿論選の段階で人の目が入ってるから価値判断まではできないというのは大きな課題ですけど、データベースを利用して上手い句が結果的に作れると意味ではやってることは変わらないわけで。ここで、人が作ったからっていう一番素朴なアンチテキスト論をかまさないと俳句が延命できないなら、うーん……って感じがしますね。今は生駒さんや安里さんがやってることは新しいけど、僕がそういう手法を真似てやっていく、そうやっていくしかないとしたら、道のりはけっこう厳しいよね。
丸田:まあでも僕は早々にその道を逸れたわけだから。それでも頑張ってる人のきらめきはありますが。辛いものもありますけどね。
平野:書けなさってあれは書けすぎてしまい、技術の巧さが先に立つから本当に書きたいことが書けませんみたいな話じゃないの?
柳元:あ、もちろんまだ読んでないから、そうだったらごめんなさい!という感じです。迂闊にオルガンの名前を出しましたけど、批判の意図はないですので。批判というか、そもそも読んでないから、引用や批評要件を満たしていないので。あとでちゃんと読みます。
丸田:初歩の言語学みたいな感じじゃないですか多分。書こうとしてることが書いたことと違うみたいな話な気がする。僕も読んでないので、読まなきゃなんですが……。
柳元:そんなことはないと思うけど、もしそうだったらけっこう厳しいね。現代の僕たちが本当に書けなさに立ち止まることがあるとしたら、それはこれまであったこと、書かれてきたことの蓄積と自分たちの関係の中で発生する書けなさで、書けてしまうことに対する書けなさって感じだな。作句しててものすごくそれを感じるわけじゃないけど、背後にそれを感じる時はあるよね。別に類想がどうこうって話じゃなく、なんか全てが……、なんだろうなあ、難しいけど。外山さんの母子的な関係っていう比喩の通りな気がします。全部母親の前で遊んでる感じがするんですね。母親に与えられた積木を崩して積み上げてを繰り返して。時折、良い積木とかブロックとかができると楽しいんだけど、でも、昔の俳句やエッセイを読むと、俳句はこういう営みじゃなかったんだな、ってすごく思う。
丸田:最近書くよりも読む方に行きたいって言ってたのはそんな感じ?
柳元:そんなこと言ったっけ?
丸田:何か句会のときに、僕は書くとかあんまり、みたいな。
柳元:そのときのぼくはたぶん、めちゃめちゃ弱気になってるし、しかも最悪なことに生意気だな(笑)。
一同:(笑)
柳元:まあでも読んでる方が楽しいもんなーと思っちゃうときあるな。自分が書くことがなんかもう無理な気がするというか。他のジャンルもそうだと思うけど、データベース化ってしちゃうとそこから抜けられないから。全部が嘘くさく感じるんですね。例えば、ロックンロールってものがあって、それが1回データベース的に、GとAとDの3コードでロックっぽく聞こえます、とか四つ打ちで、みたいなそういうデータベース的なロックンロールが成立して以降は、その音を出し続けても、全部ロックに聞こえないわけじゃないですか。魂がこもってないというか。シミュラークルって概念があるじゃないですか。プラトンのコピーなきコピーの話だけど。田中裕明の時とかはオリジナルをコピーできたけど今はもうコピーなきコピーというか。模造品、二次創作みたいな感じなんだよなあっていう感じがしますね。
平野:俳諧読んでて季語が活きているって話を、前に柳元にしたと思うんだけど。季語がしっかり実在する季物に繋がっていて、リアルな季物のシミュラークルとして句がある。リアルな季物のシミュラークルという意味で、句自体と季語が同じレイヤーにある感じがする。
柳元:「水争い」とかそういう季語のこと?
平野:そうそう。それを句で言い留めていたけれどもドンドン失われていったんだなぁって感じがして。
丸田:いい会議な気がしてきましたねえ。
一同:(笑)
柳元:どうなっていくんだろうね。短歌で同じ現象が起きないのは、口語のデータベースに移行したからまだ口語のデータベースが満ちてないだけだと僕は思っちゃうんだけど、短歌をやってる洋渡くんから見たときにそのあたりはどうなんですか。
丸田:うーん。僕からすれば、俳句はもうとっくに数十年前に限界がきてると思うけど。短歌も口語に移っただけで。もう既に口語も、学生短歌内でもかなり擦られすぎてキツイところがあるし。一字空きとか記号とか多言語とかのテクニックの余地が俳句よりまだあるから、まだ延命できるっていうだけの差であって、本質的にそんな変わりはない気はする。けど季語はやっぱり枷として重いなって感じがします。季語が邪魔だなーって、短歌やってると。さっき「水争い」が出たけど、「亀鳴く」みたいな季語も僕はもう二度と使えないと思います。
柳元:うーん。
丸田:それで言うと、「桜」とかも結構考えないとなぁって思うから、季語難しいなって感じがしますね。
柳元:その難しさはなんで?
丸田:そんなに実感してないぞってのもあるし、季語っていうものがコピー過ぎるというか、季語が自分の言いたい桜ではない桜を引きずり出しているから、かな。
柳元:うん。
丸田:前の連作であえて季語ほとんど入れないやつ作ったんだけど(「the fifth season’s texture」)。青本瑞季さんの連作(note「花の諸相/擬く・ではない・象る」)も見かけましたが、季語を外されるとそれはそれの難しさがあるから、そのラインがちょっと難しいなっていうとこですね今は。
柳元:青本さんの連作面白かったな (『俳句』2020年九月号「窃盗辞たち」) 。季語となる代替物を吉増剛造とかから取ってきてるわけじゃないですか。力のある言葉であれば、季語の代替になるっていうのは、季語を使ってないといえば使ってないけど、もう少し広い意味でいえば結局季語を使ってるのと何ら変わらない気はするよね。でも、だからこそのむなしさというか、そういうものにアクセスはしそう。
平野:言葉を消費してる感じになるよね。季語を消費してる気持ちになる。
柳元:消費に向き合うというか、消費していくことによって、むしろそれしか道がないみたいな誠実さは1つあるわけじゃないですか。言葉を使い捨てていくことでしか今のこのものを描けない空間、表象できないっていうのは、確かにあると思うから、それは確かにそうかもしれない。でもやっぱり、じゃあずっとこれやるしかないんですかって感じだよね。その苦しさはあるよね。青本さんの技術の問題でなく、そもそもの方法論が抱え込むものとして。
吉川君はどうですか、これまでの話を聞いて。
吉川:私は特に付け足すことがないからずっと聞いてただけで、言ってることは凄く分かる。皆がさっき話してたようなレベルではなくても同じようなことを感じる時はあるし。ただ、自分は俳句に対する気持ちが緩いから、自分が俳句を延命させるだけだしそういう遊びをしてるだけでしかないってことを自分は楽しめてしまうし、『水界園丁』に柳元が感じたようなキツさを感じることもなくて。長期的な目線が欠けてるというのはあるだろうけど、延命するだけの俳句を心の底からダメだとは思えないし、どちらかというと良さを感じる部分もある。俳句を生かそうという気力みたいなのはないし。
丸田:まぁそういうタイプもいるよね。
柳元:でも正面切って、俳句を生かします!っていうのは揶揄される時代になってるわけじゃん。ぼくが自意識過剰なだけかもしれませんけど。
吉川:まぁ、確かに。
柳元:一番ズルいのが、吉川みたいに、まぁ緩い気持ちで俳句を続けているにも関わらず俳句を生かそうしています、っていうのが偽善、ではないけどズルい感じがする。吉川はそれに意識的だけど、そうじゃない場合がしんどい。
丸田:中途半端だよね。
柳元:また関係のない話をすると、コロナ前に東京都現代美術館見に行ったんですけど、その時はコピーと現代アートみたいなテーマで。これまでの広告とかを野外でコピー機に入れて、出て来るとコピー用紙にコラージュされるみたいな。そこで残響を聞くことがモチーフの展示があって。その残響っていうのになんとなく『水界園丁』を思いましたね。なんか『水界園丁』をだしにして、自分(たち)の不安を語るみたいになってしまいましたが。
一同:(笑)
柳元:ではこのあたりでお開きにしましょうか。ありがとうございました。
(2020年8月27日、Zoomにて)