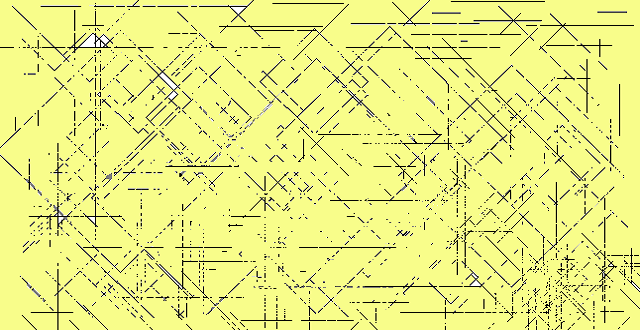所収:『髙橋みずほ歌集』砂子屋書房 2019
『坂となる道』2013 より。髙橋は独特の韻律を描いている歌人である。〈目の前の取っ手を握りドアを押す長き廊下の折れ曲がり〉(『凸』1994)に見られるような結句5音の歌が多く、〈その昔やかんの湯気も加わりてめぐる団欒〉(『 㐭 』2007)の7音分の消失、〈そこがとってもかなしくて涙がわいてくる穴のようです〉(『しろうるり』2008)のような自由律的な作品も見られ、韻律の面で多彩さを見せている。
掲歌では、一字空きも加わって、さらに表現が鋭くなっている。といっても、下の句は綺麗に77で読めるために一首自体の後味(韻律の?)はよく、前半とのズレ(速度の差)で不思議な感覚になる。
内容自体は、大きくとれば、雨が降っていて、産み落とされた時の和らぎを感じている(思いだしている)、となるだろう。大滝和子の〈サンダルの青踏みしめて立つわたし銀河を産んだように涼しい〉(『銀河を産んだように』1994)や、鬼束ちひろの「I am GOD’S CHILD/この腐敗した世界に堕とされた/How do I live on such a field?/こんなもののために生まれたんじゃない」(「月光」(作詞作曲ともに鬼束)2000)などを連想する。
産む側の涼しさでもなく、この世に生まれてしまったことへの厭悪でもない。「和らぎ」。私には少し意外な感覚で、この和らぎとはどういうものなのかいつも考えている。あたたかいのか、それとも涼しいものなのか。母と自分の関係のことなのか、空間のことなのか、世界と自分の関係のことなのか、それともその全てなのか。
ヒントになるのかどうかよく分からない前半の雨の光景。先ほど「雨が降っていて」と解釈したが、「音する 雨」はいいとしても、「音のむ」が引っかかるポイントになっている。雨が音をのむとはどういうことか(雨が主語なのではなくて、他の何かが主語で、雨がそこに挿入されていると読むこともできるかもしれない)。
「雨」といえば、上から降ってくるもの。ある意味、空や雲が産んでいるともいえるもの。産み「落とされた」という表現は雨を意識しているように感じられる。この繋がりから個人的に読んでいく。
主体は部屋などに居て(雨に当たる場所にいれば音より先に雨を感じるだろう)、音がするのを感じる。それを雨だと把握し、雨音が部屋中を包みこむように響き、他の音も雨に飲み込まれていく。空から落とされてくる雨から、自身の生まれ方を連想し、産み落とされたころの和らぎを思う。
雨に羊水、音に(自身が胎児であるときの)母の心音などを重ねるなども考えたが、そこまでになると過剰な読みになるだろう。
なんとなく分かるが、それと同じ量くらい、分からない。これは先に触れたとおり、韻律、表現も影響しているだろう。上の句の不安定なリズムに「音」と「雨」の繰り返し。
声に出して読むにも悩む。完全に定型ではない新しい型(のようなもの)をもって詠んでいる歌が作者に多いことから、私は「おとするあめ/おとのむあめ/……」の6677のように読んでいる(または、三句目が消えたと取って、66(5)77と空白の時間を取る)。定型に引きつけて、(休みを、タン、として)「おとする タン/雨 タン おとのむ/タン 雨 タン」のように空けて読むのもいいかもしれない。
前半の韻律(と表記)の不安定さに対しての後半の綺麗な77のリズム、前半の意味の不安定さ・不可解さに対しての後半の「和らぎ」。バランスが崩れている歌のように見えて、ある意味で非常にバランスが保たれた歌であると考える。韻律と内容の響きがもたらす、やわらかく美しい髙橋の歌の「味」をまた追っていきたいと思う。
記:丸田