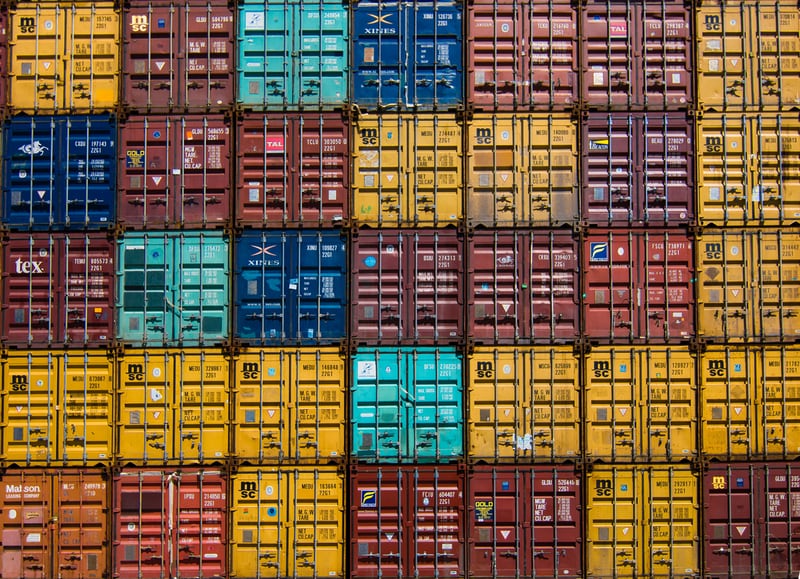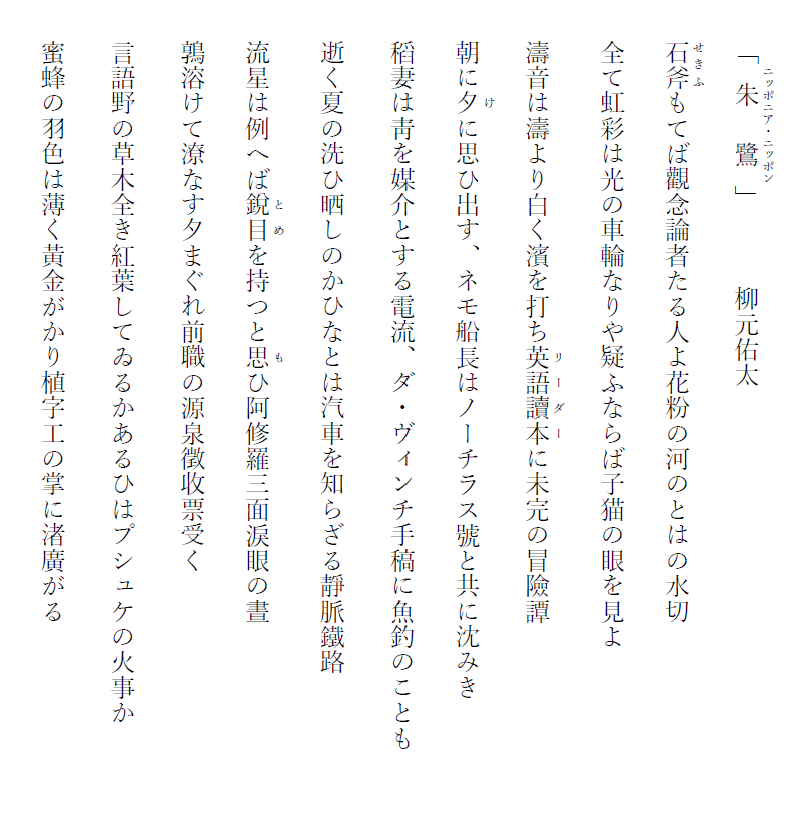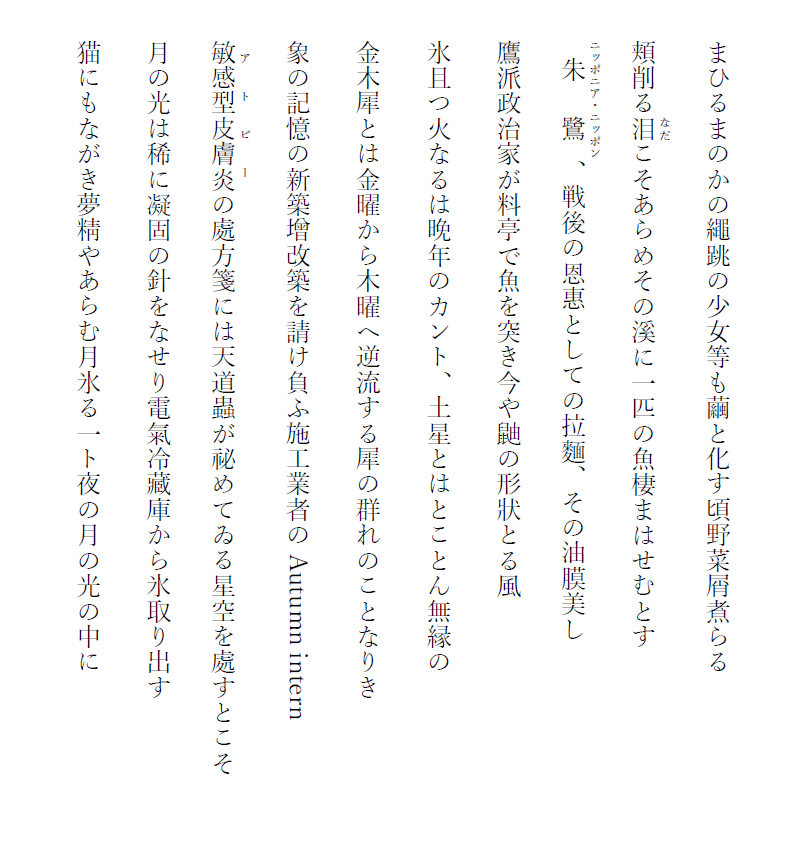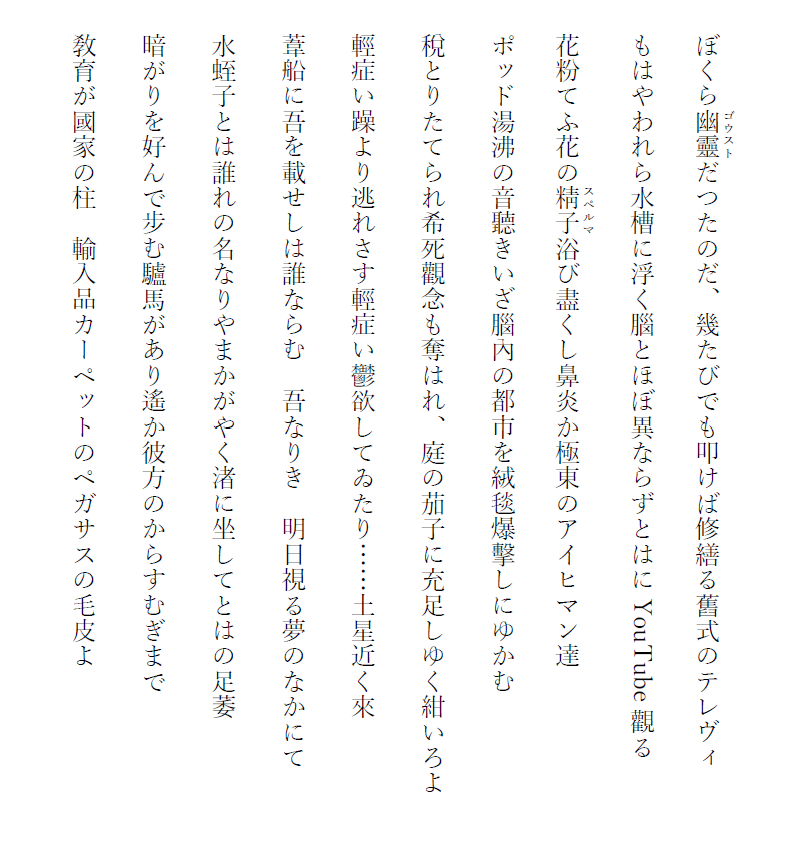所収:「現代短歌」9月号(現代短歌社、2021)
〈腹をもむ いきなり宇宙空間に放り出されて死ぬ気がすんの/工藤吉生〉をとっさに思い出す。腹始まりで、後半にかけて世界が突然開けていく感覚がする。
「腹痛の100メートル走」、という言葉を聞いて、ふつうどのシーンを思い浮かべるものなのだろうか。お腹の痛みに苦しみながらいま100メートルを駆け抜けている最中か、100メートル走をすることに緊張して腹痛が始まっているところか。「いまここで」「バトンタッチをしたい」とあるが、ここまで行ってもおそらく映像は人によって異なるのではないか。走っている最中なら、50メートル地点くらいで限界が来てしまって、あとの50メートルは青鷺に頼みたい。走る前なら、緊張と腹痛が酷いから、100メートル走自体を青鷺に代わってほしい。
別にどちらでもいいと思いはするが、その想像によって「バトンタッチ」の映像も変わってくる。自分がいま手に持っているバトンを本当に青鷺に渡すのと、「交代」の意味でつかった言葉だけのバトンタッチ。本当にバトンを渡すなら、青鷺がバトンを受けとって走る具体的な映像まで想像する必要がありそう(どうやって手? 羽? で受け取るのか、そしてグラウンドを歩くつもりなのか、飛んでも「走」にカウントはされるのか、それを快くOKしてくれそうな運営なのか……)。言葉上でのバトンタッチなら、交代するなら何でもよかったはずの主体がわざわざ「青鷺」を選んだ理由を思わせられる(青鷺を直前まで見ていたのか、急に思いついたのか……)。
「100メートル走」というと私はすっかり運動会や体育祭のイメージがある。だから無意識に、この歌の主体を高校生くらいにして読んでいる。読んでしまっている。だから、「腹痛」は運動会の緊張からだ、という読みを考慮しているわけである。
もしこれが、30代くらいの人物であったら。40代くらいの人物であったら。酒を飲み過ぎて「腹痛」、という可能性も生まれてくる。そうすると、この「100メートル走」には競技としての側面はそこまでないのかもしれない。たとえば腹痛でトイレにどうしても行きたい、トイレに行きたいぞと思っていると、100メートル先ですと書いてある。これはれっきとした「腹痛の100メートル走」だろう。
もしくは、運動会よりもさらに競技なのかもしれない。この主体がオリンピックの選手だったら。プレッシャーもかかるだろう。「100メートル走」の重みが変わってくる。
ここで謎になるのが、先に触れたように、なぜよりによって「青鷺」なのかというところ。私個人の感覚から言えば、青鷺はかなりマイナーで詩的な存在である。鳥の中でもおしゃれだし、動物の中でもかなり上位に食い込む。
これが、本当に「腹痛の100メートル走」を目にした人の発想だろうか。腹痛で苦しんでいて、思考もおぼつかないときに、ぱっと出てくるのが青鷺になるものだろうか。
疑念を覚えるのは青鷺そのもののおしゃれさだけではない。「100メートル走」で代わりたいと思うとき、そこにはふつう、地面を速く駆け抜ける動物がくるのではないだろうか。動物でなくてもいい、とにかく速く走るもの。新幹線とか。ヒョウとか。チーターとか。せめて鳥でも隼とか。「青鷺」は速く走ってくれるだろうか。優雅に川のまんなかで静止しそうなものだ。「青鷺」と漢字なのも、やや発想に時間がかかる(慣れていたらすぐだが、ふつうは「鷺」は難読の漢字である)。
それに、「バトンタッチをしたい」の言い方にも若干違和感を覚える。これは私だけかもしれない。「いまここで」と速い性急な言い方をしていたら、私であれば「バトンタッチがしたい」になる。とにかく代わりたいという意志で、「バトンタッチ」を強調する形で「が」を持っていくと思う。「を」だと、バトンタッチという行動、皆さんも知っていますよね、そう、そのバトンタッチを、青鷺にしてみたいと思うんです、というくらいのスローさを生むと私は感じる。一度落ち着いて主体が「バトンタッチ」というものを考えている気がする。
この歌のどこかで、主体(あるいは作者)が、一度冷静になって、代わりたい相手を「青鷺」に変更したような印象がある。もしくは、よくよく考えて導き出した、適当に詩的な相手という印象が。
この歌に対する全体的な私の感想を書いていなかったが、かなり好印象である。「青鷺」に対する違和感が、すごく自然だった。伝わりづらいと思うが、この歌の「青鷺」はおそらく嘘だろうし、嘘だと思われることも分かっていながらの「青鷺」だろう、そして、これが「チーター」だったらもっと「本当らしい嘘」になっていただろう、それを嫌ったんだろうな、と感じた。
この「100メートル走」は、もう腹痛が来ている時点で負けているし、「腹痛の100メートル走」とネガティブに捉えられている時点で、勝敗の問題ではなくなっている。もしここで本当に速い動物に代わってもらってその動物が高速でゴールしたとしても、もう自分自身には関係のない話になっている。バトンタッチ先が何であっても、ゴールしてもゴールしなくても、「いまここ」の腹痛が消えてなくなるわけではない。
だから、もはやバトンタッチなんてどうでも良いことである。主体にとって問題なのは「腹痛」そのもの。バトンタッチしたい、という適当な想像に、チーターや豹をもってきて本当らしくする必要はない、いっそぶっとんで「青鷺」とかにしておこう、という流れが見える。この変な誠実さというか、照れ隠しというか、痛み隠しというかが、私はすごくいいと思った。どこかで冷静になって、何かに気を遣って、「青鷺に」になっていった過程が、「100メートル走」みたいだと思った。
ちなみにこの主体は、100メートル走の完走のために、「腹痛が消えてなくなること」よりも、「バトンタッチ」を選んだ。いますぐレースから抜けたいとか、死にたいとか、排泄したいとかではなく、あくまで走り切ることを想定して、バトンタッチしたいと考えている。このよく分からない謎に力強い意志にも笑いながら惹かれた。
蛇足だが、白鳥とか鴉とか鶯とか色を持つ鳥は他にいるのに、なぜ「青」鷺なのだろう。もしかしたら、主体が今持っていたバトンの色が直感に影響したのかもしれない。この「青鷺」という言葉が即興で出てきたものか、推敲中に時間をかけて出てきたものかによっても見える景が少し変わってくるだろう。江戸川乱歩「心理試験」を思い出したりもした。
記:丸田