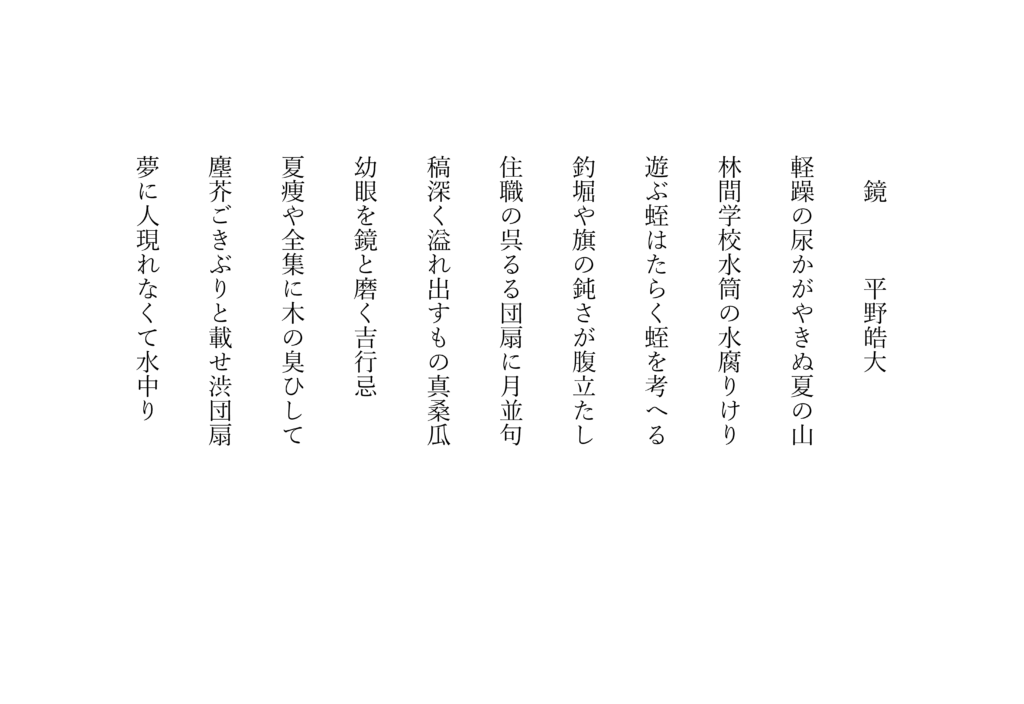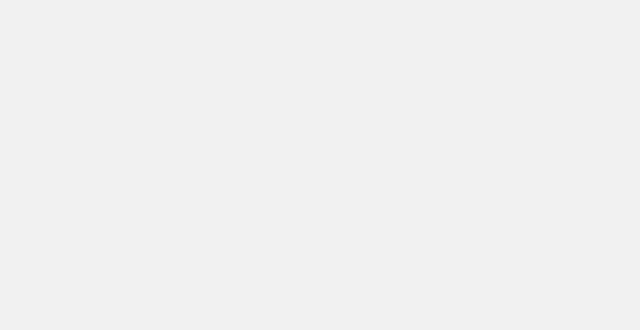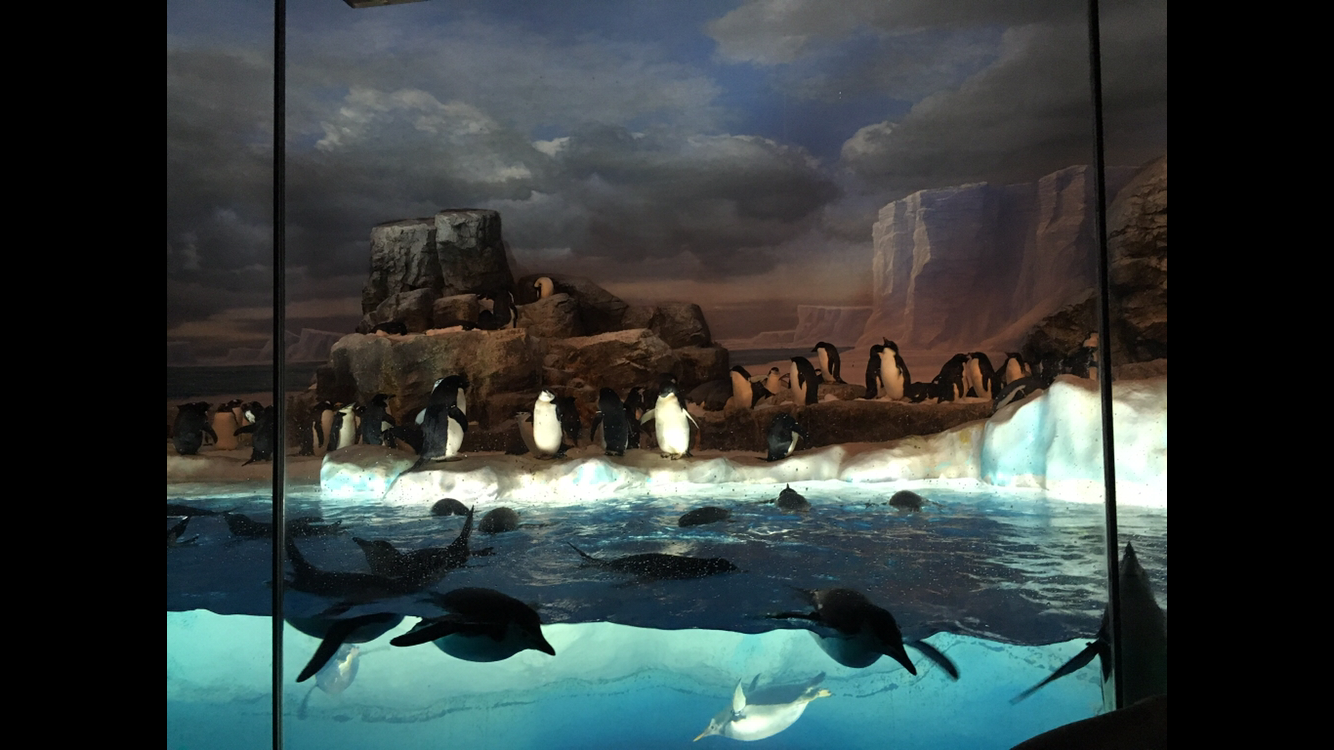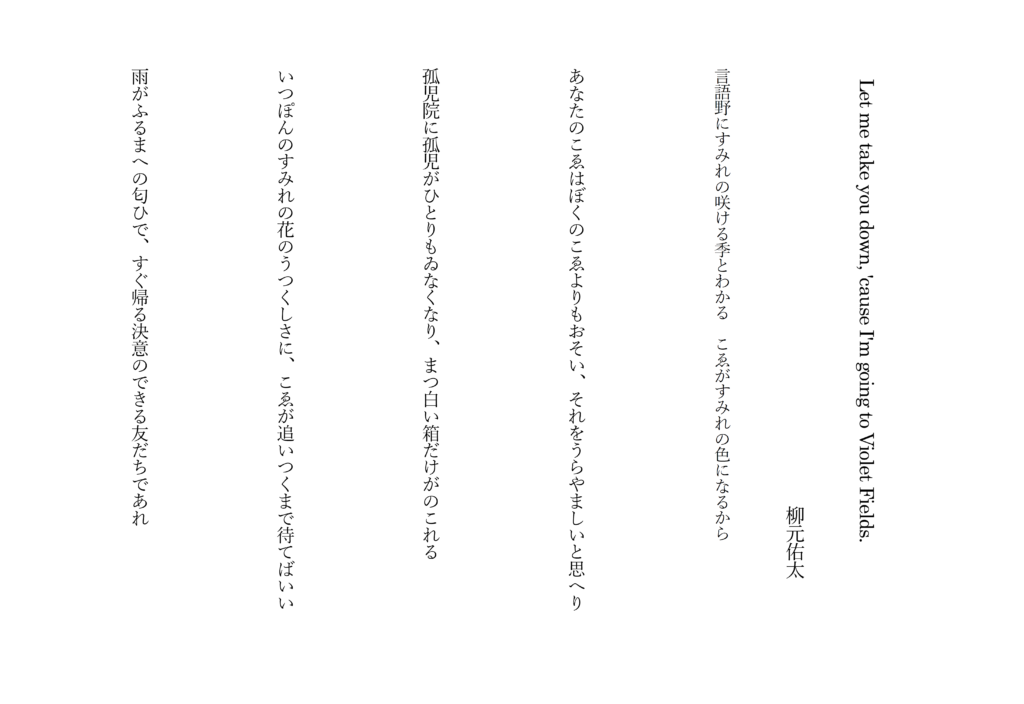
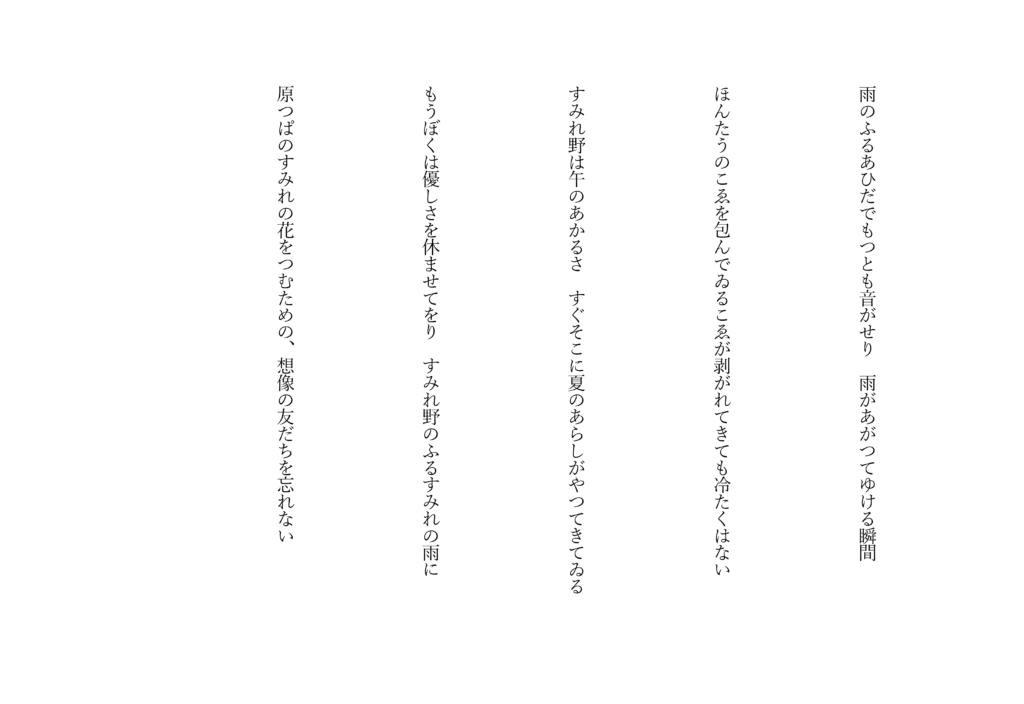
Let me take you down, ‘cause I’m going to Violet Fields. 柳元佑太
言語野にすみれの咲ける季とわかる こゑがすみれの色になるから
あなたのこゑはぼくのこゑよりもおそい、それをうらやましいと思へり
孤児院に孤児がひとりもゐなくなり、まつ白い箱だけがのこれる
いつぽんのすみれの花のうつくしさに、こゑが追ひつくまで待てばいい
雨がふるまへの匂ひで、すぐ帰る決意のできる友だちであれ
雨のふるあひだでもつとも音がせり 雨があがつてゆける瞬間
ほんたうのこゑを包んでゐるこゑが剥がれてきても冷たくはない
すみれ野は午のあかるさ すぐそこに夏のあらしがやつてきてゐる
もうぼくは優しさを休ませてをり すみれ野のふるすみれの雨に
原つぱのすみれの花をつむための、想像の友だちを忘れない