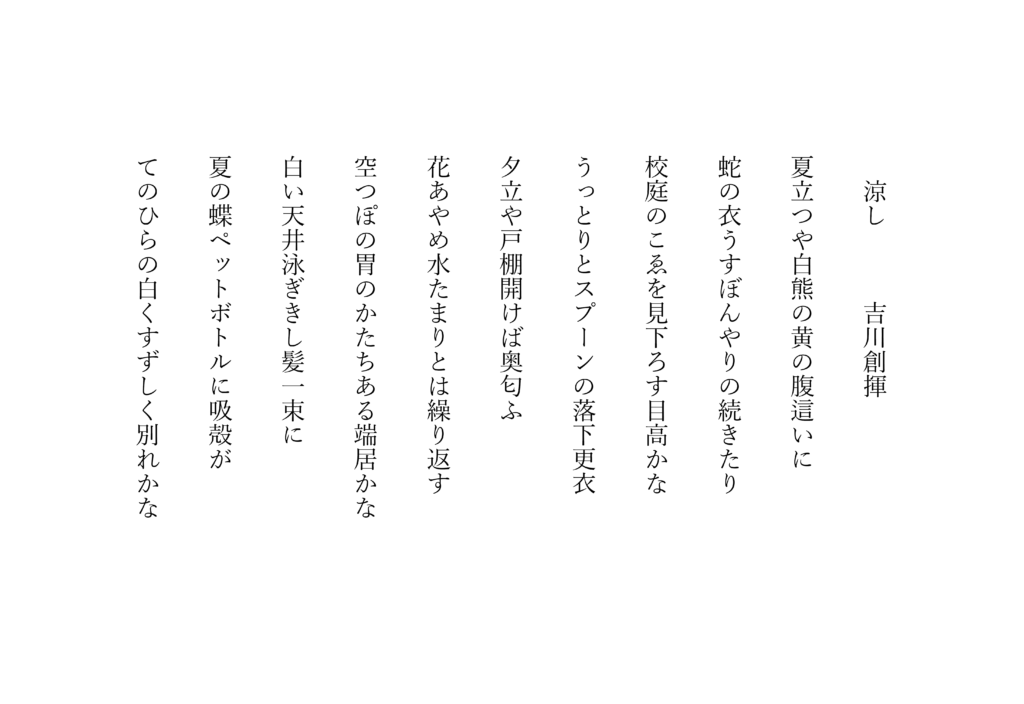『俳句』6月号(角川文化振興財団、2020年)の作品をもとに、前回(5月号)同様、勝手に座談会を行う企画です。 事前に一人三作品良いと思ったものを選んでおき、それに基づいて行います。 そして、今回はゲストとして「群青」所属の岩田奎さんをお招きして、平野、丸田、柳元、吉川との五人で話しました。
(2020年6月21日にZoom上で行った会話を文字に起こしたものとなります。 )
選の結果
手堅さのなかで――鎌田俊「出汁」
声質としての文体――小澤實「花屑」
”郊外”の延長――千葉皓史「石神井・上井草」
語を振り回しつつ――野口る理「処世」
口語の在り方――福田若之「うたわない」
牙を抜かれた蝮――茨木和生「蝮」
信仰のなかの生活――亀井雉子男「椿垣」
爽波と調和――橋本小たか「ちりとり」
番外編 関悦史「二〇二〇年 春」・仲寒蟬「山川草木悉皆成仏」
総括
〈選の結果〉
鎌田俊「出汁」 平野・丸田・柳元・吉川
小澤實「花屑」 柳元・岩田
千葉皓史「石神井・上井草」平野・吉川
野口る理「処世」 丸田・吉川
福田若之「うたわない」柳元・丸田
茨木和生「蝮」 岩田
亀井雉子男「椿垣」 岩田
橋本小たか「ちりとり」平野
○手堅さのなかで――鎌田俊「出汁」
柳元:〈風光る開けつ放しの金物屋〉が一句目で非常に手堅いですよね。金物屋で売っているものの描写から始まって、だんだんと鯛を捌いたり鰆を捌いたりする。どれもそつなくまとまっていますよね。あとは〈初花やそぎ切りにして鯛の柵〉も好きだったな。〈出汁とりし昆布の疲れ春の月〉、昆布の疲れも良い。〈三徳包丁鰆の皮を嫌ひをる〉、嫌ひをるの動詞の充て方も擬人化まではいかないけれど、そのラインがちょうど良い感じだったかなと。「椿油」の語も好きだった。最後の〈俎板の傷の錯綜卒業期〉の「傷の錯綜」はなかなか言えない。「卒業期」が季語としてどこまで効いているのかはちょっと測り兼ねたかな。変に卒業の、卒業してひとびとがいろんな道を歩んでいく方向づけと合わさらない方がいい気がします。読み筋としては卒業のころのやや日が温かくなってきたけれども、まだ寒い日も続く感じと俎板の感じで読むのが良いのかなと思いましたが。そんなにカロリーがかかるタイプの連作ではないと思うけれど、非常に読んでいてよかったなという感じだった。
平野:好きな句はほとんど同じで、品がよいというか、綺麗に収まっている連作だと思いました。対象との距離の取り方が上手な句が多かったです。途中で〈春分の出刃をゆるして鯛の尻〉とか〈花の夜やまたも噛み当て鯛うろこ〉など、おかしみのある方向に移行していったのは、この手堅い雰囲気のなかで力があるなと。
岩田:小澤實「花屑」と最後まで迷って取らなかったんです。わりと前半部の三句の並びとかも良いと思いますし……かなりテーマ性をもって編まれている作品だっただけに、中盤・後半で食傷してしまったかなという感があって、わりと花冷え的な金属質な物や魚の光り物的な情感に合った季語をいろいろ斡旋しているんだけど、そのパターンが〈花の夜や〉〈初花や〉〈花冷えや鯛の血合ひを濯ぎ出し〉と三つもあるのはどうかな、と気になってしまいました。それはテーマ性という以上仕方ないのですが、色々な飛び具合があってもよかったですよね。厨の外に出ても良かったのではないでしょうか。ゆるして、とか、嫌ひをる、あたりの動詞も余り好みではなかった。
柳元:僕もこういう擬人法の動詞の書き方はあまり好みではないですが、文体としてはアリかなぁ。ものによりますね。
吉川:書きぶりが同じトーンで安定しているのにプラスして、季語のつけ筋とか素材の面で安定しているのが連作として読みやすい部分で、私は十二句くらいなら食傷せず、好意的に取れました。好きな句は被っていて、食傷せずに読めたという点で、平野くんが言っていた、おかしみのある句とかが混じっているというのは、緩急としては良かったのかなと思いました。〈出汁とりし〉と〈花の夜や〉みたいに季語のニュアンスもつけ筋も似通っている節はあるんだけど、句の方向性がちょっと違うことで、あまり引っかかりなく読めたので、そういうところは巧みに思いました。
丸田:ほとんど同じなんですけど、個人的に最後の句の〈俎板の〉が好きで惹かれました。確かに卒業っていうラインで回収してしまうのは、この連作的にはどうかなとは思いました。岩田くんが言うように、花とのつけ方がワンパターン気味で飽きっぽくなる感じはありますね。ただ、この企画での自分の読み方的に、角川『俳句』全体で見て、他の連作と比べて読んでたりするので、他と比較したときには圧倒的に読みやすかったなあと思いました。あと自分なら包丁と魚系が伝わるちょうど良い題名をつけると思うんですけど、この感じで「出汁」にするのが自分の感覚とはちょっと違ってて面白くて、愛着みたいなのも湧いて取りました。
柳元:この前の時も一番点が集まったのは、十二句くらいで、やや伝統っぽい句づくり、安定した書きぶりの作品だったよね。余り良くない気がする(笑)。
○声質としての文体――小澤實「花屑」
岩田:○と×がいっぱいついた感じですね。まあでも○はやっぱり面白いので、最終的に取ったという……面白い句の絶対数みたいな基準だと、さっきの十二句(*鎌田「出汁」など)と迷って五十句を取るのは、なかなかちょっとフラットな話ではないんですけど。やっぱり野趣みたいのは、言葉の野趣というはよく分かるなと思った一方、アクは感じるし、句自体が面白いかどうかはよく分からないというのと、好き嫌いの話になっちゃうんですけど、という感じですね。下五のだめ押しの話がよくされるんですけど、これに対して僕はフラットで、面白い句は面白いし、面白くない句は面白くないし、という感じでどっちの句も今回あったと思います。〈蜷のみちすこし伸びたり蜷すすみ〉とか〈目刺の腹しろがねなるや曇らしむ〉とかはそれが成功している方向性なのかなとは思いますけど。ほかはあんまりちょっと、僕は乗れなかったところもあります。あと遠足の一連で一句も乗れなかったのが、最後まで迷わせてしまったかなという感じです。
柳元:ぼくは「澤」に所属しているので、この中だと一番小澤先生の句に親しんでいると思いますが、小澤先生の句の感じがすごくしました。5月号の正木ゆう子さんの句づくりの感じとはある意味で正反対だと思います。つまり、正木ゆう子さんは安定したトーンで五十句書いていて、取れない句がない。最大公約数的なところを担保しながら書いている感じがあったのですが、小澤先生の句の感じは最大公約数に投げこんでる感じがしないんです。だから岩田くんが言うような、○×がたくさん付く感じは僕もよく分かります。なんなら「澤」の中にいる人間ですら○×が付くというか……。
よく言われますけど、下五のだめ押しに関してはどうでしたか?「澤」にいるからその感覚がバグり始めている感じがありまして……下六に感じ入ってしまうみたいなところがあるというか。
平野:〈落椿ほぼ天向くや横倒しも〉あれやっぱり下六なんだな……どうして下六なんだろうって思って。
柳元:ひとつの文体なんだよなぁ、小澤先生の。不用意に余ってしまったとかではなくて、選択した結果の下六なんだよね、きっと。〈木の芽谷カレーの肉の脂身がち〉とか、そういう下六のフックの作り方は小澤先生の文体なんだよね。善悪とかじゃないというか。〈横倒しも〉、〈脂身がち〉も、文体としてある気がする。それって肉声というか声質みたいなものというか。だからもちろん一句一句見ていって、良い下六、悪い下六っていうことも大事だと思うんだけど、その一方で、小澤先生という作家の書き方として、こういう作家性があるんだという話の中で回収されていくべきなんじゃないかな、とかは思ったりしますね。俳句史の特異点という言い方も変だけど、小澤先生って、師系的な理解を拒む作家じゃないですか。現在の文体は湘子から来る「鷹」のそれじゃない。あれは何処から来てるんだろう。「鷹」の文体って、俳句のスタンダートと結構近いというか、角川俳句的な在り様とも親和性が高いというか。「鷹」もやや最大公約数に投げこむタイプの句作りをすると思うんだけど。
岩田:上手くかつ平明、ですよね。
柳元:ありがとう、ナイスフォローですね(笑)。まあ、俳句と最大公約数というのは親和性が強いと思いんですよね。なぜなら季語というのが最大公約数ですから。だからこそ、伝統の句作りで大御所のポジションにいながら、最大公約数に投げこまない小澤先生、いいなと思うんですよね。昭和三十年世代生まれの人たち、岸本さんとか小川軽舟もそうだけど、最大公約数に睨みをきかしながら作るのがうまいじゃないですか。でも小澤先生はあんま最大公約数を意識していない感じが僕はいいなと……無論それは最大公約数を経てきたゆえの余裕なのだと思いますが。自分の先生なので饒舌になってしまいました。お取りになってないほか三人はどうでしょう。
平野:取らなかった理由はないですね。他の人たちが取るだろうという予想もあったので。
丸田:僕も普通に○×が付いて、総得点的に負けたという感じですね。〈横倒しも〉はかなり引っかかって、自分はわりと下六、上六好きでOKなタイプですけど、〈横倒しも〉だけは厭な六音だなと思って、引っかかりましたね。
柳元:厭なのはなぜですか? (笑)
丸田:なんか、なんか厭で……なんなんだろうな、〈脂みがち〉の句の方はどうしても言いたかった感じがあるんだけど、〈横倒しも〉は優しいけど悪意がある感じがして。言いたいという気持ちは分かるけど、自分だったら推敲に回すと思うから、このまんまで行くぞと決めたところにちょっと厭らしさみたいなものを感じましたね、うまく説明できないんですが。もちろん、このままで行くぞ! っていう決意がそのまま作者としての個性だというのは分かってはいるんですけど。
柳元:なるほどなあ、〈横倒しも〉の句はね……うーん難しいな。澤調の弱みは、中七まで言ったときに下五がある種パターン化されるというか、中七で切ったあとに寄ってもう一度別角度から描写するという構造が見えるというか、そのパターンで意外性がないかたちのまま下五に乗っちゃうと、ウーンなるほどなぁという感じになる。予定調和というか……。内容の意外性が実はあまりないところに対して、型が大仰というか、過剰な型みたいなのを感じるのでしょうか。
岩田:部外者的な意見としては「や」ってもともとは強い切断じゃないですか。もともと強い切断という文脈があったところに、同じ対象を別の角度から捉えたからキュビズム的で面白いと言うのが澤調の強みなのであって、だけどそれを同じ角度からまた同じものを捉え直してしまうと、「や」の効果自体が俳句全体のなかで逓減して、ある種言い方を変えれば「悪貨が良貨を駆逐」しちゃうのかなと。効果的なのは良い、効果的でないのは悪いと言えばいい話なのかなと僕は思っているというのと、倒置の作用ってあるじゃないですか。〈うすらひに猫ねむるなり薄目開け〉とか、あるいは〈はろかなる灯の滲むなり芹噛めば〉という句も別に倒置自体がおもしろいわけじゃなくって。じゃあ倒置を元に戻したときに内容が面白いかというと、それもどうなんだろうという話になってきちゃう。抵抗感の正体はこの二つかなと僕はおもいます。プレーンな内容にしたときに面白いかどうかと、結局同じ角度から捉えた物に「や」を導入してきてないか。そうじゃなければ僕は面白いと思いますし。
吉川:澤調への素朴な感想として、切れた後もさらに描写に踏み込む構成、ギアの変化があることで句の中に分かりやすい加速があるというか、キャッチーさがあるのかなと私は勝手に思っています。句の中で明確に心が動いた点があるんだなっていうのがよく伝わってくる文体だなと思っています。
柳元:確かにそうだね、澤調自体が気づきの「けり」みたいな(笑)。
岩田:面白いですね。
吉川:私が読者として澤調の句を読む時に、いい句だなぁとすぐに飛びついても、それは文体のキャッチ―さに目くらましされているのでは、と立ちどまってしまう時があります。
岩田:小澤さんだけだったら全然良いと思います。それがミーム化してしまうところに、悪意も入りこみやすいという感じなんじゃないですかね。
柳元:一人の作家の文体としての価値はめちゃくちゃあると思うんですけどね。ただそれをパターンとすること、結社の中で主宰の文体に寄ってくるみたいなのは、主宰が選をするという構造があるという以上起こりうることだと思いますけど、やはり避けたいですよね。自戒も込めてですが。
○”郊外”の延長――千葉皓史「石神井・上井草」
平野:第一句集の『郊外』を出して、その”郊外”をまだ続けているんだなと思って、書き方がアップデートされている感じはなかったので、最初はちょっと批判的に読んだんですけれど。千葉皓史はこれでいいのかな。平成の初期の郊外とは違って、ネット社会で郊外が変わっているのに、もしも時代に敏感な作家であろうとするなら、書き方が変わっていて当然のところが、そこまで変化していない。〈少年の問ひ昂ぶりぬ木の芽道〉とか〈幼くてめいめい遊ぶ梅白し〉とか。〈善福寺池に映りて下萌ゆる〉は歴史性の薄くて、どの寺でも大丈夫そうな感じはいかにも郊外だし……でも、そういう懐かしさみたいなところで書いているなら、ありなのかなと思いました。
柳元:一句目が〈待春の郊外電車通ふなり〉だし、そうだよね、よく分かる気がする。句自体で言えば僕もそんなに嫌いじゃない。〈雷鳴のありしと思ふ蓬かな〉は好きだったな。
岩田:これいいですよね。
柳元:〈青空の働く辛夷咲きにけり〉は「働く」が不思議な投げこまれ方をしている。確かに平成の郊外の精神をひとりで延長している、という指摘にはいろいろ思うところがありますね。
吉川:今のを聞いて納得してしまって。つまみ食いの千葉皓史イメージ像しかないんだけど納得しました。一句単位で好きな句があったのと、〈馬小屋に馬の納まる日永かな〉や〈校庭を通す農道うまごやし〉とか、ノスタルジーの対象になりやすいものを、ノスタルジー味がなく描かれている感じが面白いなあと私は思って取りました。
岩田:候補ではありました。〈赤松の林の傾ぐ桜かな〉は結構いいかなと思いました。ちょっと一箇、〈金星の生まれたてなるキャベツ畑〉は、大峯あきらに〈金星の生まれたてなるとんどかな〉(『宇宙塵』、2001)があるので、それは指摘されるべきじゃないかなと思いました。
○語を振り回しつつ――野口る理「処世」
吉川:野口る理さんの魅力を上手く言えるかと言われれば言えないんですけど、好きだった句から言うと〈サイダーこぼす見開きいつぱいの砂丘〉、〈水無月の紙を透かせるカレーパン〉、〈夏至はもうレインコートのまま眠る〉とかが好きでした。野口る理さんの句には「記憶」であるとか、ウェイトの重い単語が出てくるんだけど、そのウェイトの重い単語に振り回されるんではなくて、自分でウェイトの重い単語を振り回す。一句単位で見て完成度が高いと言う話はうまく理解できていないので、解像度の高い話は出来ないんですけど、作風が好きというのがどうしてもあるなと思いました。私が思っている野口る理さんのそういう力が十句通して見れたかなと思いました。
柳元:僕は〈紫陽花や多分で終はる話して〉みたいな句があると非常に迷うというか。こういう句を書かないことが非常に大事なんじゃないかなと思うというか……それこそ松本京子の『檸檬の街』の、俳句における俵万智みたいな形で言われていた女性口語俳句みたいな方の残滓を感じるというか。そう言う方向に行かない方が野口る理さんはいいんだろうなという感じがします。吉川の言い方を借りれば、「振り回し」きってほしい。一つ一つを見ると良い句はあると思うんだけど〈夏至はもう〉みたいな句は余り好きじゃない。〈紫陽花や〉や〈夏至はもう〉があることが非常に取りにくくされてるなあとおもいながら、僕は選から外したんですが。
丸田:僕も柳元くんと同意見ではあります。〈夏至はもう〉とか〈紫陽花や〉の句とかはあんま好きではなくて、で、こういうのを書かないのが大事っていう意見も確かに分かるといえば分かる。でも、それで消していってめちゃくちゃ良い連作が出来上がったとしても、それは野口る理さんらしさではない気がしていて。
柳元:確かにねえ。
丸田:題名に「処世」を持ってくるところも含めて、主体の明るさとか、吉川が「単語を振り回す」って言っていたけど、主体の腕白な感じが大事どころである気はするので、愛嬌としてこういう句たちがあるのは許されるかなと思います。ただそれが嫌いという人は同じくらい居るかもしれないなとは想像がつきます。そんな良い句がたくさんあるわけではないような気はしていて、〈手を洗ふ泡に驟雨の記憶かな〉とかはかなり強引で、「驟雨の記憶」っていう語がやや浮ついた、そんなにな句かなと思います。個人的には最後の〈処世とは鈍らせること金魚は金〉が好きで、「鈍らせること」はそんなに新しくはない表現だけど「金魚は金」の言い方が良くて、他の人だったら「金魚の金」とかもっと違う落とし方をすると思って。こういう主体の感じも含めて言い方が納得というか、この人ならこういう言い方をするよねと。その主体と気持ちが合ったという感じがして、読んでいて作品として面白いなと思い取りました。
柳元:一句一句から立ち上がる作中主体というか、作者像みたいなものに回収されていって立ち上がる主体の明るさみたいなものに、どちらかというと野口る理さんらしさがあるという理解で大丈夫ですかね?
丸田:はい。他の人の作品を読んでいてもあまりそんな気持ちにはならなかったので、「処世」に関しては歩いて喋っている人がなんとなく見えた、そういう在り方もありかなと思って。
平野:うーん。「金魚は金」ではないじゃないですか。そこの一種のずらしと言うか、処世の出来る人が書けるんだろうなと思いました。鈍らせることはものを書く人なら、まあやってはいけないことで、それを一面ではしつつもそういう自分のあり方を相対化している。処世とは「金魚は金」と感覚を鈍らせて信じ込むことだ、みたいなおどけ方はそれ自体が処世的だなというか。それで騙してやっていけるのはちゃんと器用な大人だなというか。もっと不器用に歯を食いしばって、対峙するような姿勢の方が僕は好きですね。
丸田︰たしかに、それ自体が処世的というのはそうですね。僕的には、自分の感覚を鈍らせてというよりは、開き直った印象を受けていましたが。
岩田:ライトヴァースの同時代の人の中で、認知体系が子どもみたいだということが結構言われてきた気がして、世界に対する価値判断のなさというか、〈バルコンにて虫の中身は黄色かな〉みたいな無邪気な感じが特徴だった人かなと思うんですよ。柳元さんのこういうのを書かない方がいいんじゃないかという意見は基本的に諸手を挙げて、とはいかずとも片手半くらいには賛成しますし……まあ、どっちの議論もよく分かりますけどね。あと季節的に、霧の句が紛れこんでいたのはどういう意図なんだろうというのは気になりましたね。ライトヴァースが書かれた時に身構えがちな嫌味みたいのはないですよね、というのは特長だなと思いました。
柳元:意外と考えてる時があるよね、変な言い方だけど。純粋無垢ではないときが突然。世界に対するうたがいのなさというか、そう言うような眼差しからはこぼれ落ちるような何かを意外と書いていらっしゃるような気もするというか。ミニエッセイでもサルトルのアンガージュとかの話をしてますけど、失礼な言い方だけどこういう方向にも行くんだというか。
丸田:まあ句から立ち上がる作家像と実際は往々にして違うものだし、純粋無垢だなんて思われてたのも困るかと思いますけれども。無邪気さイメージが先行しやすい句集・作家であるということですよね。
吉川:聞いてて〈紫陽花や〉とみんなが同じラインで〈夏至はもう〉を話しているのを聞いて確かにそうだなと思いました。
柳元:うむ。
吉川:〈夏の蝶ならば瞬き縫へ進め〉の「瞬き縫へ」は言えるんだけど、「進め」まで言えるとことかを好きだなと思ってしまう。
柳元:振り回していくという話の中では、その句が確かに一番吉川的な野口る理の受容には合っている気がするね。
吉川:ちょっとかなり雑なことを言っているので後で考え直します。
柳元:地味に〈新聞を破る強さに草を引く〉が上手いと思いました。
一同:確かに。
○口語の在り方――福田若之「うたわない」
柳元:やっぱ福田若之さんってこう見ると凄く密度があって書いているなという感じがしました。野口る理の口語の感じと福田若之の口語の感じは全然違うというか。一句一句というよりは、句が立ち上げる主体の方にも価値があるというか、句というよりは句の中に登場する作中主体や句を書いている作者というところまでみることによって良さがより現れるタイプの書き手というか。口語が肉声に繋がっていくことを大事にしている、その時に今自分が書くことと口語の価値が直結している。口語の原理主義というか、口語って常にそう言うことを言われながら文語に対抗するものとして持ってこられていたと思うけど、それをちゃんとやっているところで若さんは面白いなあと思います。
〈安酒さばたんきゅーとは亀が鳴く〉は面白かった。〈う、かえるはうたはうたわないうたはねうたはないの〉の「う、」とかは、最近崎原風子を読む機会があったんだけど、その辺の受容とかもひょっとしたらあるのかな。それとまた違う形で同時代的に横軸で書いている感じがあるんだけど、その裏には縦軸もしっかりある。けど、それをあまり見せないというか。今は縦軸見せる作家がいるじゃないですか、例えば安里さんとか、生駒さんとか、僕が好きなタイプの若手とはまた書き方がちがうというか。好きな句は〈安酒さ〉〈春の風邪愛をも越えてくすぐりあう〉もコロナの時局をみた感じの句だけど嫌いじゃないかな。〈たそがれが来る東から花の鵜へ〉、〈はこべらだ過ごしても過ごしても夜〉とかも良かった。〈未来なんて笑い飛ばして春の雪〉などはかなり意図的に下手な句を書いていると思うけど、でも無い方が良かったとも思う。
岩田:〈う、かえるは〉、おもしろいですよね。旧かなと新かなの違いもハックしていますし。前半は新かな、後半は旧仮名として読めば全く同じ意味になるし。『自生地』にも〈泉少しどもる少し話したいんだと言う〉がありましたけど、そういう口語性のだぶつきみたいなことにわりと関心があるのかな。〈未来なんて〉、こういうのが入っていると全体が一周回ってないものとして読まれてしまう危険性があるなあと思って。やっぱり一周回らないところでとどまらせちゃう句があると、(あまり良い言い方じゃないですけど)損をしちゃうかなと思ったので、これを入れることには否定的です。
柳元:そうだよね。ただ、それも分かるけど、泥臭さみたいなモノは若さんの書き手としての特質な気もしていて、それがこの句で出るかと言えば損の方が大きい気がするけど、一概に言えないというか無い方が良いとはおもう……二転三転しますけど。
丸田:僕は〈未来なんて〉、〈ぶらんこでうんこのことを考える〉のラインはあんまり好きじゃなくて。それは『自生地』の時から思ってたことなんですけど。柳元くんは泥臭さとと言っているけど、こういうのを言っちゃいたい自分、を書いてしまうというのもその人の良さだと思うんですけど、自分的にはそれが抑制された〈驚いて川原に何と思えば雉〉、〈たそがれが〉とかのどちらかといえばフラットな、口語のリズムと修辞にこだわられた方の作品が好きで。なので〈安酒さ〉とか〈ぶらんこで〉とかは好きじゃなくて。〈う、かえるは〉みたいなのが十句集まっていれば、おーとなるけれど、急に単発で入ってくると読みが難しくなるというか、急に連作が変な感じになっちゃうなという感じがしますね。他の人に比べて圧倒的に個性をもって書いているので好印象なのと、かなり好きな二句があったから取ったけど、内心、若之さんにはもっと良い句を期待していたところはあります。「うたわない」という題名から強い意図を感じて、結局歌っちゃってるみたいなところの面白さが今回あると思うので、やってることは分かりつつ、そこは個人的にそこまで乗れなかったですね。
平野:自分が口語をあんまり読み慣れていないというのもあるけど、どういう価値判断で口語を読んでいけば良いのか分らないんだよね。
丸田:それで言うと今の文語もそうだと思うけどなあ。僕からすると。
柳元:文語はある程度パターンで判断が付くというか、ある程度伝統の枠組みの中で書こうとする場合、パターンへのあらがいの中で句の良さが立ち上がる瞬間があるけど。口語は既存のパターンの中でどうこうというより、もっとナマな感じで価値判断をしている気がするなぁ。
丸田:今は口語で冒険する人が何故か少ないからあれだけど、口語で良い句を作る人がいっぱい出てきたらこういうのはつまらない、という人が出てくると思う。先進的だからっていうのがある気はするな。
吉川:こういうの、とは十句の中のどのラインなの?
丸田:まあ、全体的にじゃない。文語は逃げてるというか……口語はさびが早い気がしてて。新しさで見て〈う、かえるは〉とかは良いと思うけどこういうのもすぐ錆びちゃうんだろうなという気はします。今にも錆びつこうとしている発話を捉えるという句の特性は分かっていますが。〈未来なんて〉とかはずっと起きる感じがして、それを口語の良さとして作っているのは若干ミスマッチな気がしました。いかに古びないようにしながら、一回性みたいな顔をするかが(良くも悪くも)俳句だなと思っていて、現時点の口語だとその古びなさをどうこなしていくかが難所になると思ってはいるので、こういう句群も分からなくはないんですけどね。
柳元:〈未来なんて〉は確かに普遍なとこを言い止めようとしているけど、それは口語だとめちゃくちゃ面白くないんだなというのは不思議な感じがするね。即時性とか……むしろさびの早いことの方を特質にして書いていったほうが口語としては、僕としては実りがあるのかなという感じがするなあ。
丸田:そこが福田若之さんの得意とする、どんどん作っていくぞという感じなのかなと思っていたので。
柳元:〈驚いて〉、〈たそがれが〉とかは強度をレトリックで補強してるじゃないですか、そういうのは口語のひとつの在り様としては分るというか。レトリックは普遍という言い方も変だけど、言葉のひねりとかで、もちろん時代ごとにある程度、価値は変わるのでなんとも言い難いけど、パッと読み下せない感じとかの、そういうものに対するフック感は普遍だと思うので、そういう方で口語を担保するのはわかるな。けど、そうじゃない口語の良さはあってもいいのかなという気がするなあ。若さんの場合特に。
丸田:もちろん、それはそうだね。
柳元:宮崎莉々香さんが書いてたときに思っていたのはそう言うことで、レトリックが充実してるという句を書くタイプじゃなかったけど、りりかさんが書く句の価値は、レトリックとか普遍とかそういうことじゃないものだった気がする。
岩田:〈七分袖素早い景色だが残る〉とかですかね。
丸田:確かにね。文語口語という捉え方自体がナンセンスだと思っているけど、角川俳句でまあこれだけ口語が少ないのを見ると、引きつづきその効果を積極的に考えていきたいなという気になりますね。
○牙を抜かれた蝮――茨木和生「蝮」
岩田:鎌田俊「出汁」で食傷とか言っておいて何だという話なんですけれども。でもこれは面白く読めて、〈変な蛇庭這ひゐると蝮差す〉、〈蝮見て来たる夜はよく眠りけり〉とかは普通に単体として立つ句かもしれないなあと。あと〈馬肉置きゐたり蝮を誘はんと〉とかも良いですかね。
要は凄い薄められているんですよね。本来五句連作くらいでいい内容が薄められたことによって、なにかが引き延ばされて変なモノが露出しているという感じで、〈渡り蝮かたまりて村移りゆく〉あたりから蝮が増殖する。一匹の蝮じゃなくなるんですよね。一匹の蝮であるというアリバイを捨てて、赤黄男の「蝶はまさに〈蝶〉であるが、〈その蝶〉ではない」みたいな。〈その蝮〉であることから発して、〈蝮〉へと転化していく瞬間みたいな、季語として遊び出す感じが面白くて。何回も蝮は死ぬし。ゾンビみたいな一つの現象になっているわけですよね。その季語が蝮であることにもちゃんと意味があって、脅威が無毒化されている、まさに牙を抜かれていることによって、安心してへらへら笑って季語として受容することが出来る、だから眼前の毒蝮ではなくなって安心できているみたいなところがあるのかなと思って。そういう意味でふざけた感じがして僕は良いかなと。かつ前書きで「平群に移り住みし時、妻は」ということで、奈良の実際の蝮から発生しているというエクスキューズを付けていることによって、現実性にも立脚している変な魅力があって……もはや句の平均値的な話ではなくて、全体の構造として面白かったですね。
柳元:なるほど、そう言われるとそう読める感じがするね。普通のリアリズムではないよね。マジックリアリズム的な切り替わりがあるところは確かにあって、それは岩田くんに言われないと気付かなかったな。初読としては連作の流れというよりは一句一句で見た時に、どうしても立ってない句の多さというか、引き延ばされた薄さに乗り切れずというところがあった。そこでスルーしてしまったというのは読みが浅かったな。もう少し時間をかけて読んだときに何かを読めたなあとは非常に思いましたね。簡単に書いてしまった句はどうしても嫌だなあと思って。〈湖に死にたる不幸蝮浮く〉とかは明らかにそうなんだよね、その辺に乗れなくて……。
丸田:まあ、これに一票入れられる岩田くんのその感じが良いなと思いました(笑)。あえて薄められているなとは思ったし、二十一句もらってこれを書けるのは面白いなと思ったんですけど、なんていうか、新聞を久々に開いたら面白い四コマ漫画があったみたいな、さくっと読めて面白いけど、あんま記憶に残る事もなくって感じで、自分は一票入れるほどではなかったかなという感じではあるんですけど。岩田くんの牙を抜かれて、というのはいい指摘だなと思いました。
柳元:茨木和生のこの作品は岩田くんというかなり良い読者を得たでしょう。なかなか連作として書くとき、連作の完成度を上げる方に考えがちだけど、連作そのものの枠組みを使って、連作を書いていく方向性は確かに十分にあるなあと思いましたね。
岩田:云うなれば「平句マジックリアリズム」みたいなことが確かに可能性としてはあるのかなと思って取った感じですね。
柳元:角川俳句賞とか、あるいは他の連作の賞がそういう読みを今、どこまで出来るのかなぁ。新人発掘が目的になっていくと一句単位の強さにどうしても目が行きがちだし。今回の「帚」の四人がそうであったように。こういう連作を書いて、それこそ岩田くんみたいな形で読んでくれる人が居る場があるといいいよね。ジャーナリズムを回していく事は必要だなぁ。
○信仰のなかの生活――亀井雉子男「椿垣」
岩田:茨木和生みたいに語りたいわけではなく、語らずとも良い句は良いよねという話なので……。最初の句〈鶏の駆け出してきし椿垣〉とか〈満開の桜一本雑木山〉と隣の〈種牛の角の切られて山笑ふ〉辺りが結構良いかなあと。通俗的な「山笑ふ」のつき方でもありながら、かなり暴力的で、血も滲んで痛々しい風景なので、角をワイヤーとかで伐ったりしてということを踏まえると、「山笑ふ」も怪物とか怪人の笑みみたいな感じにも見えますし、シニカルで良い句だなと思いました。〈神殿に抱へて来たり桜鯛〉もわりと良いかなと思って取りました。宗教関連は、ちゃんと世俗的な空間に接している句は面白かったんですけど〈磯遊び竜宮橋を渡りけり〉あるいは〈落武者の墓にふぶける山桜〉とかは面白くないなという感じです。確かな生活感があって面白かったです。末尾のコロナ詠二句については特にコメントはないかな、という感じで、これはいらなかったなと思います。
平野:同じく末尾の二句(*〈磯遊び〉、〈落武者の〉)で推せなかった感じですね。
柳元:岩田くんが挙げてくれた句も結構好きで、予選には入れていたものの、ただ最後の二句で作品として推せるかとなると。普通に〈鶏の駆け出してきし椿垣〉は良いと思う、凄い好きです。
吉川:自分も予選で取っていて。指摘としては、宗教、いわゆる自分のように信仰のない地方都市の生活感ではなく、宗教と交わりつつの生活感がある句は、私には珍しく新鮮に読めました。
柳元:この句に限らず、今回の角川俳句は宗教感あったよね。確かに亀井雉子男さんの句は、まあ句の単体として良いよねという話をしたほうが実りのあるタイプの連作ですね。
○爽波と調和――橋本小たか「ちりとり」
平野:モノの雰囲気。〈鶏ののぞきこみたる蝌蚪の水〉だと鶏と蝌蚪の水が現実的なモノとして使われていて、両方のポテンシャルが調和されていたりする。〈チューリップ新聞束と並びたる〉は二つのモノが浮び上がってくるというか、並列されることによって手ざわりがある感じですね。まあ「秋草」の人と言うことで、自分の思う爽波ってこんな感じだなあって。そこの面白さがありました。
柳元:わかるよ、僕も爽波感じるな。〈鶏の〉に関していえば、岸本尚毅の句を小川軽舟が評して、季重なりで互いの季節感を打ち消し合い、ものそのものが現れるって指摘がありましたけど、その感じだね。動物二首を詠み込むと差し障りがある、まあ〈行春や鳥啼魚の目は泪〉みたいな俳諧的な焦点が複数あることがゆるされる形で書くなら別だけど、写生という焦点が一つに定められることが求められる読み口を採用したときに、どうしても「蝌蚪の水」と「鶏」とはお互い食い合う形になる。それを逆手に取るという。小川軽舟の話とかを思い出しながら読むと面白いですね。〈田楽やまともに風のあたりたる〉はとぼけながらの巧さもある感じがします。〈チューリップ〉は本当に爽波な感じがする。
平野:素材もそんな感じ。チューリップと新聞紙の人事と。
岩田:僕も結構気になりました。波多野爽波–山口昭男ラインで言うと、本来取り合わせにしばしばどきっとするところがあるのが「青」の特性だと思うんですよね。山口昭男先生はもうちょっと爽波のアグレッシブさを嫋やかにまとめた〈空海の真白き肌葦の角〉とかそういった方向性ですけど。今回、そういう意味で取り合わせにどきっとはしなかった。良くも悪くも調和的だったなって。最後の句だけは調和が計算されていなかったので、即物的だなと思ったんですけど、どきっとはしなかったのでいただきはしなかった。〈花冷の手ゆび消毒液に浸け〉とかは、これくらいの距離感で時事を詠むのは好きかなと思いました。
平野:うん、モノとモノ自体はそこまで離れていないよね。
柳元:爽波ラインといえど、爽波はどきっとするというよりは実直にモノを書くタイプだったと思うし、山口昭男さんは爽波というか裕明タイプで、取り合わせのラインをとっているんじゃないかな。ある種直系のお師匠さんに先祖返りをする形で、爽波のスタンスを意図的にとりこんでいるのかなあ。
岩田:どうなんですかね、結局虚子まで先祖返りしていますから。僕としては爽波こそどきっとする取り合わせの人だと思うんですけど。〈福笑鉄橋斜め前方に〉、〈鮨桶の中が真赤や揚雲雀〉とか、それを引き継いでいるのが初期の山口昭男さんの〈出汁昆布の箸をつるりと浮寝鳥〉、〈劇薬の茶色の瓶や浮氷〉とか……。
丸田:何も見ずにすらすらと……。よく覚えてますね……。
○番外編 関悦史「二〇二〇年 春」・仲寒蟬「山川草木悉皆成仏」
柳元:前回に続いてまた番外編という形で、どうですかね。とりあえず関さんから話をしましょうか。かなり時事にコミットした感じですね。結局、政権批判とかそれ自体が句の強度になることはそこそこ難しくて、イロモノ的な目で見がち。かつそういう時事との距離の取り方、句材としての扱い方って難しいなと思う。変に情緒を残そうとしたときに、どっちとも食われるし。季語も上手く働かなければ、時事も丸めこまれている。関さんの場合は非常にドライというか、情緒ゼロみたいな、無機質な手つきで言葉を組んでいく感じがあるけど。手法を知っているからかもしれないですけど、違和感なく読めたかなと思います。「AKIRA」とか「アマビヱ」とか、ツイッターでトレンドになっているものを上手く詠みこんでますね。〈光り立つアマビヱもがな春の海〉、アマビヱでこういう句を作れるのは凄いなと思うなぁ。改めてだけど、野口る理さんが関さんと同じように時事的な態度を取っていたのはなかなか面白かったね。
岩田:野口さんのあの文章と合わせて読むと面白いですよね。〈心臓巻き込む税の歯車落椿〉とか落椿が面白いなと思ったし、〈東京裂けゆくAKIRA悪疫春の夢〉は中七の音便が面白いなって。なんだろう、お家芸って感じですかね。もう僕らも変な話、めちゃくちゃ真面目には読まなくなってはいるかなとは思います。
柳元:やっていることを関悦史の文脈で見たとき、関悦史自身を更新しているよねという見方にはなかなかなれないのが。関さん自体が特異的というか、関さんしかやっていないことなのでそれはそれでいいのかなって。技術的な粗があるわけではなく、ほぼ完成形というか。この形以上の時事詠みたいなのはなかなかもう……悪口としてではなくお家芸と言える感じがするな。あとこれは岩田君に対して意地悪な物言いになりますけど仲寒蟬さんとかはどうですか? (笑)
岩田:若之さんも「群青」ですし、そんな意地悪じゃないですよ(笑)。そうですね、僕はよく見ているのでこれもお家芸だなって感じなんですけど。原始アニミズムみたいなことはよくされていますね。それをある種、茶化すことによって逆に人間の側に引きずりこむみたいなことをよくやっているかなと思います。〈粘膜のごとく氷室の石の壁〉とかは結構良いと思いました。
柳元:『巨石文明』の時の句を思い出しても、その時の印象となにかが変わると言えば変わらない気がする。わりと書いちゃう人なんだなと。含みを持たせると言うよりは書き切っている、〈いつ影と入れ替りしや夏の蝶〉とか余韻を残すような句作りではないというか。そういう意味では僕としては好きなタイプではあまりないけれど……。
○総括
丸田:今回、岩田くんに来ていただいたということで。
柳元:外部の視点という意味で岩田くんが来てくれた訳だけど、すごく遠い形で違和として入ってきたわけではなかったので、刺激になる点もたくさん合ったけど、同時代的なものを共有しているなと感じることが多かったですね。やっぱ同じ世代にいるからこそ、上の世代がどう見えるかみたいなものって、結社とかの文脈は違えども、似てきたりするんだなと思いました。まあ岩田くんのバランス感覚が優れていて僕らにアジャストしてくれてるということだとは思いますが。皮肉じゃなくて。
吉川:選が前回よりも今回は被りがちだったので、私たち四人が作る句が違うから、なんとなく全員違う価値観で俳句を書いてはいると思っていたけど、読みの価値観がどうしても似通っているところがあるとあらためて気付かされて面白かったです。
丸田:読みの価値観が似てるというよりは、面白い句が限られていてその中でどれを取るかという話だとは思うんですけど……。今月号はふつうに面白いなと思いました。関悦史さんのようにコロナウィルスを詠み始める人が一杯居て、まあまあそうなってくるよなあという感じがしました。時事詠って、難しいなと改めて。あと岩田くんの読みがビシッと決まって作品が読みやすくなることが何度も有ったので、自分もそうなるべく頑張らなきゃなと思いました。
平野:ほか三人が言いたいことを言ってくれたので、僕からは上に同じくという感じで。
岩田:ありがとうございました。良かったと思いません?(笑)
一同:(笑)
岩田:どの先生に付いているかでポジションが発生して、なんとなく意見が対立しているように見えますけど、実際は若手ってそんな対立している訳ではないし。そんなに分節化を引き継いであげなくてもよくないですか、という気持ちなんです。それで黙っているとどんどん大陸移動説みたいにじわじわ離れていくように見えてしまうので……今回も前回も、「帚」の方々は歴史性をかなり踏まえたお話をされていましたよね。若手でそういうのを意識しているのは特異だと思うんですよ、意外と。僕もそういうのはわりあい好きな方なので、他の方がゲストだったらそのあたりも差異として浮彫りになったりするのかなと思いました。
柳元:なるほど、ありがとうございました。じゃあそんな感じで今回は締めようと思います。
(2020/06/21 Zoomにて)
・ゲストプロフィール
岩田奎(いわた けい):1999年生。京都府生まれ。「群青」所属。