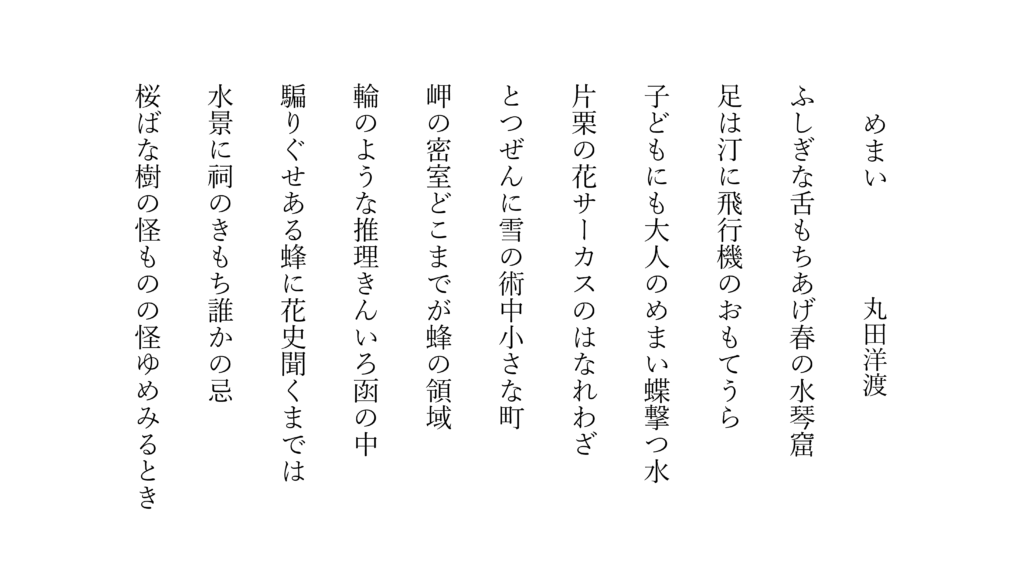柳元佑太
春日井建20歳の時に刊行された『未青年』(作品社・1960)という歌集は初めから伝説となるべき要素を抱え込み、なるべくして伝説となったような歌集である。17歳から20歳までの歌を所収した一青年の第一歌集に三島由紀夫の序文つき。しかも三島由紀夫をして「われわれは一人の若い定家を持ったのである」と言わしめている。
大作家が無名の青年の序文を執筆することを訝しく思うむきもあろうが、春日井を三島に紹介したのは敏腕編集者の中井英夫。中井英夫は「短歌研究」「短歌」の編集長を務めた所謂「前衛短歌」の仕掛け人、黒幕である。彼が著した『黒衣の短歌史』を読むと、中井が当時十代後半だった春日井に格別目をかけ、総合誌での作品発表の機会を与えていたことが分かる。要するに平たく言えば春日井にはジャーナリズムの中に後ろ盾もあった。その歳において得られるものとしては最高のものと思われるバックアップのもと『未青年』は世に問われ、世の歌人に賛否ありつつも熱狂的に迎えられ、センセーションを生んだ。
また春日井の『未青年』以後の歌集の一般的な評価が余り高くはない(ようにぼくから見える)ということも、相対的な『未青年』の価値を高めてしまっているように思える。『未青年』以後の春日井に向けられた読者のかような眼差しには同情を禁じ得ないが、しかしそのような受容こそが『未青年』を「伝説」に押し上げたのも事実であろう。
とはいえ、伝説など犬も喰わない。一読者として春日井のテクストに忠実に精神を浸して、『未青年』を受け取りたい。ある種の古典は、己に引きつけてある種強引に読まれることを待っている。だいたい、例えばドストエフスキーやサリンジャーを醒めた批評的な「大人」の精神で受け付けて何が得るところやある。精神的な成熟を迎える前の人間が一人部屋に籠り読むべき書という愚かなカテゴライズが許されるならば『未青年』もそのような種類の歌集であるように思うし、ぼくのごとき生意気な(!)未だ精神の青く熟していない読者の評を『未青年』が許さなければ嘘であろう。
さて『未青年』は以下のようなエピグラフから始まる。
少年だつたとき 海の悪童たちに砂浜へ埋められた日があつた あの日 首すじまで銀の砂粒をかぶつて みうごきできない僕が 泣きながら知つたのは何だつたろう 夕焼けの火影となつて立ち動く裸の少年たちにくみふせられたぼく そして 残照にまだ熱い砂に灼かれて 肌はきんきんといたむのだった ああ日輪 みんなの素足が消えていつた砂山のむこうから やがて青ざめた怒濤がおしよせ ぼくのいましめの砂が波にほどけるころひとりぽつちのぼくの真上には 病んだ 紫陽花のような日輪が狂つていた
鼻につくくらい甘美な文章である。ここにはマゾヒスティックな倒錯した快楽に目覚めてしまった非力で泣虫な少年がいる。このエピグラフが見事に導出した、受動的で脆弱な主体は、章の中で主題を変えながら、ナイーブさへの嫌悪(禁忌を侵犯しようとする動き)とそのナイーブさ自体の持つ深さへの逆説的な耽溺を行き来する。なお、一首ごとに評をつけるような野暮はやめようと思う。章から好きだった歌を選んで章ごとに感想を附したい。
「緑素粒」
大空の斬首ののちの静もりか没【お】ちし日輪がのこすむらさき
学友のかたれる恋はみな淡し遠く春雷の鳴る空のした
唖蝉が砂にしびれて死ぬ夕べ告げ得ぬ愛にくちびる乾く
埴輪青年のくらき眼窩にそそぎこむ与へるのみの愛はつめたく
プラトンを読みて倫理の愛の章に泡立ちやまぬ若きししむら
童貞のするどき指に房もげば葡萄のみどりしたたるばかり
われよりも熱き血の子は許しがたく少年院を妬みて見をり
白球を追ふ少年がのめりこむつめたき空のはてに風鳴る
青嵐はげしく吹きて君を待つ木原に花の処刑はやまず
石皿に噴水の水あふれゆけば乳にむせたる記憶の欲しく
粗布しろく君のねむりを包みゐむ向日葵が昼の熱吐く深夜
水仙の苔のしづむ眼の清くみどり児が知恵をふかめゐる冬
青年が恋愛感情を抱く。同性愛のようにもとれる。過剰な身体性を持て余しつつも積極的に動くことは出来ず、むしろ進んで自らの身体の観察者の位置に立ち、自然が火照った身体を冷ます。鬱屈とした性の芽生え。理性による抑えつけが性愛のとめどなさを保証する。濡れ滴るような、色彩的な叙情は圧巻。
「水母季」
襲ひくる兄の死霊を逃れむと帆を張れば潮の香がなだれこむ
水門へ流るる潮にさからひて泳ぎつつ兄の死も信じ得ぬ
生きをれば兄も無頼か海翳り刺青のごとき水脈はしる
潮ぐもる夕べのしろき飛込台のぼりつめ男の死を愛しめり
内股に青藻からませ青年は巻貝を採る少女のために
水葬のむくろただよふ海ふかく白緑の藻に海雪は降る
蝶の粉を裸の肩にまぶしゐたりわれは戦火に染む空のした
兄よいかなる神との寒き婚姻を得しや地上は雪重く降る
白猫の眼にうつされし灯が揺れて父の胸奥【むねど】にねむる軍港
舌根が塩に傷つく沖にまで泳ぐともわれはけだものくさく
亡くなった兄への愛、思慕と恐れ。兄への挽歌であるのだろう。兄と自分は鏡像関係にあるようにも読めるし、兄弟間での愛というものも仄めかされる。敗戦後十五年しか経っていないことを考えれば南洋で死んだ(とされる)兄のイメージはリアル。
「奴隷絵図」
ミケランジェロに暗く惹かれし少年期肉にひそまる修羅まだ知らず
エジプトの奴隷絵図の花房を愛して母は年わかく老ゆ
略奪婚を足首あつく恋ふ夜の寝棺に臥せるごときひとり寝
有頂天に生きてみづみづと孵化しゆく少年の渇を人らは知らず
火祭りの輪を抜けきたる青年は霊を吐きしか死顔をもてり
牛飼座空にかたむき遠くわれに性愛を教へくれし農夫よ
子を産みし同級の少女の噂してなまぐさきかな青年の舌
絵画や彫刻のモチーフが頻出。この辺りから家族や血の「待逃れがたさ」を朧げに感じ始める。〈子を産みし同級の少女の噂してなまぐさきかな青年の舌〉が男性の身体性の暗がりの中に発見している獣臭さは、案外表面的に見えるけども、キャッチーで届く。
「雪炎」
季めぐり宇宙の唇【くち】のさざめ言しろく降りくる冬も深まる
肉声をはるかに聴きてくだりゆく霧の運河にひたる石階
だみ声のさむき酒場に吊られゐて水牛の角は夜ごと黝ずむ
膝つきて散らばる硝子ひろはむか酔漢の過失美しければ
帰りゆくさむき部屋には抱くべき腕さへもたぬ胸像【トルソオ】が待つ
ことばなど失ひはてむ日がくると仰げり小暗く雪の舞ふ空
雪の冷たさの中に熱が見出されるという在りようは、この歌集における作中主体の在りようともリンクするのではないか。
「弟子」
ヴェニスに死すと十死つめたく展きをり水煙する雨の夜明けは
唇びるに蛾の銀粉をまぶしつつ己れを恋ひし野の少年期
刺すことばばかり選べり指熱くわれはメロンの縞目をたどり
石膏のつめたき筒をぬくめゆく若く愛されやすき両脚
無骨なる男の斧にひきさかれ生木は琥珀の樹液を噴けり
傷つけばなべて美し薔薇疹も打撲のあとの鈍き紫紺も
旅にきて魅かれてやまぬ青年もうつくしければ悪霊の弟子
太陽の金糸に狂ひみどり噴く杉のを描きしゴッホ忌あつし
ねむられぬ汝がため麻薬の水汲めば窓より寒く雪渓は見ゆ
力のある歌が並んでいる印象。師弟関係を性的な関係に読み替えていく作業が行われている。思えばこれまでの章でも、同性、血縁関係、師弟関係などの社会の中では性的関係に読み替えることを禁忌とされてきたものを、あえて侵犯している。
「火柱像」
磔刑の絵を血ばしりて眺めをるときわが悪相も輝かむか
ひとときを燃えて悔なし金環の陽が翳るときほそく息吐く
沈丁花の淡紫のしづむ午さがり未生の悪をなつかしむなり
星落ちて宇宙組織の脱落者のわれのみならぬことを哀しむ
両の眼に針刺して魚を放ちやるきみを受刑に送るかたみに
獄舎の君を恋ひつつ聴けり磁気あらし激しき海を伝へる電波
暗緑の菌糸きらめく石壁にもたれて形余の友を恋ひゐき
独房に悪への嗜好を忘れこし友は抜けがらとしか思はれず
軟禁の友を訪ひゆく夜くらく神をもたねば受難にも遭はず
罪を犯し獄へ向かう友人を見送る自分。自分は悪の途に踏み込むことはしない(いつだってこの作中主体は消極的である)にも関わらず〈独房に悪への嗜好を忘れこし友は抜けがらとしか思はれず〉などど述べる。悪への憧れがあるのだが、それを成就させないことにマゾヒスティックな快楽を覚えているようにすら見える。60年という時代を考えれば安保なわけで、独房などどいう語は同時代的状況とも確かに響き合っていたはずである。
「血忌」
晩婚に生みたるわれを抱きしめし母よ氷紋のひろがる夜明け
芽水仙に光が氾濫する昼は累々と毛嫌ひするものが増す
死せる兄生きゐる弟みな冥くながき血忌の胸ふかく棲む
「兄妹」
あばら骨つめたく軋みて氷上を追ひゆかり飢ゑしわれ男巫【おとこみこ】
雪まみれの二月といふにまざまざと干からぶ眼窩もつ兄弟か
千の嘘告げしつめたき愛のため少女の雨の日の夢遊病
「血忌」「兄妹」二つの章とも歌はやや弱い印象を受けたけれども、家族や血という主題についてより厚みが出ている。ただ、この先には天皇制の問題があるはずだけれども、春日井はそこまでは踏み込んでいない。これは春日井の手落ちであると思う。この歌集における唯一の欠点を挙げるとするなら、世界観の構築を優先して斬るべきもののすぐ近くまで到達しながら斬らなかったことを挙げたい。
「洪水伝説」
鉄舟を漕ぎゆか男みづみづと幾千のノアの水漬ける街
水ひかぬ路地の露店に骰子を振るわが欲望の鳥【イアンクス】の泥光る手よ
無尽数の白兎がとべる波がしら大洪水の後も騒ぎたつ
夜の海の絡みくる藻にひきずられ沈むべき若き児が欲しきかな
わが手にて土葬をしたしむらさきの死斑を浮かす少年の首
余剰なるにんげんのわれも一人にて夕霧に頭より犯されゆけり
最後の章。神話と名古屋(春日井健は愛知県の人である)をオーバーラップさせていて非常に読みごたえがあった。水の底に沈んだ大都市名古屋。ああこれだけ豊かな物語をカタルシスで終わらせてしまうんだなという微妙に残念に思う気持ちもありながらだが。
とはいえ春日井建『未青年』を通読して感じたのは、これを過去のものとして通り過ぎるにはあまりにも惜しすぎるということである。幸い、近々読本が出る水原紫苑をはじめとして、健に惹かれ、師事した歌人は多い。それだけ健のエッセンスは歌壇には分有されているはずだし、彼らからにじみ出る『未青年』を感じるのもそう悪くはないはずだ。
*春日井建の表記に誤りがある箇所がありましたので修正いたしました(2021年3月13日)