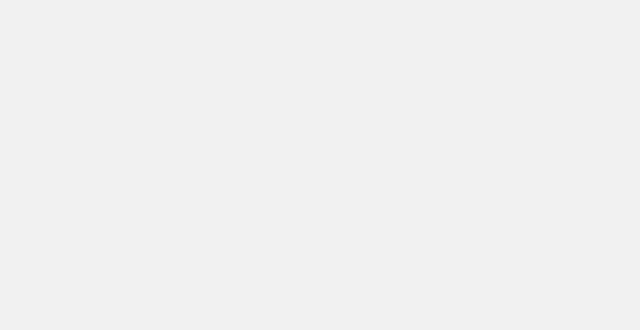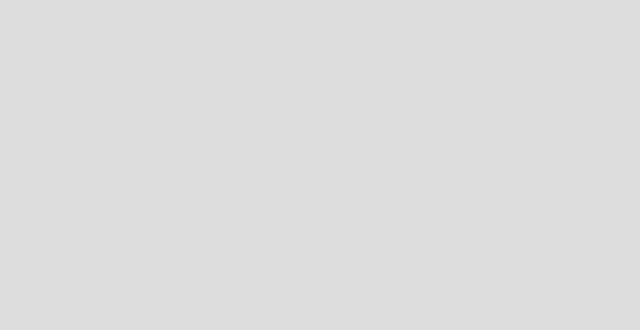所収:『広い世界と2や8や7』左右社、2020
制服にセロハンテープを光らせて(驟雨)いつまで私、わらうの/山崎聡子
あめいろの空をはがれてゆく雲にかすかに匂うセロファンテープ/笹井宏之
疲れっぱなしの下半期 百均の幅の小さいセロハンテープ/武田穂佳
自分はこれからもっと悪くなる 見なくてもわかる 幅の小さいセロハンテープ/同
セロハンテープといってぱっと思い出す歌を並べてみた。その透明さからくる素敵な雰囲気が詩的に昇華されていくものもあれば、生活圏内で多用する道具としての一面が濃く出ているものもある。
永井の歌は、どちらかというと生活の中の一道具としてのセロハンテープ感が強く出ている。「カッター付き」であることで一気にストレスフリーになるセロハンテープ。もし詩的なものとして「セロテープ」を見つめるなら、カッターがついていようがついていなかろうがさほど関係ないだろう。「付きのやつ」という言い方からも、より便利なものだとなんとなく捉えられているだけで、それ以上のものは見られていないように思う。
この、ふつうセロハンテープといえば思い浮かんでしまうような透明な素敵さを、ほぼ無視して道具として押し出すことが、逆に詩的に感じられてくる。
下の句では、「生きてること」自体の素晴らしさで「盛り上がりたい」と言う。たしかに、生きつづけていること、生きられているということは常に奇跡の上で成り立っている。生きて、社会の中で動いて、忙しく色んな事を考えていると、つい生きていること自体の奇跡を忘れてしまう。改めて生きれていることで盛り上がりたい、という主体の気持がとても分かる。
ここで面白いのは、その感覚が生じたきっかけが、カッター付きのセロテープを買ったという点である。見過ごして忘れてしまうようななんてことのない幸福、というのを、そんな小さな道具が引き出しているというのが面白く、感動的である。ここで、うつくしいセロハンテープの透明さが、主体に人生まで透かして見せて、こう感じるに至ったなどと無理矢理詩的に解釈していくことも可能ではあるが、ここではそれはしない。セロハンテープを詩的な要素として使っているから良くなっているのではなく、敢えて道具的な側面を言うことでそんな道具から考えたのかと思わせ、飛躍自体の詩的さを全体で増幅している点が優れているのである。
実際この歌は、いち道具から思考が飛び過ぎているのに、さほど違和感なく受け入れられるのは、それくらい思考というものは常日頃からぶっとんでいるんだということが、無意識のうちに分かっているからなのかもしれない。上の句と下の句というテンプレートを持つ短歌は、その形からして、そういう生活上の思考の飛躍を記すのにはぴったりな形なのだろうと、永井祐の歌を見て改めて思う。
とだいたいこの歌に関してはそういう把握(小さい道具に端を発して、生きていること自体の嬉しさに目を向けたという歌)だが、最後の「盛り上がりたい」には若干アクというか、すっと飲み下せない何かがあるように思う。
この「盛り上がりたい」を、テンションの高いクラブでのダンスや、友達と集まってするパーティーのようなものとして考えると、急にみんなを巻き込んでいるのが気になる。生きてることを「みんなで」盛り上がりたい、となると、そこに事情を見てしまう。何もかもみんなと感情を共有したいという若者的な感覚なのか、みんな生きてることの奇跡を忘れてしまっている、そうさせられてしまうような忙しく圧をかける社会があると非難する意図があるのか。
「盛り上がりたい」をひとりの、自分自身内で完結する感情と考えると、「たい」が気になる。~したい、という言い方は、その時点ではそれが叶っていないことを意味する。空を飛びたい、と言えば、今は空を飛んでいない。ご飯を食べたいと言えば、今はご飯を食べていない空腹な最中だと考えられる。「盛り上がりたい」とは、今、またそれまでは生きてることだけでは盛り上がれていなかったことを意味する。ここでも、生きてること自体の大切さを忘れさせてしまっていた原因をいろいろ想像してしまう。
カッター付きセロハンテープから、「生きてることで盛り上がりたい」と思えた、その思えたということに希望を見たいが、主体は果たして今後生きてることで盛り上がり続けることは出来るのだろうか。買った一分後には、そんなこと言ってもやっぱりそれだけじゃやってられないよね、と熱が冷めてしまうかもしれない。
この歌に、生きてることで盛り上がるぞ~と嬉しくなっている主体を見るのか、生きていることだけでは正直盛り上がれないと分かっていて寂しくもそう言っている主体を想像するのか、私/みんなが生きていることだけで盛り上がれるような世界になればいいのにと祈りに近い感情を抱いている主体を想像するのか。はっきり見えるようで、見えない、まさにセロハンテープの歌だなあと思ってしまう。
記:丸田