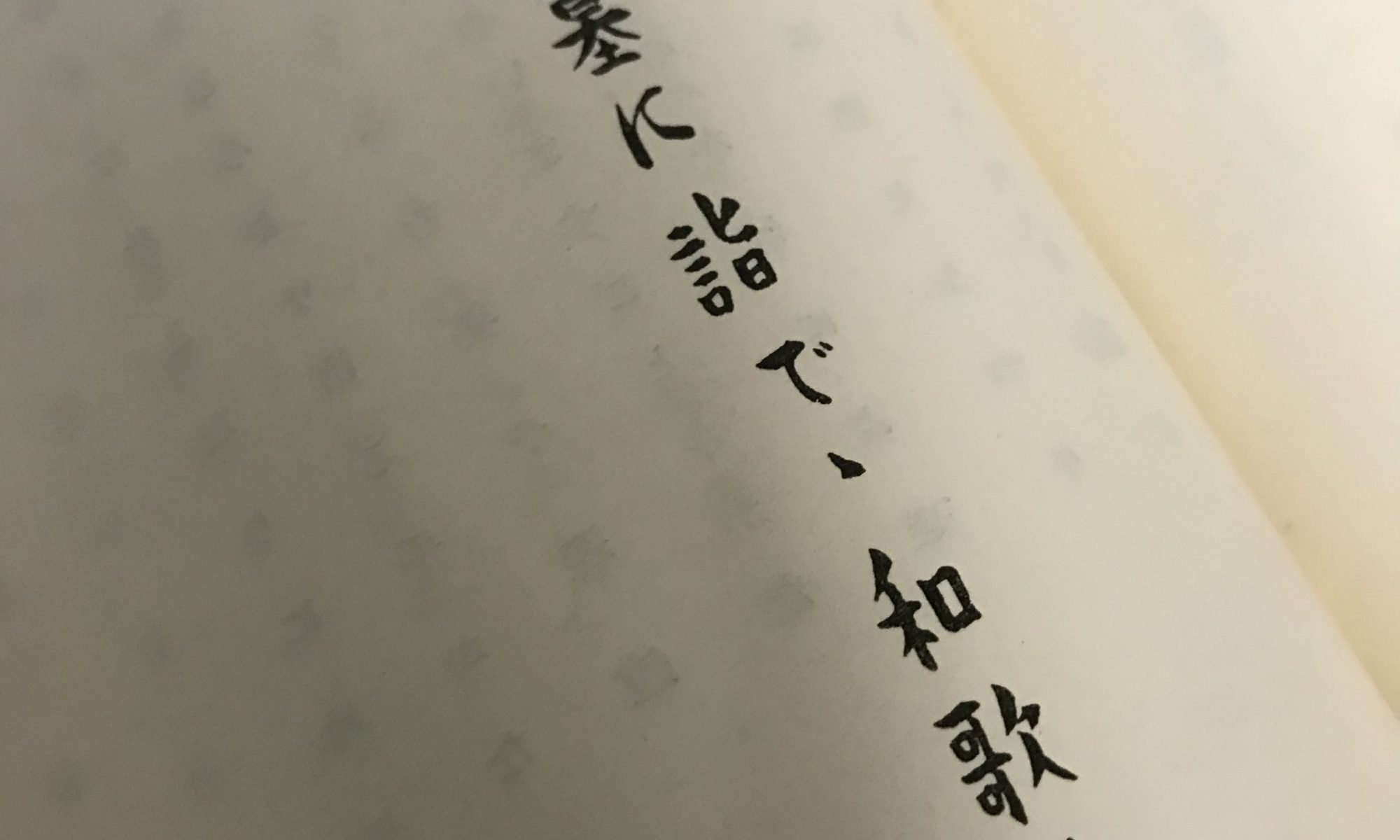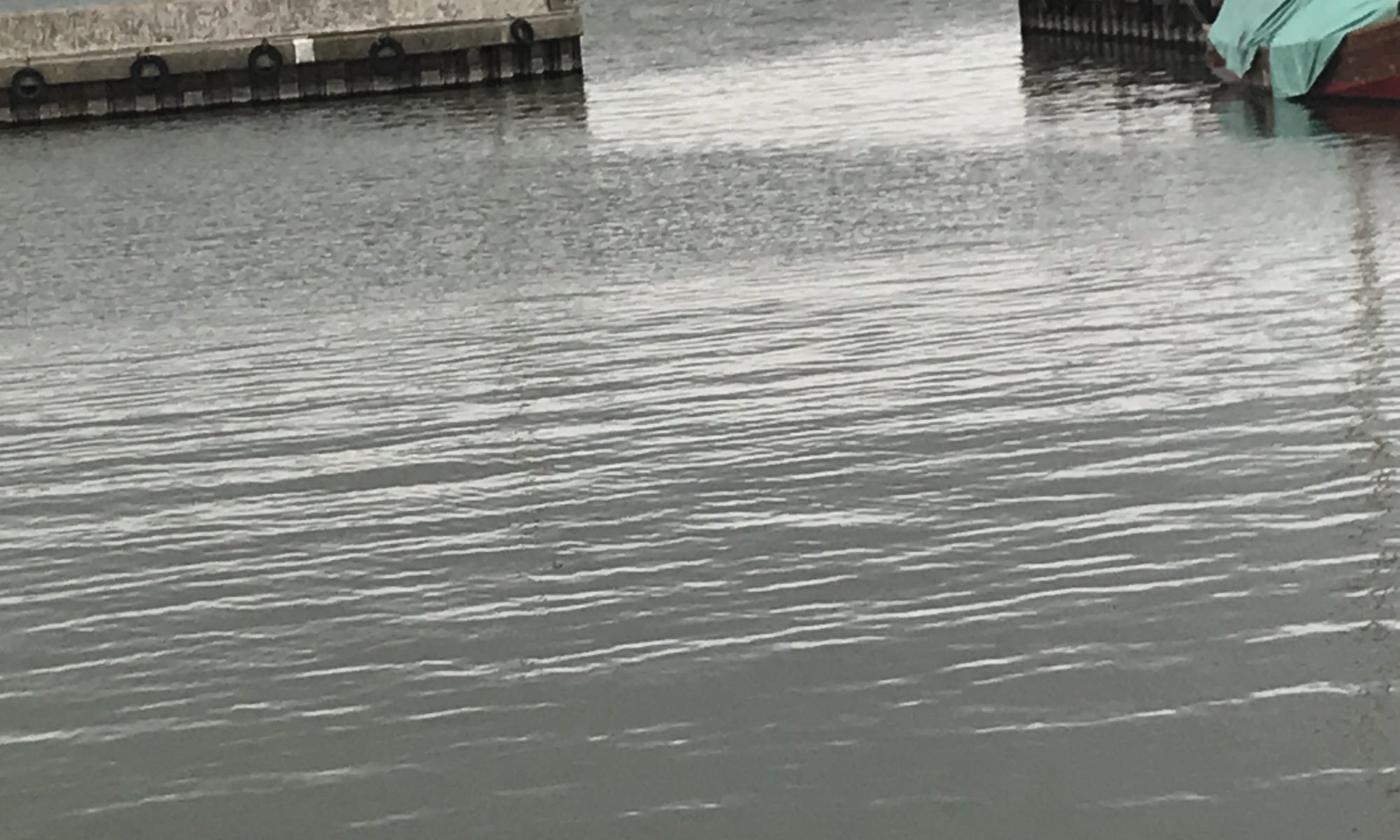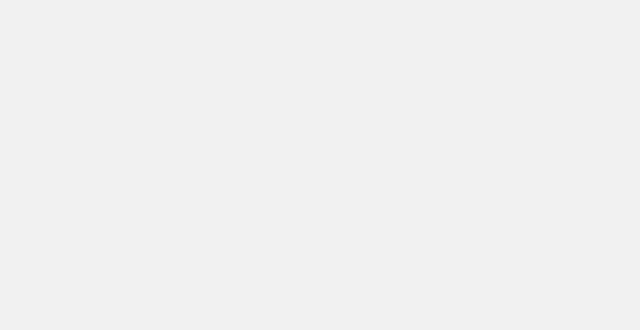所収:『白蛾』短歌新聞社 1997(底本:『白蛾』第二書房 1953)
以下、頭の中で雪が積もった話である。
──────
頭の中では何が起きるかわからない。ときにサーカスのようにアクロバティックで、ときに石のように整然としていることもある。それ自体は魅力的なことでも、短歌(に限らず文章全般)で「頭の中」と言うのには、いくつかの困難が付きまとう。
例えば今から怖い話を聞くというときに、「さっき思いついた話なんですけどね……」と言って話しはじめられると、怖がれなくなってしまう。お化けや幽霊がいたわけではなく、相手の単なる想像話と思い、一気に気が緩んでしまう。別にさっき思いついた話だとしても本当は良いはずなのに。(「友人の〇〇から聞いたんですが……」という怖い話の前振りはだいたい嘘を嘘っぽくなく言うための言い回しだし、ホラー映画もだいたいは創作。)ただ、怖がる時には、その人の話が(嘘だとしても)本当っぽいことが大切で、嘘であると明示されているなら、分かっていても怖がれるくらい怖いものを求めてしまう。
これが短歌でも起きる。俳句や短歌では現実・感情ベースなため、「頭の中」と先に言われると、「そうですか」と一歩引いてしまう読者が出てくる。頭の中なら何が起こってもいいのだから簡単だ、本当に見たもの、感じたものこそが肝心なんだという風に。それに、怪談と同様に、創作だとしてもそれを作品内で言わなくていいじゃないかという意見も考えられる。「頭の中」に自然発生的に、自身は意図せず景色が生まれているとしても、その頭はあなたの頭なのだから、どうしてもそこに操作(傀儡の糸のような)が見えてしまって乗れない……。
──────
ところで森岡の掲歌について、私が最初に読んだときに思ったことを順に記す。上から読んでいって、「頭の中の」で、「頭の中」と言ってしまったら損することもあるのに、それを言ってしまうなんてよほど面白いことがあったんだろう、それか、言わないではいられない(実際に外で見ましたよ、という風な変更は自身に許さない)誠実な方なのかな、と思った。次に「雪」が登場し、「片隅に」の指示があって、「青磁の壺」と「グローブ」が出てくる。脳内特有の、順番の唐突さが面白く、同時に、(歌として面白くなるものを持ってきているのだろうと予想されるので、)「青磁の壺」と「グローブ」のぶつけ方と、「雪」と「青磁」(とわざわざ壺に修飾させられた情報)の色の混ぜ方に、センスが見られるなと思った。そして最後に「がある」。「頭の中に」と始まって「がある」で終える。さっぱりしているようでなんとも力強い、濃い(ビビッドな?)表現だなあと思い、なんとなくメモしておいた。
それからしばらく経って、花山周子『風とマルス』を読んでいると、次のような歌に出逢った。
しずかなる机の前にいたりけり頭の中をからすが飛べり/花山周子(『風とマルス』2014)
静かな机の前に主体がいて、頭の中をからすが飛んでいる。心地よい静かな歌。瞑想にも近い、頭の中の光景が述べられている。これは、言葉がシンプルで丁寧に選ばれているからなのか、そうなんですね~だけでは終わらない静かさの気持ちよさがある。「しずかなる机」という表現から、その前にいる主体も静かに見えてくるし、「からす」の飛翔だけが聞こえてくる。主体も空間も静けさを通して一体となっているような感覚。頭の中の空と、机の向こうにある本当の空が一致しているようにまで感じ、外でもからすが同時に飛んでいるんじゃないかとまで思った。机の上に窓があったなら、その窓は確実に空いているような。
「頭の中」と作中で言う歌は他にもたくさんあるが、そのとき偶然森岡の歌を思い出して、もう一度歌集を開いて確認した。
──────
花山の〈しずかなる〉ではもっと現実と頭の中の光景を繋げてその響き合いを楽しんでいたが、それとは違う……と、思ったときに、最初に読んでいた時はそこまで強くは意識していなかった、「頭の中の」の、二回目の「の」に目が行った。
最初に読んだとき、なんとなく脳内の話という把握だけして、あとは文字上、言語としてのセンスを見ていた。よくよく考えれば、〈しずかなる〉と同じ読み方をしていた。というのは、頭の中の雪と、「青磁の壺」・「グローブ」がまったくの別の場所にある、と読んでいた。「片隅に」が現実への視点移動を担っていて、頭の中では雪が積もるという美しいことがあったが、現実の部屋の片隅には~という歌だと。
もしそうだったら、自分なら「頭の中に」と書くだろう、二回目にして思った。部屋の片隅に在る物体と、脳内の齟齬・すれ違い方を見せたいから、「頭の中に」とした方が、よりそのすれ違いが鮮明であるし、「に」の方が、より頭の中に雪が積もったんだぞ!という実感が強く出てくる。接地面としての脳内も魅せられる。
しかしここで「に」ではなく「の」だということは、すらすらと繋がって、上から下まで同じこと、つまり一首通じて終始頭の中の話をしているのだと分かった。雪が積もっているその片隅に、壺とグローブがある。
そうすると、このとき謎になってくるのが、青磁の壺とグローブは、どうして確認できたか、ということである。そこにその二つがあることを知っていて、そこに雪が積もった、のを逆から言っているのかとも思ったが、それだとどうも「片隅に」が引っかかる。「その中に」なら理解できる。「片隅に」というのは、確実にそこだ、と場所を指さしているような言い方で、そこに二つが実際に(脳内の話だが)見えているような言い方だと思う。
そう考えると、雪が積もった後、「その上に」壺とグローブが「ある」のではないか。雪に積もられてしまっては見えなくなるし、もし半分くらい積もって半分くらい姿が見えているのだとすれば、グローブなので、「つもりぬ」と言えるほど積もっていないことになる。
とすると、雪が積もった後、二つは突然に、雪の上に、出現したことになる。それが上から置かれるようになのか、下からせりあがってくるのか、自然に在ることになったのかは分からない。が、雪もそこまでかかっていないような姿で、二つのものがあることになる。(私が好きな推理小説で、一面の雪の上に、足跡の一つもなく血で染まった死体があるシーンがあったが、それを思い出す。)
そこがこの歌の読みどころなんだ!と閃いて、少し感動していた。普通の現実の光景との交わりのようにも見せながら、助詞や順番(雪→物)にこだわって細部まで操り、頭の中の美しい光景をしっかり頭の中っぽく描いている。頭の中だからこその順番、出現の仕方が自然すぎて、傀儡の糸は完璧に透明だった……。
──────
と読んでみて、ふつうに、これは歌の良さと言うより、自分が勝手に翻弄されたように迷って得たものであり、自分の読みの力不足でしかないなあと思いつつ、この鑑賞記事を書いていると、急にはっとして、「ぬ」に目が行った。助動詞「ぬ」はおそらく完了の意味である……。そして、「ぬ」の終止形は「ぬ」、連体形は「ぬる」である……。
つまり、この歌は「つもりぬ」で一回切れて、「片隅に」で現実の光景に戻っている。頭の中の雪の映像から、現実の生活感ある青磁の壺やグローブに引き戻される強引な力が読みどころだったのだろう。ずっと「雪のつもりぬ/片隅に」を口語で言うところの「雪が積もった片隅に、」と読んでいた。
さんざん読み迷ったなあと思いながら、他の方が書かれている森岡の鑑賞の記事を調べて見ていると、阿波野巧也さんのnoteの記事(「歌集を読む・その9」2016年7月26日、2020年6月17日閲覧)にて、〈一團(ひとかたまり)飛びきたりたる水鳥の影が先きになりみづとまじれり〉(『百乳文』)について、「しかし、「飛びきたりたる」って文法はどうなっているんだろう。森岡貞香はそのへん怪しい歌がたまにありますね。」と指摘しているのを発見した。たしかに助動詞「たり」が重複している。
私もよくよく森岡の歌を確認しなければならないが、そういう節があるのだとすれば、可能性として「ぬ」を連体として使っていることも考えられる。
とすると、どちらにも読むことができて、どちらがいいだろうと悩む。個人的にはずっと頭の中の話の方が、雪との順番が面白いと思うが、おそらく切れを作って、現実への切り替えにした方が、壺やグローブの生活感が出ていいだろう。
右往左往考えているうちに、頭の中に、雪が降りはじめ、いつの間にか積もっている。どこにあるべきか自分の中で定まらなくなってしまった青磁の壺とグローブが、サーカスのように空中に浮かんだままになっている。
追記︰後半の、「つもりぬ」の「ぬ」が終止形で軽く切れているとしても、それは少し時間を開けている程度で、「片隅に」でたちまち現実に引き戻されるわけでもなく、積もった雪の上の片隅を差している、とも読めるので、文中ではかなり雑に判断してしまっています。その他にも根拠の足らないまま判断している部分があるので、読みの力を更に付けていつか再挑戦をと思っています。
記:丸田