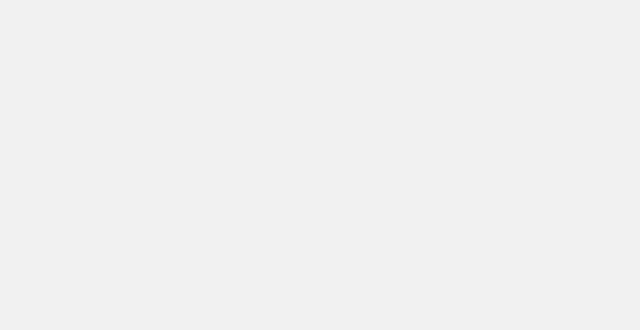所収:『鯉素』永田書房 1975
岩井英雅が『森澄雄の百句』の中で掲句を紐解いているのだけれどもこれが中々森澄雄らしいエピソードを引いていて面白い。
盆休みの八月、澄雄は四泊五日の旅をし、伊吹山に登った翌日に琵琶湖に浮かぶ多景島に渡った。生駒山地の南部にある信貴山へ登ったのは五日目。おみくじを引くのが好きな澄雄が朝護孫氏寺でひくと、五言絶句が記されていて、結句の「重ネテ鰲ヲ釣ル釣を整フ」が豪気で大変気に入ったという。鰲は想像上の大海亀。
白状すると先ほど森澄雄らしいエピソードと言ったのは「おみくじを引くのが好き」というところで、こういう言ってしまえば仕様もない俗っぽさを進んで引き受ける人間臭さに、どうしようもないよろしさと、鑑賞文をそういう消費の仕方で興じてしまう自分のはしたなさを思うわけだが、掲句には直接の関係はない。
さて、岩井が述べるように鰲(ごう)というのは想像上の大海亀であるようだ。てっきり適当な小魚と解して素通りしていたのだか、大亀となるとかなり句としてはやや大味な句になる。鰲というのは例えば龍宮神話で浦島を連れてゆく亀を鰲と呼んだりもするし、あるいは『金鰲』という小説が朝鮮最初の小説として李朝時代に金時習によって書かれていたりするようなのだが、いずれにせよ表象として鰲というのは空想の動物であり、であるからこそ夢の中でしか成立しないのだ。
とはいえ、掲句は夢オチなどといった愚劣な語りの形式と一緒にしてはいけない。掲句がそういった足の早い一発芸と根本から異なるのは、夢を見ることそれ自体はうつつの営みであり、脳の束の間の遊戯が生活の中に組み込まれているものであることを秋昼寝という淡さが担保しているからである。生活に根差しているという感覚を措辞がしかと持っており、だからこそ夢であってもそれは生活の中のものなのだ。それは森澄雄というコンテクストがあるからなのかもしれないが、だからなんだというのだろう。亀は釣れるものなのだろうか、亀を釣る為の釣り針というのはどういうものなのか、如何なる強度をもつ釣竿で釣り上げるのだろうか、そういう疑問を淡くぼんやりとした身体感覚で包み込む季題が「秋昼寝」である。湖の水面もどことなく澄んでいる感じがしてくる。
記:柳元