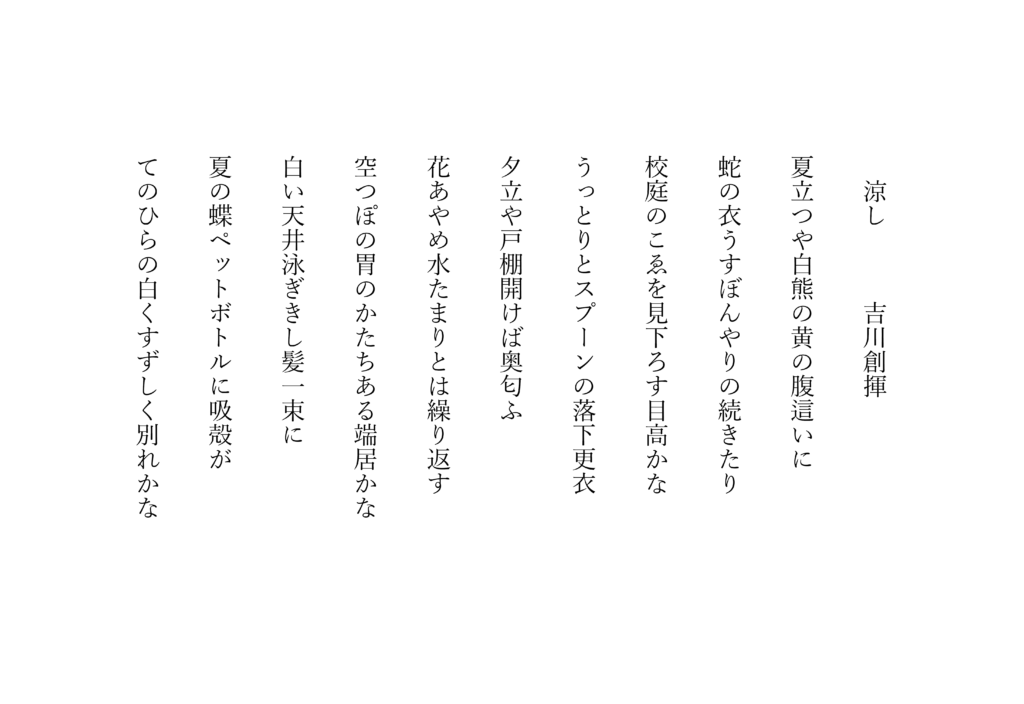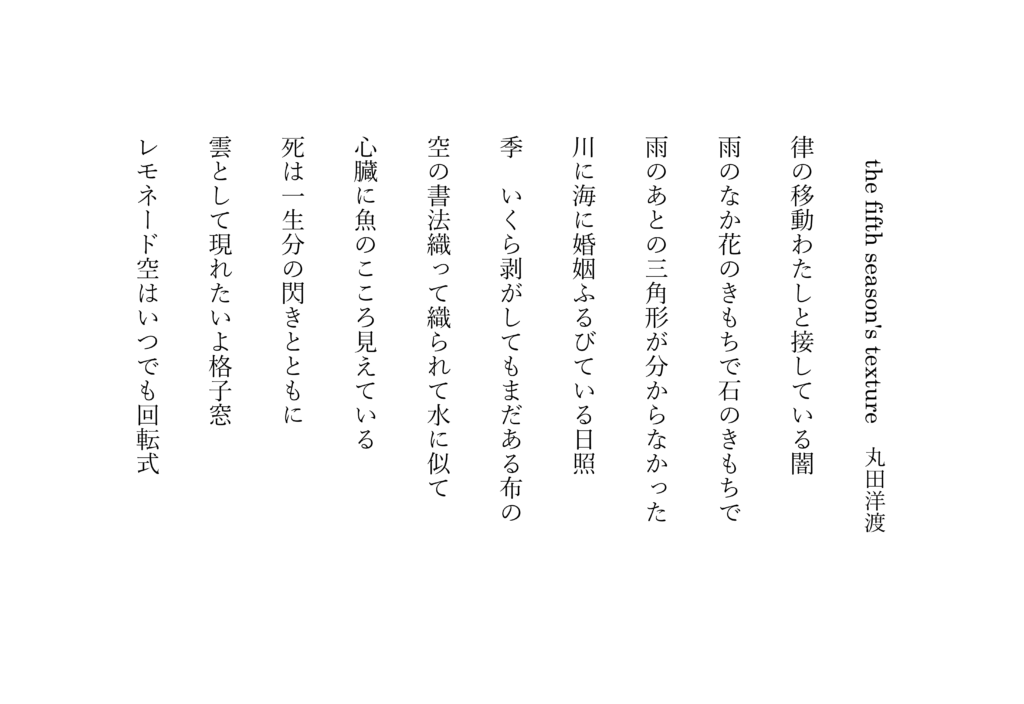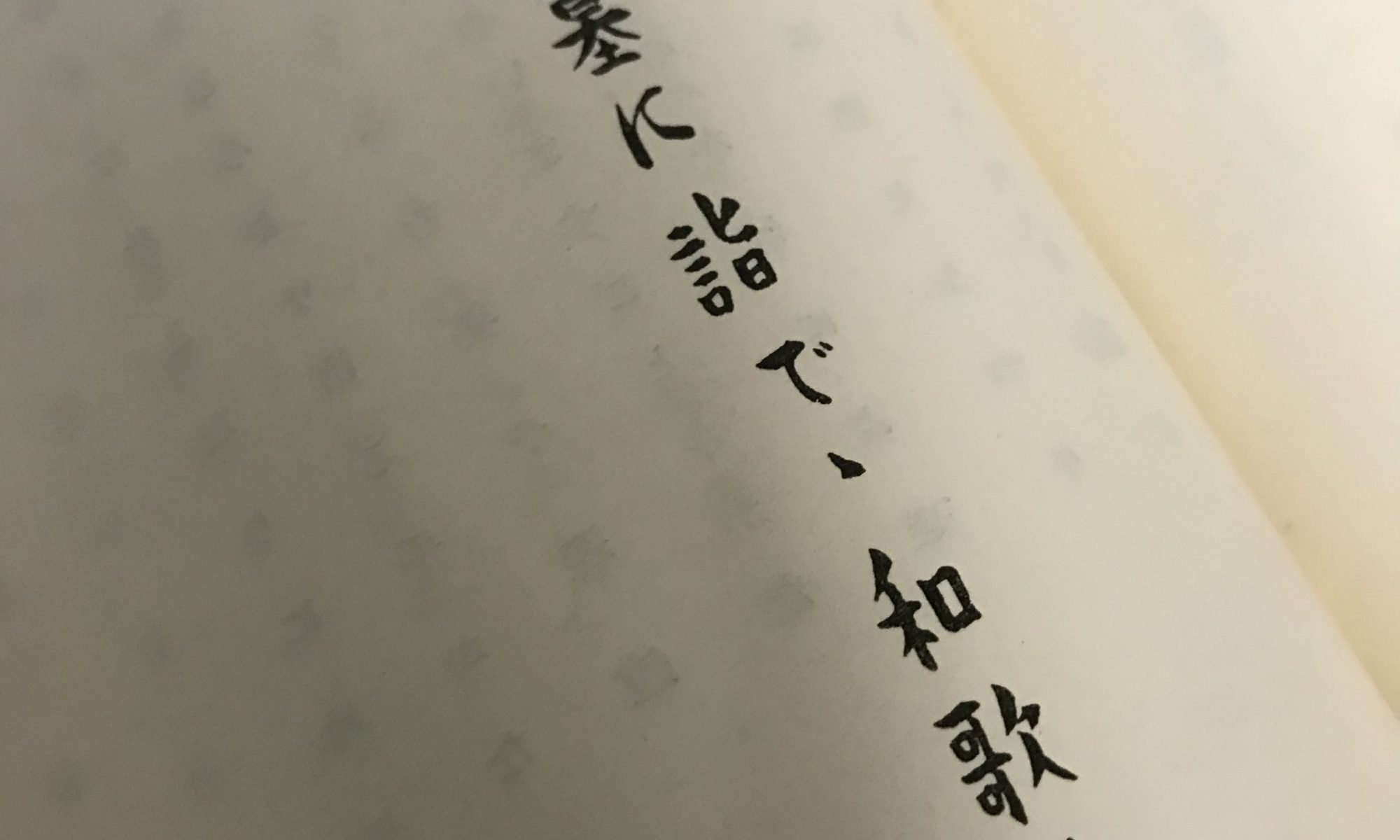所収:『春の蔵』永田書房 1980
きつねのかみそりはヒガンバナ科の植物で、お盆の頃になるとややオレンジがかった朱色の花を咲かせる。花弁は6枚あって、そのいちまいいちまいが鋭い形状をしている。山中で狐が剃刀として使っているのだろうという連想からこう言った呼び名になったようである。
「一人前と思ふなよ」という呼びかけがこの季語と呼応するのは、剃刀というものが髭なり体毛を剃るものであり、剃刀を使い始める時期がちょうど大人と子供を分ける境目に当たるからだろう。
思えば初めて剃刀を使ったのは中学生の時で、産毛のような毛が口周りに生えてきて濃くなっていくものだから気持ちが悪かった。それを見兼ねた母親が安全剃刀を与えてくれたのだが、妙に気恥ずかしかったのを覚えている。
記:柳元