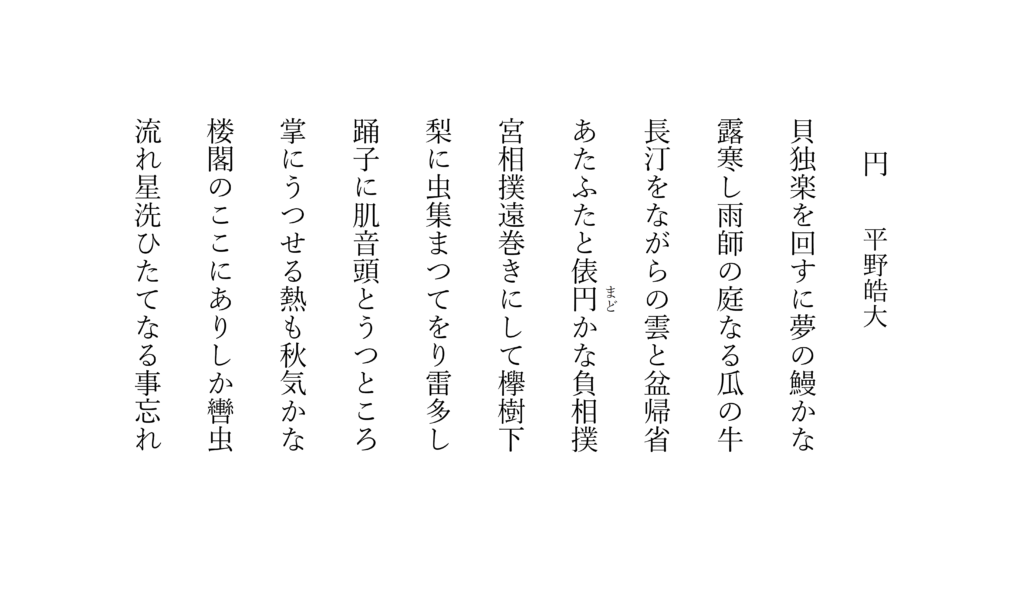所収: 『なめらかな世界の肉』(ふらんす堂、2016)
岡野の句集を読むと、素直、奔放、あたりの言葉が思いつく。思ったことをそのままに言うことの力がある。〈音楽で食べようなんて思ふな蚊〉、〈菊膾こつこつやる人がえらい〉、〈花冷えや脳の写真のはづかしく〉など。それがあまりに素直すぎて、失敗に終わっている句も散見されるように思う。しかし、作者特有の妖しさがそれに加算されたとき、魅力的な句になっている。
〈永き日の死は犬よりも育てやすき〉は、死が「育てやす」いのが怖い。育てるものという認識が一番怖いのに、「犬よりも」という面白さで中和しようとしている奇妙すぎるバランス感覚がさらに怖い。〈しどけなきデージー見せてそれから銃〉の「デージー」からの「銃」の落差に迫力があり、「見せてそれから」の剽軽さもかなり怖く、魅力的である。
掲句〈天の川音のするまで右に廻し〉も、一見、天の川を奔放に使って(使いまわして?)いる句だが、「音のするまで」がイメージの天の川を、生の(?)音の鳴る天の川にしている。何も情報がない状態で天の川を回そう、とは流石にならないだろうから、回せば音がすることをどこからか知ったのだろう。そして、「右に」という具体的な駄目押しから察すると、おそらくこの音はオルゴールのようなもともと音を主としているものではなくて、宝箱のようなものを解錠するときの音ではないだろうか(初めて音が鳴ることを発見したのなら、「右に回すと音がする」という語順になるのが自然)。この句を妖しいものとして捉え直したとき、天の川を右に回した後に起こることは何だろう。宇宙という大きな箱が開いて、主体は何かを目撃することになるのか。
もしかすると、開けたあとの施錠の操作かもしれない。岡野の作品が一瞬見せる世界は、妖しく冷気をもって伝わってくる。