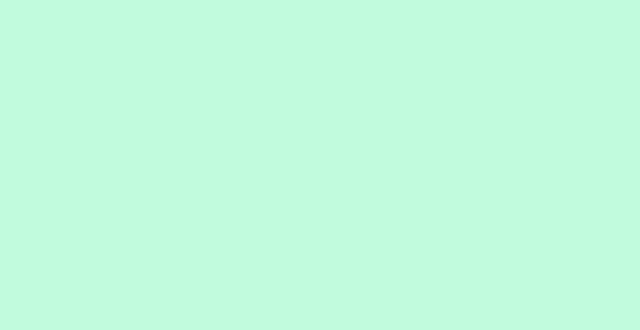所収:『ねむらない樹』vol.7(書肆侃侃房、2021)
連作「プライベート・ソウル」より。「永遠」という単語の登場からのびやかな歌かと思いきや、ぎゅうぎゅうに詰められた上の句はものすごく速く読むことを要請する。そして上の句をどういう速度やリズムで読もうかと読者が苦悶しているなか、挑発するかのように「飾り天使のコーラス・ワーク」という綺麗で分かりやすい七七が後に控えている。
まず最初に引っかかることになるのは助詞「は」だろう。費やす、という動詞から考えれば、「時間を費やす」のように「を」が来るのが居心地が良い。「君の〇〇を費やしてみてほしい」、と簡略化すれば意味は滑らかに入ってくる。ここが「は」になっていることで、一旦文が跳ねる印象が生まれる。跳ねるという表現が合っているか分からないが、「永遠」という言葉をより強調しようとして話そうとしているのが分かる。友人と会話するときの「今日面白かった話は~」みたいな「は」に感じる。この一瞬跳ねて強調される感じが、さらになめらかさを阻害する(これは人によって受け取る印象は変わるだろう。こういう取り立てて言う「は」が自然に聞こえる人であればそこまで気にならないかもしれない)。
なめらかさで言えば、「費やしてみてほしい」という部分も気になる。この勧誘の言い方からすると「君の永遠を(君が)費やしてみてほしい」ということになり、ここは「君は君の永遠を費やしてほしい」くらいでもよかった話である。これがぎゅっと凝縮されて(作者的には「刻んでいる」のかもしれない)、強引に「力試しに」が挿入されている。一見喋っているようであるが、ここには強い調整の力が入っているような気がする。小説の中で、登場人物が小説外の人に向かって話しかけているような妙な感じが。
「力試しに」。「君」にある永遠とはどういうことなのか、本当に永遠があるのか、一瞬に見えかくれする永遠性のことを言っているのか、それすらこちらは分かっていないというのに、永遠を費やすことが「力試し」のひとつになるという。ここでの「力試し」がどれくらいのテンションなのか(例えば、力試しで一問数学の問題を解くのか、力試しで重いものを持ち上げてみるのか……)によるが、そんなことで「永遠」を費やしてしまっていいのか、という漠然とした不安がある。これが、「永遠を費やしなさい」と命令されていれば、そういう物なんだと納得できそうだが、「力試しに」「してみてほしい」とこちらが責任を負う形でさりげなく言われると、なお不安である。
一体永遠を費やして何が分かるのか。どうなっていくことになるのか。「君」に対して話しかけているこの人物は、既に費やしたことがある何か達観した人なのか、何も知らないのに野次馬やファンのような感覚(うちわで「ウィンクして」みたいな)で言っているのか。
永遠は費やしても無くなることのないものなのか。
「力試し」という単語を聞くと、私はそこに他者の存在を見る。「肝試し」なら、自分がどれくらい怖がらない心を持っているかという個人の挑戦のニュアンスがある。一方「力試し」となると、他の人が複数いて、その人たちにもさまざまなレベルがあって、自分は今その人たちの中でどれくらいのレベルに位置しているのかを測る、という意味になってくると思う。学力を試すために模試を受ける、のような。
みんなは、どれくらいの「力」があるものなんだろうか。みんなも、力試しのために、所持している永遠を費やしてきたのだろうか。
生きている時間を大切にしなさい、とか、永遠なんてものは無い、みたいな言説が、おもいきり捻られた形で現れているように感じる。だから、「力試し」の言い方も、「してみてほしい」の優しいふりをした言い方も怖く感じる。この人物はどんな表情で言っていて、今まで何人にこんなことを言ってきたのか。
「飾り天使のコーラス・ワーク」は、急に短歌のフレーズのように聞こえる。やはり七七の影響は大きい。「飾り」という言葉も、「力試し」とほとんど同じ色である。なんだか、「飾り天使」「天使のコーラス」「コーラス・ワーク」とどの部分を取ってみてもちょっとずつ鋭さがあり、上の句を承けるには随分意地の悪い言葉である。
下の句は、上の句の背景としてあるのか、意味としてあるのか、象徴としてあるのか、到着先としてあるのか、関係は無いが裏で繋がっている映像なのか、私には分からない。ただ私には、「費やしてみてほしい」と言っている人物の顔がうっすら笑っていることだけが、はっきりと分かった。
この連作内での次の次の歌〈祈りまで脂まみれになっていく夜景のタワーみずからとがる〉を意識すると、より鮮明に見えてくるものがあると思う。
かなり難解で挑発的で、速くて、かっこいい歌だと思う。「コーラス・ワーク」の落とし方も、作者の(リズムの上での)(カタカナや語の配置上の)柔軟性を感じる。
またこの歌の話からは逸れるが、この連作はもっと多い歌数で見たかった。七首しかないとどうやっても窮屈である(短いことを分かっていながらそろえた詠草であろうから、これはこれで見ていて面白かったが)。とくに瀬口の歌は歌数が並ぶことによって生まれる加速や、速度のばらつきによって生まれる浮遊感に特長があると私は思っている。笹井賞受賞者の新作で個人賞は7首というのがなかなか渋いなあというのが紙面に対する正直な感想だった。ふつうに呼ばれた歌人の20首より、受賞者がどんな態度でこれからやっていくのか、それが示される新作の20首の方を私は見たかったかな、と思う。といっても雑誌全体では良企画が盛りだくさんであったため、これからもまた期待して見ていきたい。
記:丸田