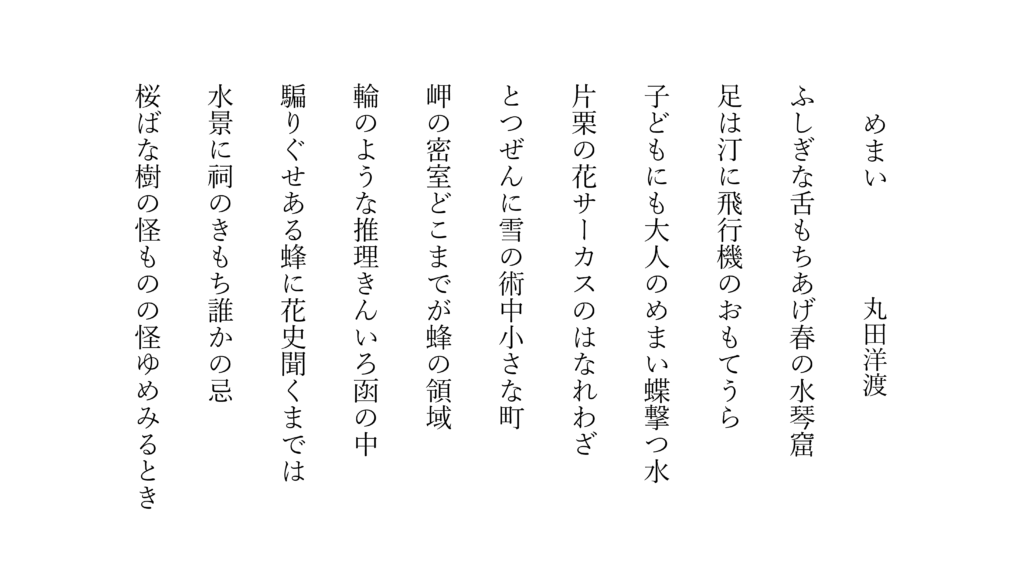所収:『古澤太穂句集』1955年
掲句には「中里学園にて」という前書があります。調べてみると中里学園は孤児院らしい。初出にあたれていないため掲句が書かれた時期は類推するしかありませんが、同時期に句集に収められている句との関係から推測すると敗戦直後、すなわち1945年から1955年の間であることは間違いないでしょう。
太穂は結核療養の後は終生横浜に住んでいました。運動などで飛び回っていたとは言え、やはり横浜に根差して書かれた句がやはり多いようです。横浜の孤児のことを考えるためには、その孤児の生育環境としての横浜を考えねばならないでしょう。そのためにまず横浜大空襲から話を始めます。
戦中、横浜の街に壊滅的な被害を与えたのは1945年5月29日の横浜大空襲でした。この横浜大空襲は白昼堂々行われました。これは焼夷弾が木造住宅の密集地に与える損害を計測することを目的とした米軍の実験的な大規模空爆であり、横浜市街を中心に大きな損害が出ることとなりました。「横浜大空襲体験講話」によると8000人から10000人の犠牲者が出ており、非戦闘員を狙った住民標的爆撃でした。以後横浜は焦土にバラックが点在することとなります。
『占領軍のいた街 戦後横浜の出発』(横浜市ふるさと歴史財団近現代歴史資料課市史資料室担当編 横浜市史資料室 2014年)に掲載されている戦後進駐軍が撮影した写真などを確認すると、桜木町駅の辺りは焼け残っているものの、市内は基本的に焼野原であることが分かります。
そして日本は敗戦を迎えます。1945年8月30日に厚木飛行場と横須賀港から占領軍の進駐が開始されました。厚木飛行場に降り立ち、タラップでコーンパイプを燻らせ、ポーズを撮るマッカーサーの写真は有名ですね。マッカーサーは日本側の出迎を断り、そのまま横浜に直行しました。このことが象徴的に示す通り、横浜は占領政策の中心拠点となりました。
8月30日から9月2日まで横浜の焼け残ったホテルニューグランドがマッカーサーの宿舎となり、東京に移転するまで同じく焼け残った横浜税関で執務をしていましたし、米軍の捕虜引揚の拠点でもありました。横浜は文字通り米軍の出入口、玄関だったのです(その名残は現在もキャンプ座間、厚木海軍飛行場、横須賀海軍施設などの米軍基地、あるいは根岸、相模原、池子の住宅施設が残っていることからも伺えると思います)。戦後の横浜は米軍と共にあったため米軍及び米軍基地の影響抜きに語ることは出来ません。
例えば米軍兵士相手の日本人娼婦の発生が挙げられるでしょう。中でも、黄金町は赤線地帯(半ば公認で売春が行われていた日本の地域)であり、黄金町周辺では米軍兵士相手の売春が公然と行われていました。不特定多数と関係を結ぶ娼婦もいましたし、特定の米軍将校の愛人となり囲われる「オンリーさん」も存在しました。そのような状況の中で、当然の帰結として米軍兵士の父親を持つ混血児「GIベビー」も誕生することとなります。太穂には〈巣燕仰ぐ金髪汝も日本の子〉という句が同時期にありますが、これはおそらくこの「GIベビー」のことでしょう。
また、寿町は大阪のあいりん地区や東京の山谷に次ぐドヤ街でした。寿町は戦後米軍の接収が解除された1956年以後に形成された比較的歴史の浅いドヤ街で、暴力団の流入もあり、放火や麻薬売買、流血事件などが絶えませんでした。身寄りがない独り者が流れ着くケースが多かったと思く、孤児も多かったようです。
太穂は以上のような「暗い」側面を持つ横浜に直面していたはずであり(ドヤ街の形成は『古澤太穂句集』以後ですが)、このような荒んだ横浜を直視する機会も多かったのではないかと思われます。そして、孤児というのは、こういう環境を所与として育っている者なのです。悪辣な環境の中で、身寄りもなく生活するのが横浜の孤児でした。
また横浜は横須賀港に大陸からの引揚孤児が居つく傾向にあり、また横浜駅が大きな駅であったから地方の孤児も集まって来ていたようです。このような背景に鑑みたとき、太穂が描いた孤児を取り巻いていたのは、現在のような洒脱な臨海都市ではなく、戦後も依然として混沌とした横浜であったと言えるでしょう。太穂の掲句を読むときに想像される横浜、孤児院の外側に広がる外部の横浜は、そういうものでなければならないと思います。
孤児は如何なる処遇を国や行政から受けていたのかについても検討しましょう。孤児に対する処遇については藤井常文『戦争孤児と戦後児童保護の歴史』(明石書店 2016)が詳しいです。そもそも孤児の問題が出てきたのは、当然のことながら戦後ではなく戦中からでした。戦争が激化するにつれ、親が出征して戦死した場合や、学童疎開で子だけが生き延びたケースが表面化し出すのです。
しかし、この頃は戦災遺児と位置付けられており、いわゆる一般的な孤児とは異なる位置付けがされていました。なぜなら戦災孤児は、戦争に殉じて亡くなった英霊たちの子であり、国の子なのです。ですから、最大限手厚く保護せねばならないというのが、戦時中に理念としてあったようです。
厚生省戦時援護課で企画された保護の方針の文言(戦災遺児保護対策要綱案)を見ても「殉国者の遺児たる衿持を永遠に保持せしむると共に、宿敵撃滅への旺盛なる闘魂を不断に涵養し、強く正しく之の育成を図り」とあり、行政政策においての「国子」としての位置付けが伺えます。
しかし、敗戦を受けて「国子」の扱いは「孤児」に戻ってしまいます。著者は人権保護的な理念からではなく治安管理的な理念から、戦後の孤児の保護政策が進められていたことを指摘しています。保護の方法が法律に定めが無かったため、実力行使的な収容が行われました。実際「狩り込み」と言われる、警察や職員による暴力を伴った孤児の一斉収容が1945年12月15-16日の両日に渡って行われ、この日は2500名にのぼる収容者が出たと『都政十年史』に記されています。
ちなみに「狩り込み」は俗称ではなく、行政の通知で平然と使われているところに、この時期の人権感覚がいかに鈍していたかが伺えます。せっかく収容しても施設の設備が不十分であり、衣食住の環境が整っていなかったために脱走者が相次ぐ。それをまた「狩る」。そして又逃げられては堪らないので、逃走防止のために服を着せなかったり、靴を与えなかったり、檻の中に閉じ込めたりする。このような施設が孤児たちにとって居心地が良いはずがなく、また脱走する、というようないたちごっこが続いていました。
法的な対応としては、1945年に「生活困窮者緊急生活援護要綱」が、1946年に「浮浪児その他の児童保護等の応急措置実施に関する件」と「主要地方浮浪児等保護要綱」が通牒されます。しかしこれらはどれも緊急措置的な側面が強く、実地的な対応に関することのほとんどは施設任せで、児童に配慮された内容とは言い難かったようです。そして1948年に児童福祉法が施行されることで、孤児院は児童養護施設となり、少しずつ人権に配慮されたものとなっていきます。
太穂が訪ねた中里学園は、1946年9月に県立の施設として開園しています(現在は閉園)。時系列的には1946年4月の国からの通牒を受け、県としても街に溢れる戦災孤児の収容の必要性を感じていたために開設されたものでしょう。中里学園がどのような保護施設であったのかについては資料にあたれなかったため類推することしか出来ませんが、充分な物資が確保されていたとは時勢的には考えにくいように思います。そのような時勢において、映画が上映される日というのは孤児たちにとっては非常に楽しみなものであったのではないでしょうか。
最後に、映画の内容はどのようなものだったのでしょうか。戦後の映画製作、上映にはGHQの統制があったことを忘れてはならないでしょう。
敗戦を受け、GHQの指令のもと、戦時の映画産業に対する国家統制は廃止されました。代わりにGHQが新たな方針を策定し、その指針に沿った映画産業の復興が試みられます。GHQは映画会社に対し「日本ノ軍国主義及軍国的国家主義ノ撤廃」など占領の基本目標に基づき「平和国家建設ニ協力スル各生活分野ニ於ケル日本人ヲ表現スルモノ」「日本軍人ノ市民生活ヘノ復員ヲ取リ扱ヘルモノ」「労働組合ノ平和的且建設的組織ヲ助成スルモノ」など 「映画演劇ノ製作方針指示」を示しました。ここでGHQは日本という国に民主主義を根付かせるための手段として映画を活用せんとしていたことが分かります。
また戦前の旧来的な思想に通ずるものは、製作だけではなく上映も禁じられていました。GHQは「反民主主義映画の除去に関する覚書」を発表し、国家主義や軍国主義の宣伝に利用された「封建的法典の遵奉、生命に対する侮蔑、武士道精神の強調」 などを内容とした日本映画を上映禁止処分とされています。
これを考えたとき、おそらく孤児院で上映されていた映画もこのような制約を多分に受け、民主主義的な新しい価値観に合わせた映画が上映されていたと考えて良いでしょう。太穂は「燕の天」という開放的で底抜けに明るい季語を取り合わせていますが、これにより映画の内容や、そのときの孤児院の気分が良く出ているのではないでしょうか。ある種の言祝ぎのような季語の斡旋に、太穂の戦後を喜ぶ朗らかさを感じます。
古澤太穂は1913年の生まれの俳人。本名太保(たもつ)、1913年に富山県上白川郡大久保村の料理屋兼芸妓置屋に生まれています。太穂は父死去による経済的困窮から母に連れられ東京、のち横浜へ転居。太保自身も家計を助けるため、様々な職を転々としつつ勉学に励み、1938年に東京外国語学校専修科ロシヤ語科を卒業します。しかし直後喀血、5年間の療養生活に入ることとなり、この療養生活中に水原秋桜子が主宰する「馬酔木」と出会い、1940年10月の「寒雷」創刊と同時に同誌に参加しています。以後は楸邨を師と仰ぎつつ、主宰誌「道標」や新俳句人連盟などを中心に活動しました。また俳句だけでなく政治運動や社会的な実践でも活躍しています。内灘闘争(石川県河北郡内灘町の米軍の試射場の設置に反対する運動、1952年から1957年の米軍撤退まで行われました)や松川事件(機関車転覆事故に関わる戦後最大の冤罪事件、1964年に全員無罪が確定)の支援を主とし、レッドパージの嵐吹き荒れる中で、大小様々な左派的な運動に精力的に携わっていました。
記:柳元