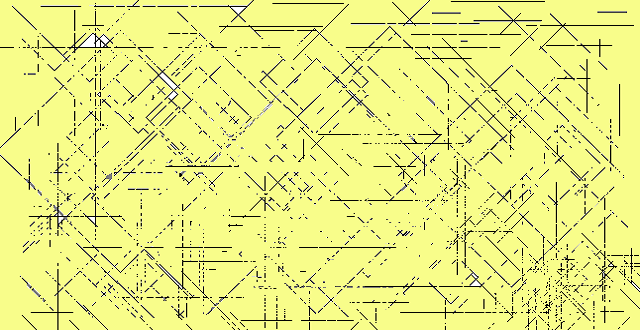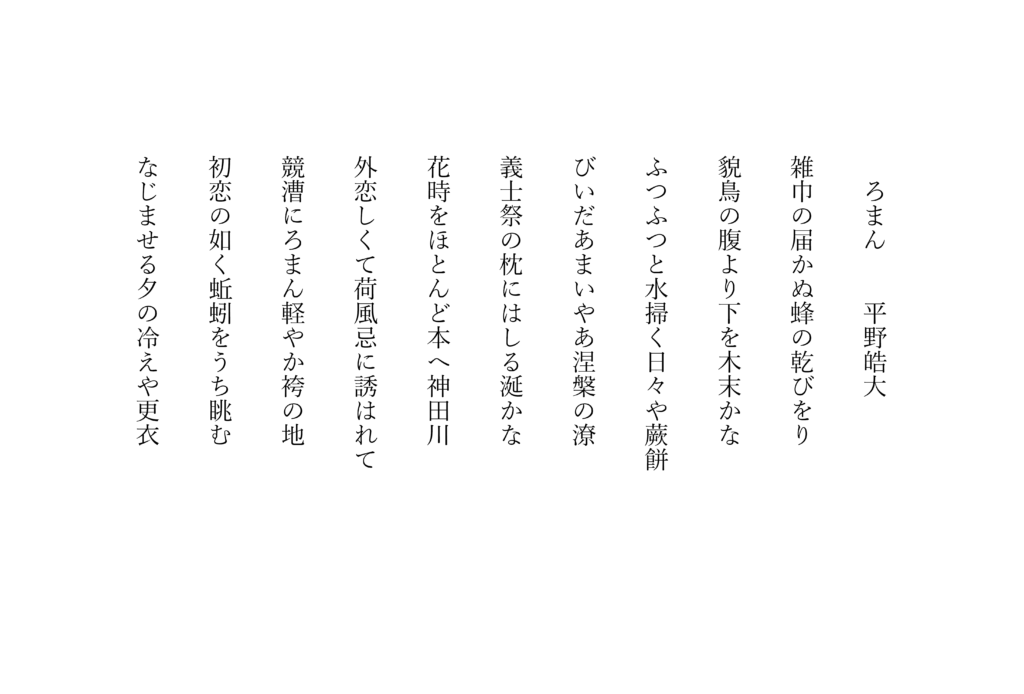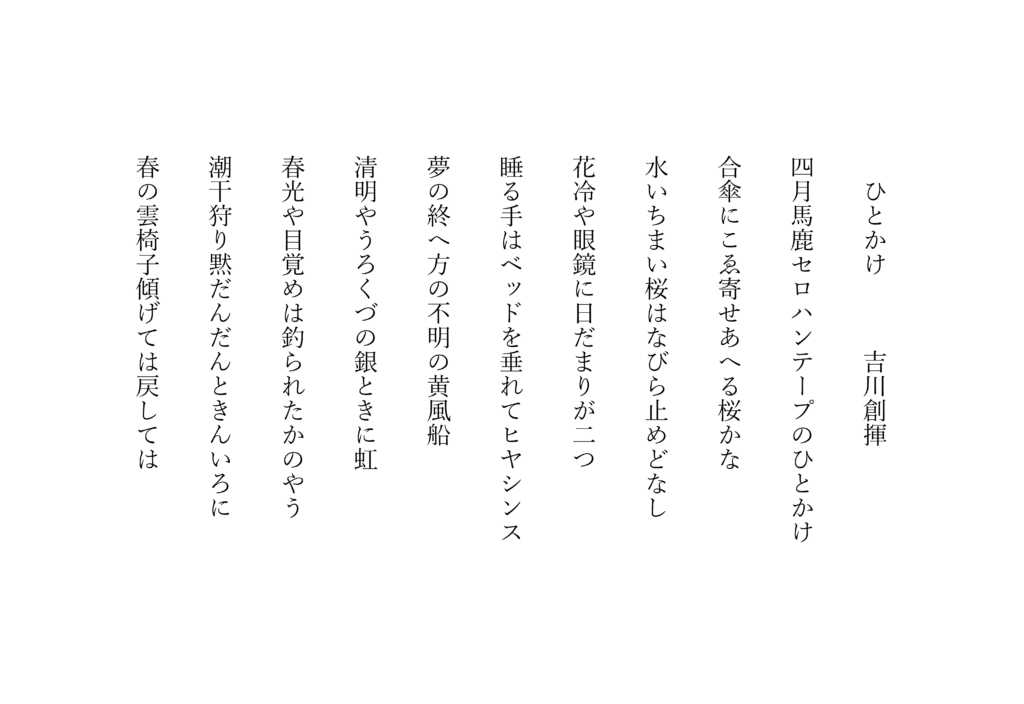所収:『松本たかし句集』1935年
船頭が棹で舟を10回も漕ぐことなく舟が向こう岸に着いた、という舟渡しの様子を詠んだ1句であろう。
表現の抑制の塩梅が巧みだ。
「渡し」の語の直後に「水の秋」と水のモチーフを置くことで舟渡しのイメージを補強している。また、直接舟という語を用いずに、動詞「渡す」を名詞にした形の「渡し」を用いることで船頭が棹で漕ぐ動きが見える。長い棹を静かに、しかし大きく動かす様は空間の広がりや、水の様子をイメージさせる。
10回も漕ぐことはなかったのだから短い舟渡しであったのだろう。川幅の短さがイメージされる。舟に揺られる束の間は、秋のもつ儚さとも響き合うかもしれない。
上5中7で、このように船頭の動作や川幅などの空間や、舟に乗っている短い時間をイメージさせることで、下5の「水の秋」は非常に活きてくる。「秋の水」は単に秋という季節の川や湖のことを指すが、「水の秋」は水が美しい秋という季節に思いを馳せる語である。「秋の水」よりも空間的にも時間的にもイメージの広がりが大きい「水の秋」という下5が、上5中7のイメージの広がりを受け止め、情緒の深い1句にしている。
作者の松本たかしは能楽師の家に生まれ、能楽師を志すものの病弱のために断念した経歴をもつ。私は能に詳しくはないが、舟が登場する能の作品もあるようなので、そこにインスピレーションを得た1句なのかもしれない。