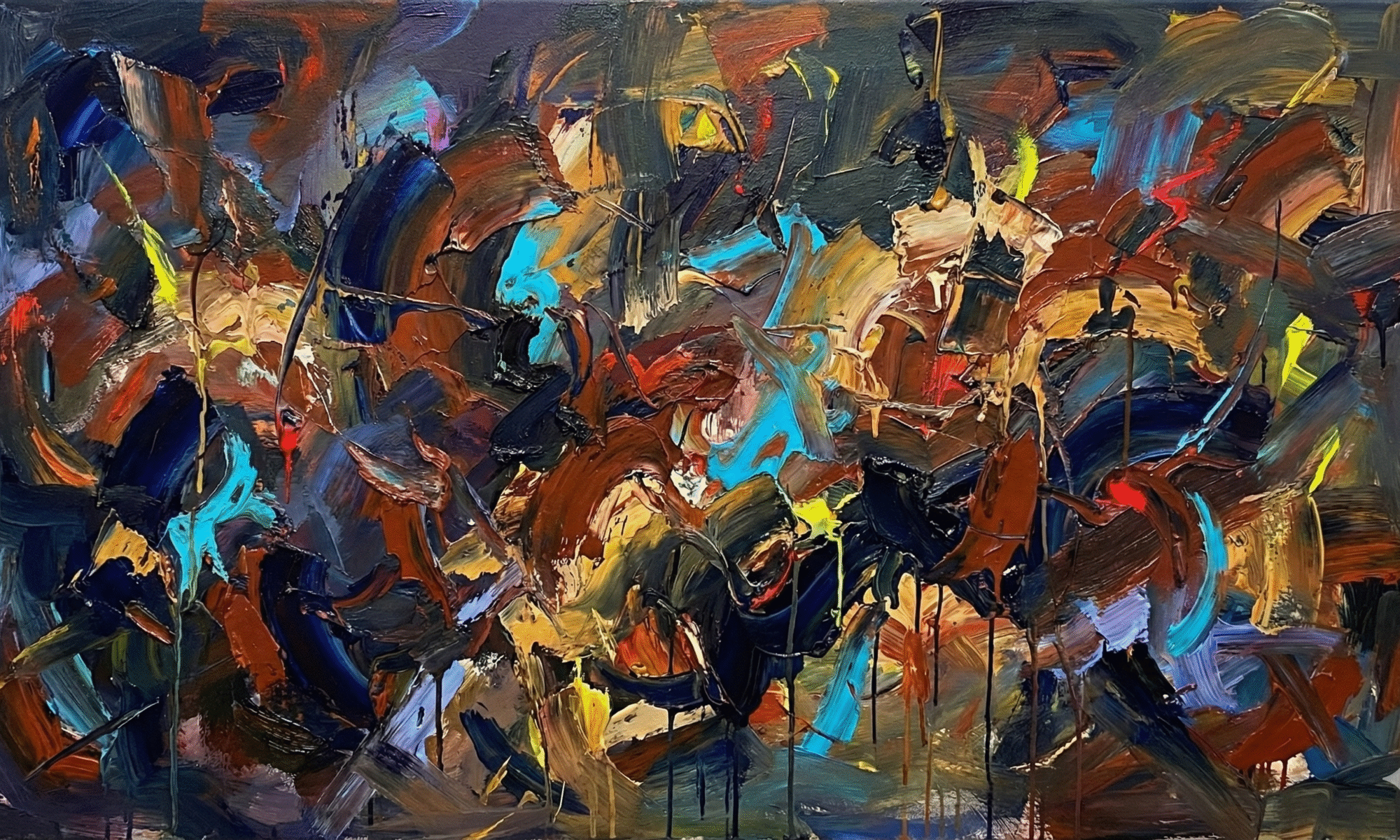安倍晋三氏を銃撃して殺害した山上徹也氏(「被告」という言い方は俳句鑑賞の場においては凡そ相応からぬように感じるので「氏」とする)の公判が始まった。氏のパソコンの復元データの中には「散弾銃の作り方」というテキストファイルがあってここに「巨悪あり。法これを裁けず。世の捨て石となるための覚悟と信念のためにこれを記す」という文言があったという。
つまり「巨悪ありこれを裁けず」という赤野四羽氏の措辞は引用であって、その意味で山上氏の間接話法ですらあると言ってよかろう。この間接話法を俳句的強度を担保しながら成立させたのが赤野氏の手柄であるといってよい。山上氏の旧統一教会の宗教二世としての境遇には同情を禁じ得ない(それが殺人の論理を肯定はすることにはならないことも申し添えておかねばならないが)。
山上氏の実存のかかった言葉を俳句形式に持ち込み固着させんとすることは、ジャーナリズムが統一教会問題に対する反省が見えない高市早苗氏の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」という言葉を持ち上げたり、「サナ活」とやらを喧伝するのとは対極にある営みであるとはひとまず述べておきたい。そういう同時代的付置においてこそこの間接話法は意義深かろう。
とまれ俳句形式に持ち込んだことで普遍的に読まれうるものにもなるはずで(それこそ法で裁けなければ実力行使をしてよいと粗雑に読み替えれば、トランプ氏のベネズエラ侵攻肯定句にすら読み得ることもまた恐ろしいが)、山上氏の私的な言葉がその文脈が抹消されて普遍に開かれるにはまだ早過ぎるだろう(少なくとも鑑賞においては積極的に普遍化するのはあまり誠実でないように思う)。
山上氏が文字どおりの一世一代の賭けのような状況で「巨悪あり。法これを裁けず」と文語文法を選択していたことに私は関心を寄せる。データが復元されたものであるからには、山上氏はこのテキストを一度自分の手でパソコン上で抹消した訳であり、その行為をそのまま受け取れば、山上氏はこの言葉を残すつもりはなかったということになるが(とはいえデータが警察に事件後復元されることを見越していたのではないかとも思うが)、そういう、残るか残らないか分からないが、しかし紛れもなく自分の実存がかかった言葉を自分のために書きつける必要がある際に文語文法を選んだことは、私はもう少し考える必要があると思う。それは単なる表層的な恰好よさから選ばれたのか、自分自身を誇張したり鼓舞したり国家が国民を動員するような男性的な言葉としてあったのか、定型感覚の安寧のようなものがあったのか、伝統に連なり普遍化したい欲望があったのか。それは分からないにしても、同時代的な連帯に心を寄せることが出来ない人間のナイーブさは、いかにキッチュであろうとも文語が掬い取った(掬い取るしかなかった)ということを妙に痛ましく思った。口語で書けないことというものもある。
結審は二〇二六年一月二六日。検察は無期懲役を、弁護側は懲役二〇年以下を求めている。
話は変わるが、週刊俳句の新年詠では他に〈魔羅抜いて神馬はるかなる一粲〉九堂夜想、〈パエリアの大きな貝やお正月〉千野千佳、〈おとうとに姉われ淡し年賀状〉津川絵理子、〈初春の吸物を麩の一回り〉野城知里、〈繪歌留多のねむたき色をひろげたり〉常原拓、〈邂逅や冬褐色の木をあふぎ〉依光陽子、〈明けましてじねんじょほりに忌が六つ〉ちねんひなた、〈夕べより雪の二日となりにけり〉対中いずみ等を楽しく読んだ。
今年も帚はのんびりやっていきます。よろしくお願いします。
記:柳元