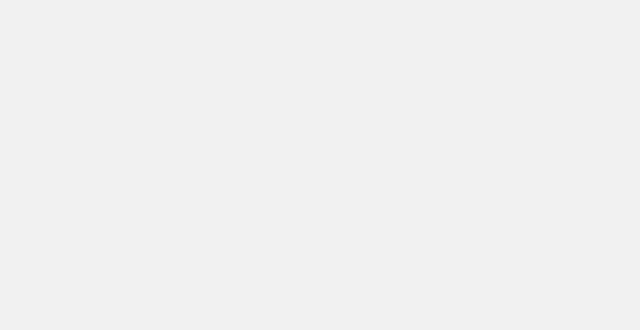所収:『ピクニック』現代短歌社、2018
生きる、生きているということに、強く理由を求められているような感覚になることがたまにある。なぜ生きるのか、なぜ今生きているのか、その原動力は何か、動機は何か、と執拗に尋ねられていると思うときがある。そして、それが言葉に出来ないと、理由もないのに生きているのかと責められているような気持ちになる。車に乗るなら免許が必要だ、と同じくらいの熱で、生きるのであれば生きるぞという強い心が必要だ、と言われているような気持ち。何らかの意味があって生きている、という考え方からそもそも、自分には馴染まないものだといつも思っている。
掲歌を読むと、それをさらっと掬ってくれるような気持ちになる。「べつにまぐれでいい」、偶然生きていて、それが偶然続いている。それ以上のことは良いんだと言ってくれている気持ちになる。「べつに」という言葉が出てくるのも、「まぐれ」以上のことを求めている人がいるから、だろう。無理はしなくていいのだと楽な気持ちにもなる。
ただ、この歌には少し気になるところがある。最後の「まぐれの君に会いたい」の部分で、何か違和感がある。おそらく、純粋に優しい気持ちから発された言葉だろうと推測できる。だから、その思い自体にどうこう言うつもりはあまりないが、もし自分がこの主体に「まぐれの君に会いたい」と言われたら、素直にありがとうとは言えない気もする。
というのも、主体が、生きていることはまぐれでいいのだと思っているということと、「君」側がまぐれで生きているかどうかは別の話ではないか。
別にまぐれで生きていていいんだという励ましは、別にまぐれでもいいけどそれ以外でも何でもいいんだよ、という励ましだと思う。だから、ここは「生きている君に会いたい」で充分じゃないのか、と思う。なぜここが「まぐれの君」に会いたいと変形されてしまうのか。今「君」側が大変な状況に居て、生きることに苦しんでいて、だから最低限「まぐれ」でも生きている君に会えたらそれだけで良い、ということだろうか。
ここが「まぐれ」になった他の理由を、短歌の創作面から邪推すると、リフレインというか、そういう技術的なところが大きいのではないか。「べつにまぐれでいい」の跨いでいる韻律や、二つの一字開きの間に「七月」を差し込むテクニックに、その気配がする。この歌にとっては、生きていることに「まぐれ」という言葉を付けられたことが何よりの勝利であり、それをさらに印象付けるために繰り返して「まぐれの君」という少し変わった表現にして表したのではないか、と私は考えている。「まぐれで君に会いたい」だと意味は変わるが「まぐれ」という言葉は自然に働くのに対し、「まぐれの君に」はやはり詩の力が働いている。個人的に「七月」という謎の季節のカットインも、夏のかっこよさをなんとなく引くためだけの道具立てなのではないかとさえ思ってしまう。
ところで、宇都宮敦の歌において、他者について語るとき、必要以上の情報は割かれない傾向があると感じている(以下引用はすべて『ピクニック』より)。
ひたすらにまるい陽だまり ひまわりの種の食べかたを教えてくれた
とうとつに君はバレリーナの友達がいないのをとても残念がった
左手でリズムをとってる君のなか僕にきけない歌がながれる
他者には他者の思考や感覚があることを分かっていて、それ以上は踏み込まない、という印象がある。例えば〈左手で〉の歌が、最後が「僕の知らない歌がながれる」であれば、踏み込み度合いは変わる。あくまでも「きけない」という事実だけでとどまっている。
新幹線から見えたネコ 新幹線からでもかわいい たいしたもんだな
ネコかわいい かわいすぎて町中の犬にテニスボールを配りたくなる
カーテンが光をはらんでゆれていて僕は何かを思い出しそう
こういう自身が思ったことをそのまま喋っているように言うところが特長である作家だが、この二つが混ざったときに、違う印象の歌が生まれている。
コインランドリーで本を読んでいる もちろん洗濯もしているよ
三月のつめたい光 つめたいね 牛乳パックにストローをさす
「もちろん洗濯もしているよ」という弁明、「つめたいね」という確認・共感は誰に対してなされているのか。自分自身とも考えられるし、書かれていないがその場にいる第三者にとも、読者に、とも考えられる。このとき、「もちろん洗濯もしている」と言わないといけないのは、「コインランドリーで本なんか読んで、まさか洗濯はしてないなんてことはないよね?」という声があったからだろう。もしくは、そういう声がありそう、と思って先回りして言っているかだろう。その声を、主体はどこから感じているのかが分からない。ずっと独り言を言っているようにも、恋人に言っているようにも、読者に語り掛けているようにも見える。このよく分からないところからの声に応じている主体、という歌の揺れ具合に魅力があると言える。
依然として、私は「まぐれの君に会いたい」には引っかかっている。他者が出てくる歌で、「まぐれの君」と言うのは、らしくないように感じる。「会いたい」という自身の感情が勝って、「ネコかわいい」くらいのテンションで「まぐれの君」が出てきたのかもしれない。
よく分からない声に応じる、という点で言えば、「べつにまぐれでいい」も、どこから来ているかは色々読みようがある。現代社会全体の雰囲気に対してか、生きづらい「君」への励ましなのか、主体自身の思想か、などなど。それによっては、「君」が単に一人を指していないようにも感じられる。もっと言えば、「君」と言って指すような人物は最初からいないかもしれない。
この歌自体が、まぐれで存在しているような、そんな気もしてくる。
記:丸田