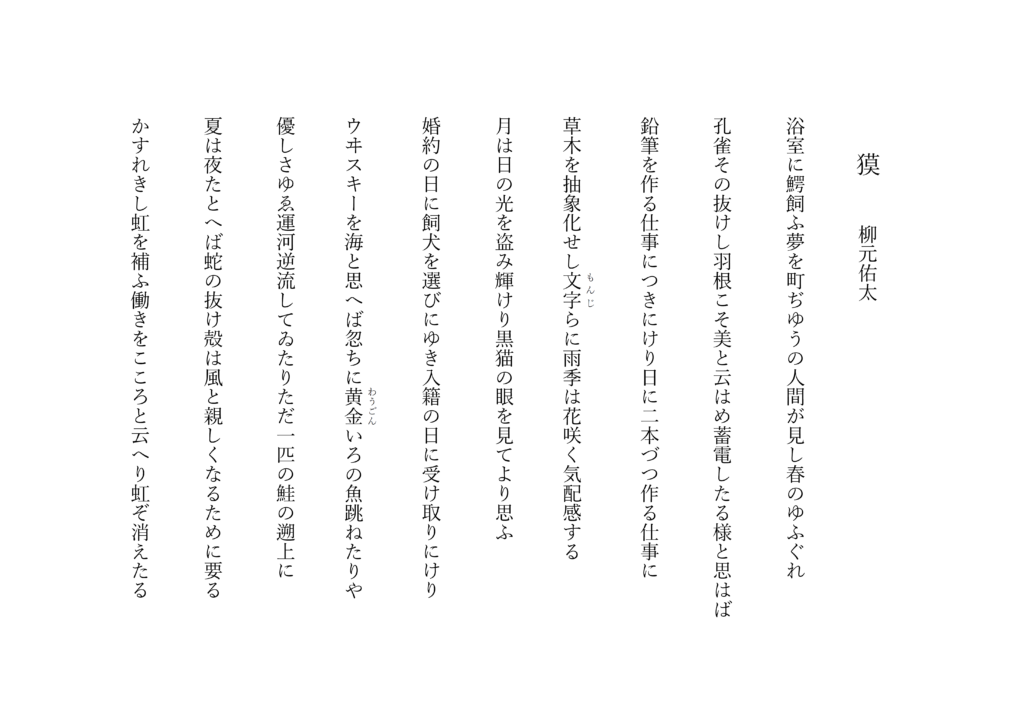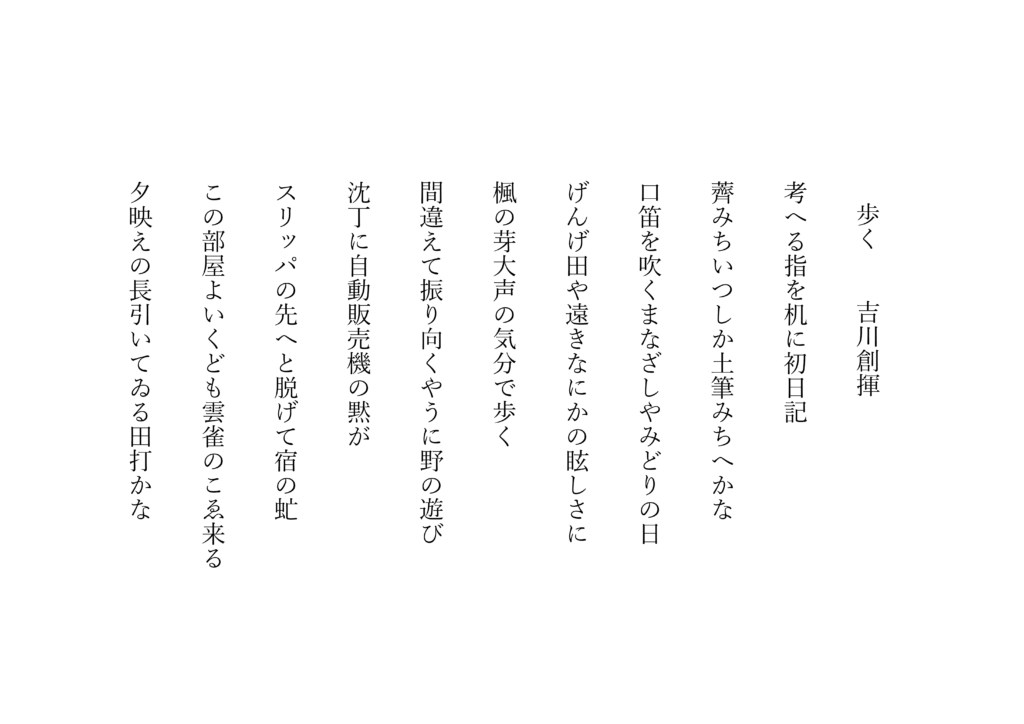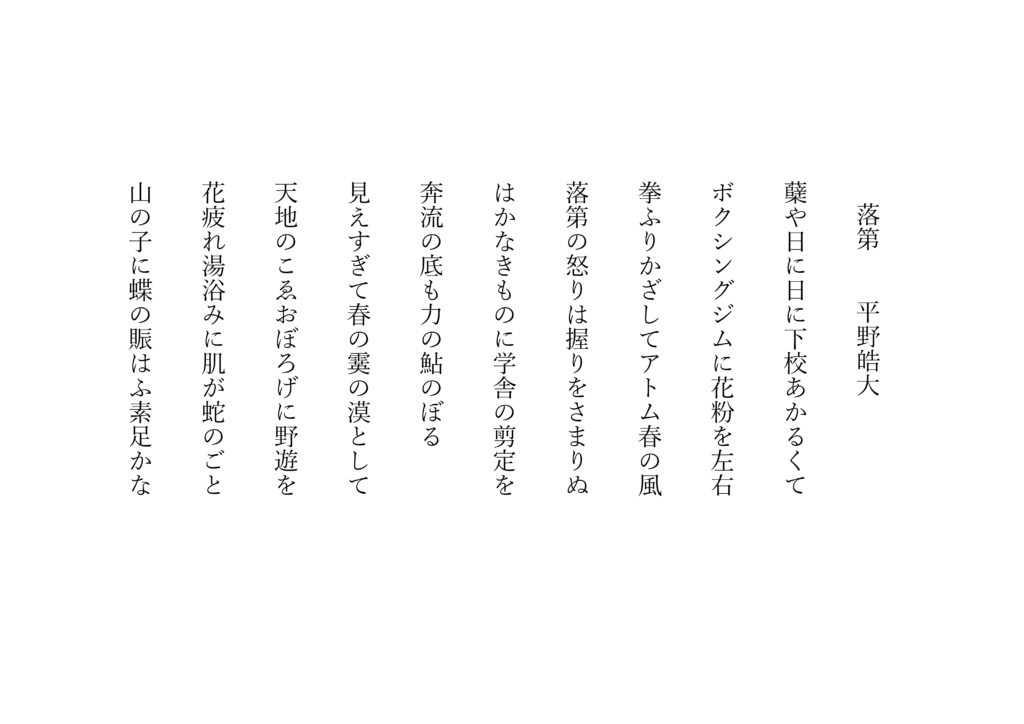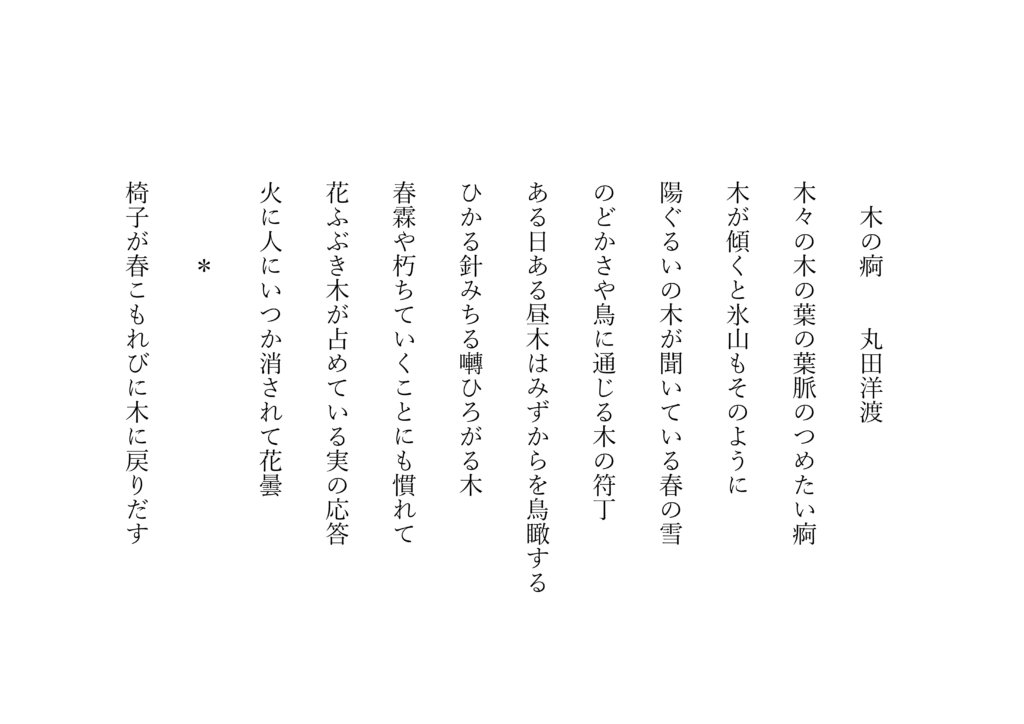所収: 『良酔』風神堂 1980年
週末、コロナ禍の上野公園に行った。美術館、博物館、動物園が軒並み休止しているにも関わらず、存外に人で溢れていてやや面食らった。訪日外国人客が上野から消えて驚くほどがらんとしているという前情報があったから訝しく思ったものの、道なりに歩いてみればたちまちに理由に思い当たる。
まだ七分咲きではあるものの、桜が開いている。つまりこれらの人々は、コロナウイルスが猛威を奮うなか、逞しくも咲きかけの花を目当てとして酒瓶片手に集まっているのである。
もちろん公園を管理するサイドもコロナウイルス対策をしている。ブルーシートを引くことを禁じ、平時のようにゆっくりとした花見は行えないようになっている。
しかし平安以来の伝統である桜樹下での酒宴、その程度の対策では妨げることが出来ない。堂々とブルシートを広げ、注意されたら場所を変えるというゲリラ花見戦法をとる人、地べたに座ることを意に介さず芝生でへべれけになっている人。
死すとも可、と言った原子公平のような強靭な意志でコロナ禍中の花見を企てた人がどれくらい居るのかは分からない。けれどもまあコロナウイルスに感染しても可、くらいには思ってはいるのだろう。
彼らを積極的に肯定するつもりはないけれど、エンタメが自粛に次ぐ自粛のなか、屋外という換気環境であることに鑑みればこれくらい許されてよいのではないかとも思う。まして支持者を集めて公金で呑んでいる訳でもあるまいし。
ワンカップ大関を啜ってみても死すとも可、という気持ちにはならなかったけれども、楽天的な気持ちの延長にふっと死が待ち構えている感覚はぼんやりと分かる。
記:柳元