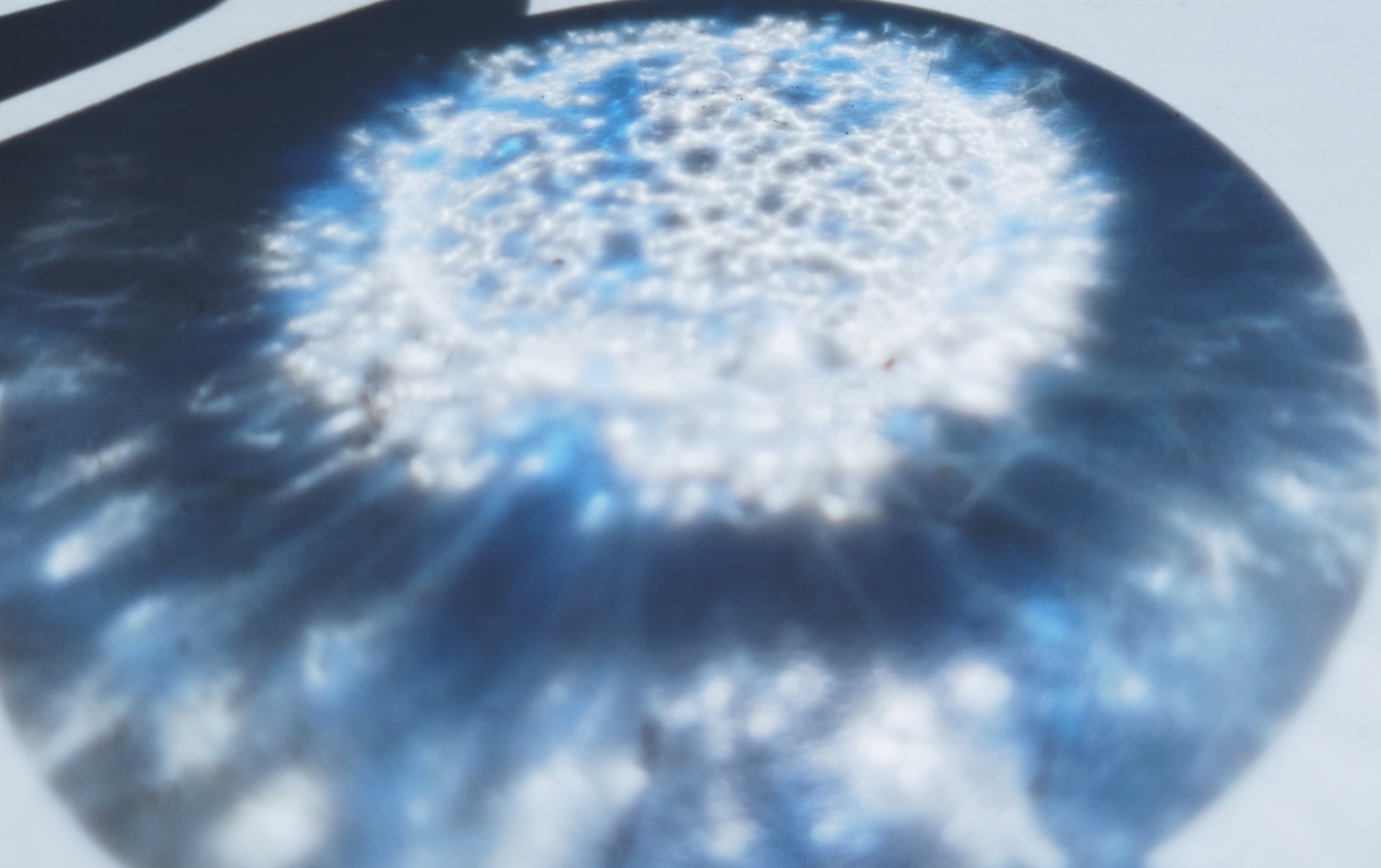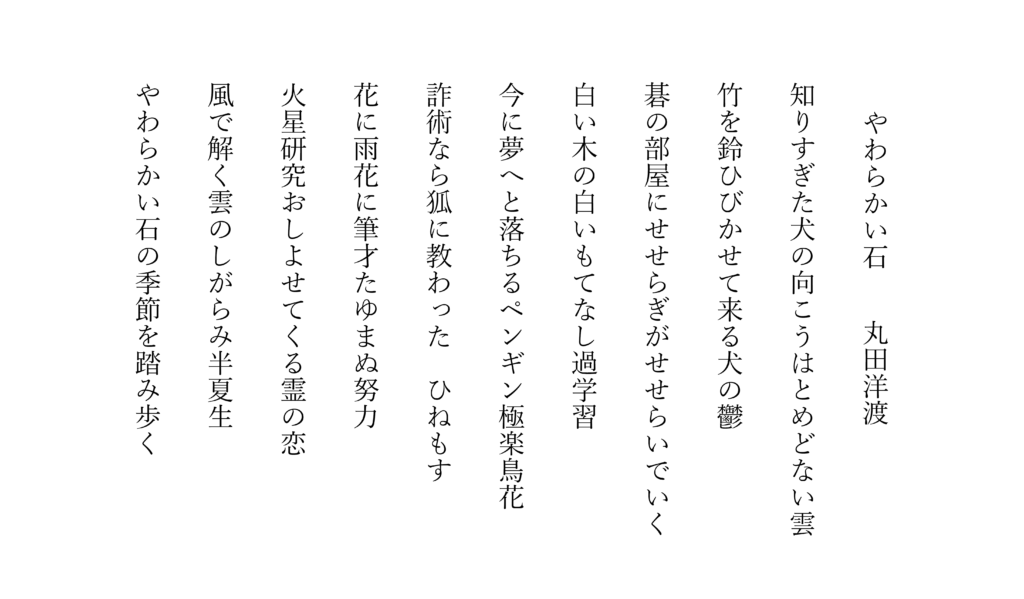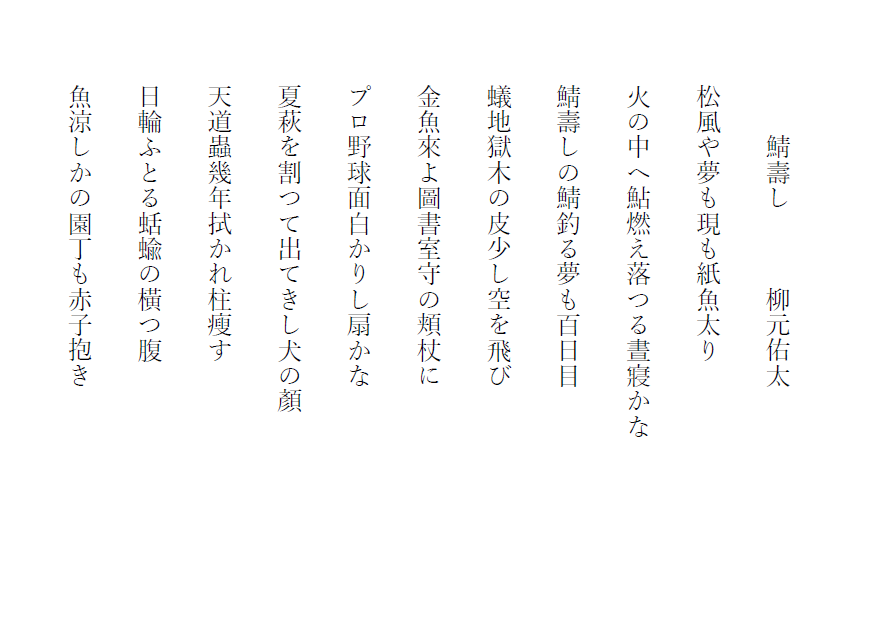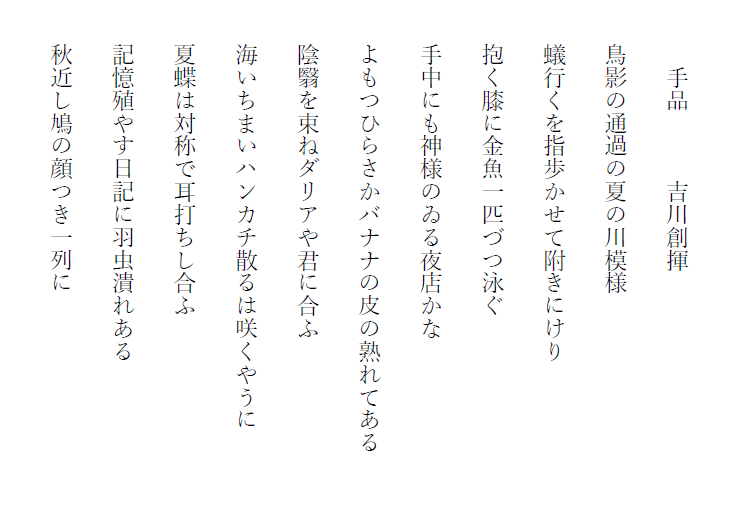所収:吉岡太朗『世界樹の素描』(書肆侃侃房、2019)
「不自由律」の章から一首。この不自由律という章名、不+自由律のように見えるが、おそらく不自由+律でもある。あっさり7首で次の章へ移ってしまうが、このタイトルは惹かれたし、もっと読んでみたいと思った。
この歌集は基本的に全編方言で記述されている。関西方面の方言。私自身も関西の方(といっても四国)出身なため流れるように読めた(まったく関西弁に対する知識? 感覚? がない人にとってはかなり読みづらいものになっているのかもしれない。そのあたり関東出身者に聞いてみたい)。
一応、「なんのを」は「なるのを」や「なっていくのを」を意味し、「待っとった」は「待っていた」を意味する。
この歌の不思議なところは、関西弁によって微妙に余韻が変わってくるところである。
「夕日ふんだり夕日けったり」が比喩なのか本当の行為なのかは分からないが、そういう遊びや空間が終わるのを主体は待っていた。ふつうに考えれば、おひらきになるのを待つということは、早く終わってほしいということで、苛立っていたり心ここにあらずであったりする。
ただ私がこの歌を読んで感じたのは真っ先に寂しさだった。その理由として大きかったのは「夕日」という寂しさを演出する材料と、「待っとった」の言い方だった。内容的には早く終わってほしいと言っている、それは分かっているが、何故か「終わってほしくなかった」みたいな感情が伝わってきた。これは単に、私自身がこの方言になじみがあって、懐かしさを覚えた(なつかしいものは簡単に寂しさを連れて来る)からなのかもしれない。
(個人的に思う)関西弁がもつ溌剌で素朴なイメージが、逆の方向に振れて、なんとなく寂しく思ってしまった。
そうすると、「ふんだり」「けったり」が「踏んだり蹴ったり」というフレーズにも見えてくる。サッカーみたいな響きなのに、心に何か悩みを抱えているような感じもする。「なんのを」「待っとった」の方言は意味だけではなく音の面でも効いている。「ふんだり」と「なんのを」の撥音便の雰囲気、「けったり」「待っとった」の促音の飛ぶ感じが共通している。
関西弁といえば漫才のようなものを想起する人も多いと思うが、関西弁で話のスピード感が生まれるのはこういう撥音や促音でリズムが出来てくるからなのかもしれないと短歌とは関係ないところで思った。
私は、見た目が完全に明るいのに、主体の言い方から察すると、かなり寂しい歌なのではないかと思ったが、別に寂しさに引っ張られて読む必要もない。
冷静に考えて、「夕日ふんだり夕日けったりする」とはどういうことなのか分からない。夕日の下、河原でサッカーをしている、のような意訳を頭の中でしていたが、夕日をサッカーボールとして踏んだり蹴ったりしているのかもしれない。そうなると、そりゃ早く「おひらき」になってほしいわな、とも思う。そんな恐怖体験もなかなかない。
比喩的な要素が少し混ざっていて、河原でサッカーをしている、そのサッカーに夕日が時折重なって、夕日を蹴っているように見える、位のことだろうと考えるの自然である。ただこの場合気になるのは、じゃあなんで「おひらきになんのを待っとった」のか。そんな眩しい子どもたちの(子どもたちかどうかは決まってはいないが)風景にいて、なぜ帰りたがるのか。自分も混ざりたいとか、終わらんとってほしいとか、そういう願望の方向ではない。
ふつうに読んだとしても、やっぱり主体には寂しくなる事情があるのでは……と私は思ってしまう。
もしくは、他人が愉しんでいるのを見たら/楽しんでいるグループに自分が参加させられていたら、早く終わればいいのに、それの何が楽しいんだと思うような斜に構える性格があるのかもしれない。しかしそれにしては「夕日ふんだり夕日けったりする河原にて」は好意的な語り方だとは思う。
なんとなく見えるようでなんとなく見えない、明るそうで寂しそうな、魅力的な一首だった。
〇
ところで、この歌集を読んでいて個人的に面白かったのは、方言がいきいきと使われている(方言が主役)ものもあれば、方言が文語みたいに使われている(方言はサブ)ものもあるところだった。
挙げた踏んだり蹴ったりの歌は、中間くらいだろうか。
例えば巻頭の一首は〈月光がこんなにふかいところまで泳ぎにきとる霜月の森〉。「きとる」(来ている/来ていた/来た)が方言の部分。これはかなり「短歌」という感じがする。文語の使用と同じで、とりあえず文語で統一しとくかみたいな、「調整」感がある。私がふつうに関西弁風に話すとしたら、「月光がこんなにふかいところまで」と律儀には言わない。「こんなに」の「に」が特に(ただこれも関西の地域差があるのかもしれない)。あと「月光が」とも言わないだろうと思う。
方言というと喋っているように思ってしまうが、喋ってはいない、書いているということだろう。もしくは、心のなかで喋っている。だからスムーズに喋っているようで急に短歌みたいな詠い方をする感じがして妙な感覚になることがある。
〈火と睦みあう冬空をひたすらに見る みるだけの生きもんとして〉これとかもそうで、「生きもの」としていても普通に読める。もちろん、「生きもん」と関西弁であることによる効果もあり、それを加味して読むことも出来る(そうするのがマナー?)が、これは全首方言にしておこうという調整が見える。それが悪いとは思わないが、「短歌」の引力が方言の喋りを不思議な方向へ変化させているような気がして、私はかなり面白く感じた。
〈ずっとおっても一日ずつしか会えんくてケージに紺の布かけわたす〉これは上の句は方言のスピード感が生き生きとしている。「一日」に何もルビは振られていないが、自然に「いちんち」と読んでしまう。読ませるスピードと迫力がある。しかし(しかし?)、下の句になって急に短歌になる。「ケージに紺の/布かけわたす」と一拍空いて見える。それは「会えんくて」から急に切れて景色の物の話をし出したのもあり、「かけわたす」という短歌っぽい動詞の選択をしていることもあり、「紺の布(を)かけわたす」の77のリズム合わせが見えていることもある。
方言で完全に喋っているように見えるもの(「短歌」からは離れている)、方言で喋りつつしっかり短歌であるもの、短歌のなかで方言に変換できるものを方言にしただけのもの、などのグラデーションで、方言アンソロジーみたいなものがいつか組まれたら面白いのになと勝手に思った。
記:丸田