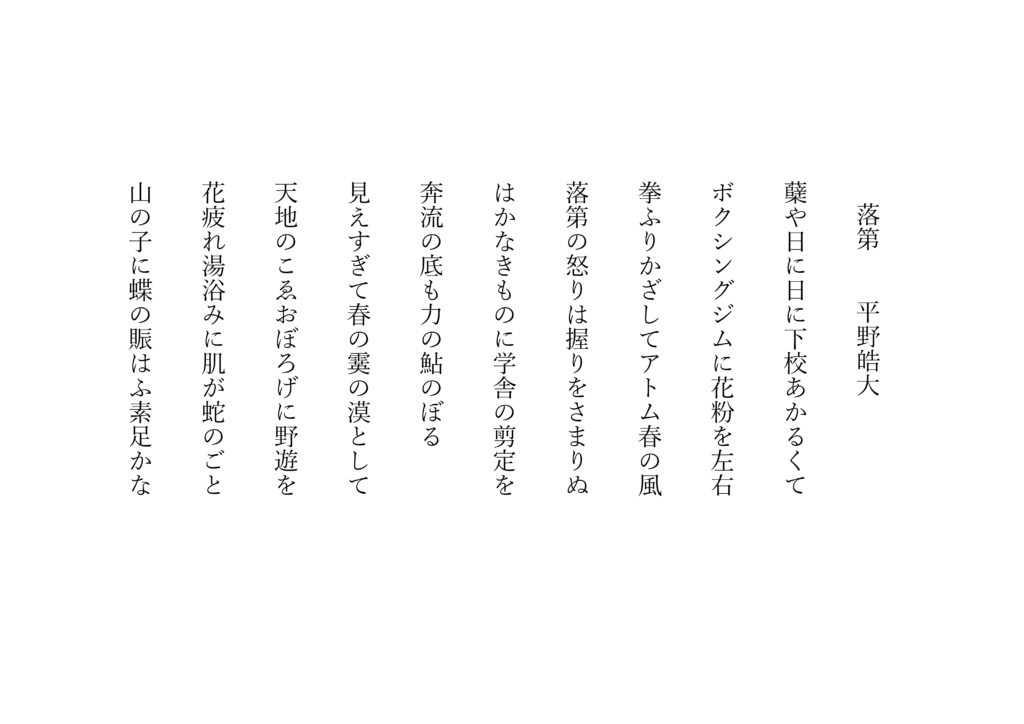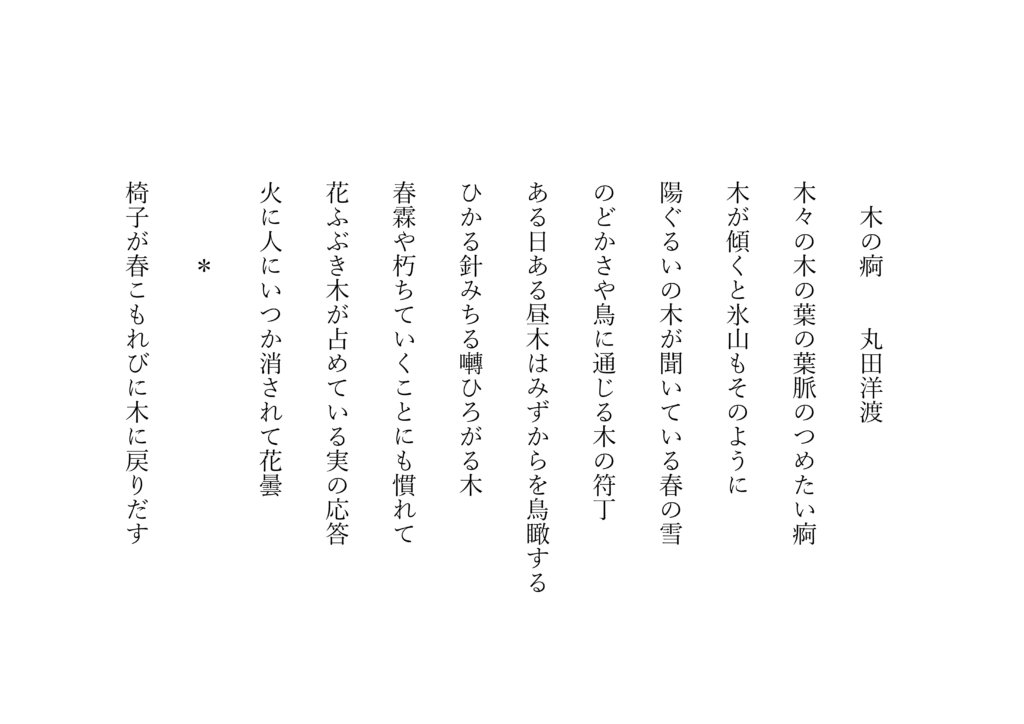所収:『hibi』港の人 2018
不思議(または不気味)な後味の川柳。作りは一見簡単であるし一句もさらりと読めてしまうが、非常に奇妙である。
まず、「藤という燃え方」。桜という植物、牛という動物、冷奴という食べ物。この「という」が使われるときには、前者が要素、後者がそのカテゴリーのようになる。ここで、藤という〇〇を考えた時、植物、美しさ、紫、などが類推できる。藤にある共通点から考えていく。ここで、想定外の「燃え方」が来る。藤は燃えていたんだ、少なくとも主体は(主体のいる世界では)、藤を燃え方の一つと捉えているんだ、と分かる。藤が急激に神聖な、得体のしれないもののように感じられる。
次に、「が残されている」。「を残している」とは違う。ただ残されている限り。自分とは少し遠い位置に藤が燃え方として残されている。果たしてそれが主体にとって希望なのか絶望なのかが分からない。例えば「自殺という死に方が残されている」という文は、死にたいんだったら、希望のように聞こえる。この句で、藤は、その燃え方は、どのように映っているのか。
それぞれの語の持っている不思議さ、哀しさ、儚さが、奇妙な構造で支えられて、独特の響きあいを見せている。一体、藤が燃え方として残されていることを主体はどう受け止めているのか、読者はどう受け取ったらよいのかが分からないまま、ただその景色・事実だけが屹然と、かつ漠然と心に残る。読者としてこの句に取り残されてしまう自分の感覚が、この句の中の藤の在り方と共鳴し合うようで、奇妙な心地よさがある。
記:丸田