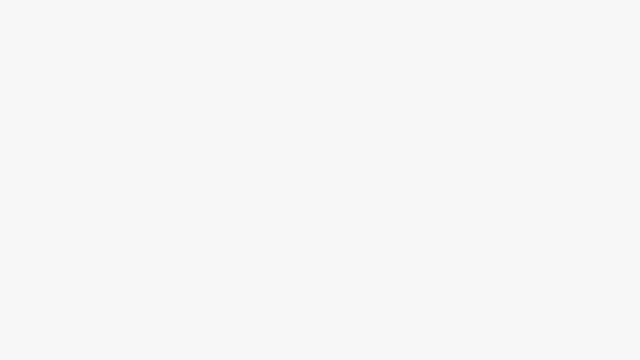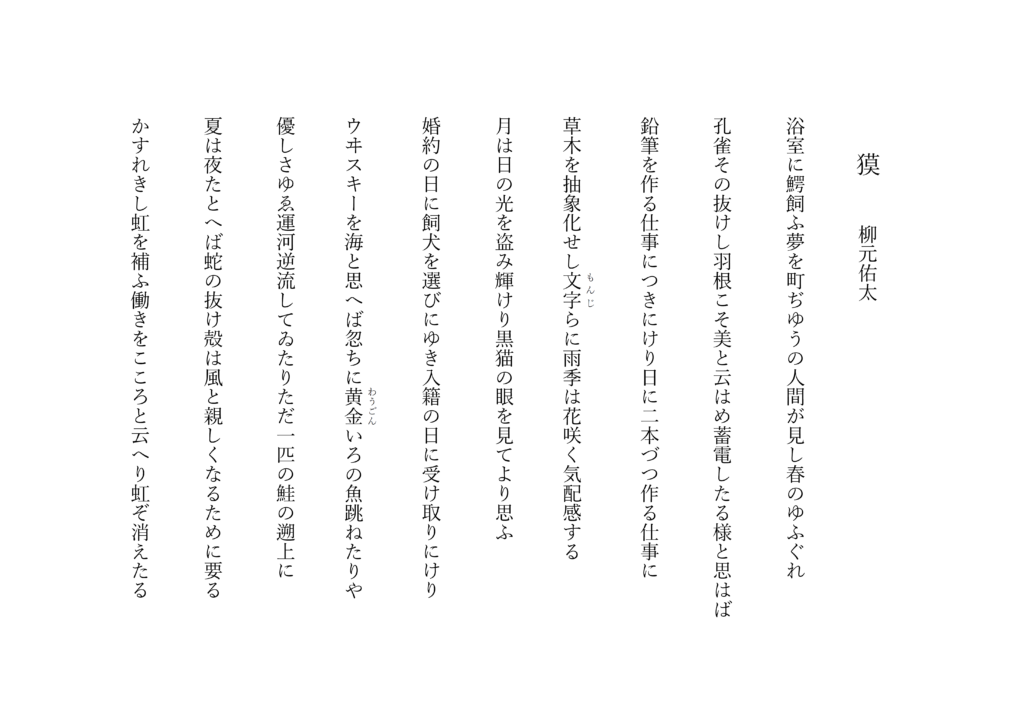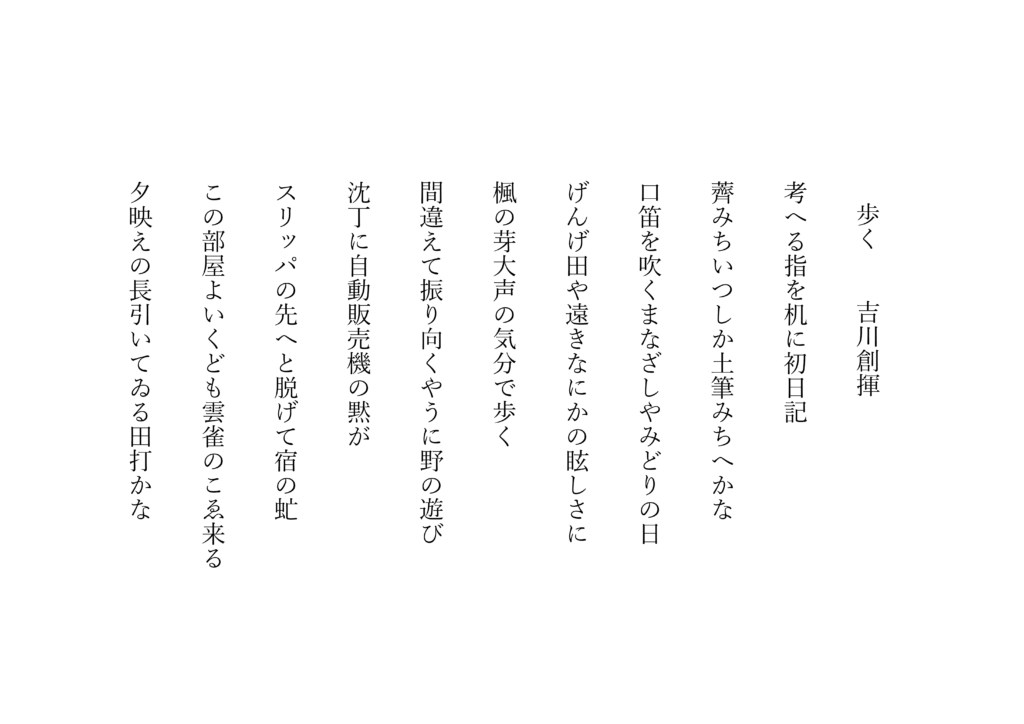所収:『山河』 東京美術 1976
スーパースターと呼ばれる人物がどの分野にも、存在する。
生まれ持った資質に寄りかかるのではなく、度しがたいほど精力的に、もしくは無邪気に見えるほど熱心に打ちこみ、誰よりも高い志を抱いている。その姿を常人は仰ぐことしか出来そうにない。巨星の熱に肌を焼かれながら、尊敬するか、滑稽に思うか。自らも同じ高みに登ろうとして、無理だと悟るか。そこで諦めるか、自分に出来ることを頑張るか。
溢れるバイタリティは自らを燃やして尽きる。燦爛とかがやいていたはずの巨星は忽然といなくなることもあり、去り際まで燃えて、ふっと消える。巨星が照らしていた範囲を知り、頭上の空虚さと、巷を覆う暗闇の広さに気がつく。それでも巨星は昇りつづける。寂しさを導く木枯らしに燃えるようにして、巨星は心の内に輝く。一人の心だけではなく、人びとの記憶の中に、巨星なら輝く。
あまり鑑賞に関係ないが、吉行淳之介に『スーパースター』という題名の短編がある。同年輩の三島由紀夫について、吉行がどのような感情を持っていたか、回想が主になり話が進んでいく。 三島もまた数少ない巨星の一人だった。
記 平野