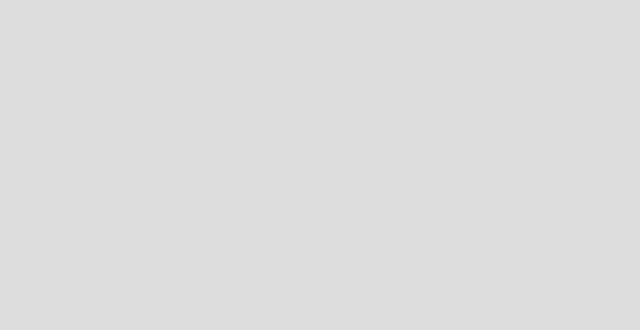所収:『行け広野へと』第三版、本阿弥書店、2018
ジャンルは何にせよ、創作をしていると色々な他の情報がそのネタのように見えてくる。お笑い番組を見ていても、漫才やコントの構成、展開、話術、テンポなどなど、自分の創作に活かせるんじゃないか? という目で見てしまう。創作をするということは、世界全般に対して、新しいアンテナを張るようなものであると日々思う。
「調律師の感性」なんか、メモせずにはいられないように感じられる。詩的なものの電波を受信するアンテナがあれば、真っ先に拾うものだろうと思う。ピアノの弦と鍵盤、振動、音、調整……。天性の音感が無いとやってられなさそうなイメージがある。慎重で繊細で、感覚を研ぎ澄ませてやる作業。
詩にするには格好の材料だろう。そしてそれをうきうきとメモした主体は、まさかの「雪原」というこれまた詩的な土地に置き忘れてしまう。
このときの、「置いてきてしまったよ」という言い方はわざとだろうと思うが、若干の軽さがある。置いてきてしまったことを後悔するのではなくて、むしろ自分から望んで置いてきたくらいに、雪原に置き忘れたことをなんだか詩的になってしまったエピソードとして面白がっている感がある。
「置いて」という動詞の選び方も、忘れたとか失くしたよりも、雪の上にそっとひらひらと置いたようなイメージが喚起される。
調律師の「感性」という言い方にもやや軽さがある。これは個人的に私だけが感じている印象かもしれないが、ここが作業過程であったり、洗練された技術であったりしたらすんなり納得する(メモも子細に記せる)が、「感性」というのは、なんとなく雑な感じがする。なんだかステキと思ってメモになんとなく書く。こちらが詩にしやすいものを勝手に引き抜いて勝手に作品にしている印象は拭えない。感性をなんとなくメモしてきたから、なんとなく雪原に置いてきてしまえるし、「置いてきてしまったよ」と言えるのだろう、と思う。例えばこれが「詩人の感性」であっても同じであって、もちろん感性が仕事の大事な部分にはなっているものの、その感性を最大限活かすための技術や努力の部分を外部の人はメモするんじゃないだろうか、と思ってしまう。
そういう受けとり方をしたときに、この歌はものすごくナメている歌だと感じられる。「調律師」という素敵っぽい職業、感性をメモするという感性豊かそうな行為、「雪原」という詩語感たっぷりの舞台設定、「置いてきてしまったよ」というとぼけ方。
一方で、これが本当に奇跡的に成り立った歌だとして読むことも出来る。
本当に調律師の仕事について触れて、その感性がいかに魅力的で重要かを知って尊敬して茫然とメモしておいたものの、それが帰るときになって落としてきたと気づく、通ってきた道は雪原であったから、雪原に落ちたんだろう……。
そんなことがあるか? と思うものの、もし本当にすごい確率でそんなことが起きたのだとしたら、「置いてきてしまったよ」と言ってしまいたくなる気持ちも分かる。ただ忘れただけだったのに、その奇蹟に主体自身も驚いて、「置いてきてしまったよ」と乗っかりたくなる感覚。
私としてはこの二つの読みはちょうど半々くらいで存在している。韻律が定型に添っていないことも、この読みによって効果が分かれて、前者の方だと調律師の感性というセンスある材料に合わせてテクニカルな韻律にしたと取れ、後者の方だと本当に奇蹟だったから動揺して起こったことを矢継ぎ早に話している、と取ることが出来る。
美しさを手ごろに詠もうとするとその手つきが透けて見えるのかもしれないとも思わされ、一方で本当の美しさというものは嘘っぽく聞こえるものなのかもしれないとも思わされる。非常に危ういところで揺れ続けているこの歌の像に、気になり続けている。
主体はきっと、メモを置いてきてしまったことによって、「置いてきてしまった」という記憶が加算されて、より色濃く覚えていることになるだろう。私は、そういう意味で、服部真里子のこの歌を置いていこうと思っている。
記:丸田