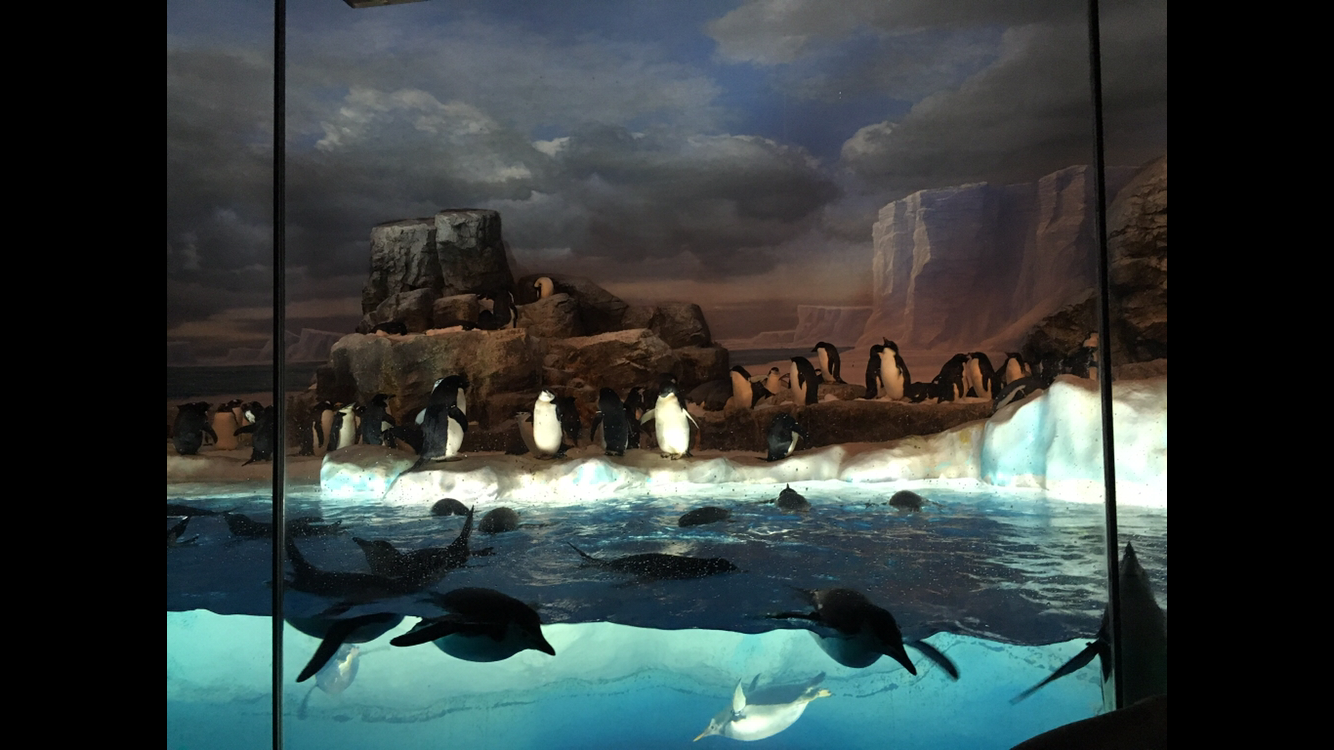所収:『感謝』ふらんす堂 2009
この句が滑稽というか、くすりと笑えるようなおかしみに転じるのは、港区が何となく「おハイソ」で「成金」ぽい感じがするからだろう。完全に偏見なので港区にお住まいの方には先に謝しておくが、ぼくがこう思ってしまうのには理由があって、というのもぼくの東京の知識は漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(通称:こち亀)によるのである。
両津勘吉(主人公)が本田という後輩の新居探しを手伝うのだが、その本田が「港区に住みたい」「ベランダから東京タワーが見える場所がよい」とゴネにゴネて、両津勘吉を困らせるのである。両津勘吉が事故物件や犬小屋を紹介する、というオチだったと思う。これを読んで以来、港区というのはミーハーが住む場所なのだという思いがあって、岸本尚毅の句にもそういうおかしみを見出してしまう。
そういえば「港区女子」という言葉もあるけれど(ご存じない方はググってください)、でも岸本の句から見える態度は、港区に集まる人を小馬鹿にするような視線ではないのがよいな、と思う。
港区の東側は東京湾に面しており、考えてみればレインボーブリッジも港区だから、何となく秋の風と言われたときそれは潮風のような感じがする。所在なさげに散歩しているときにふいに磯の匂いと出会って、ふと海のありかに思いを馳せるような、そういった良さがこの地名には初めから組み込まれている。「港」句、なのだから。大変よろしき地名である。
記:柳元