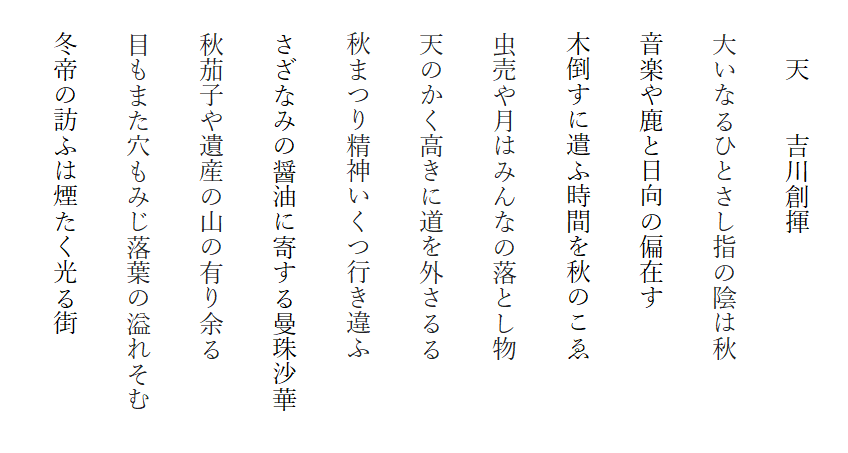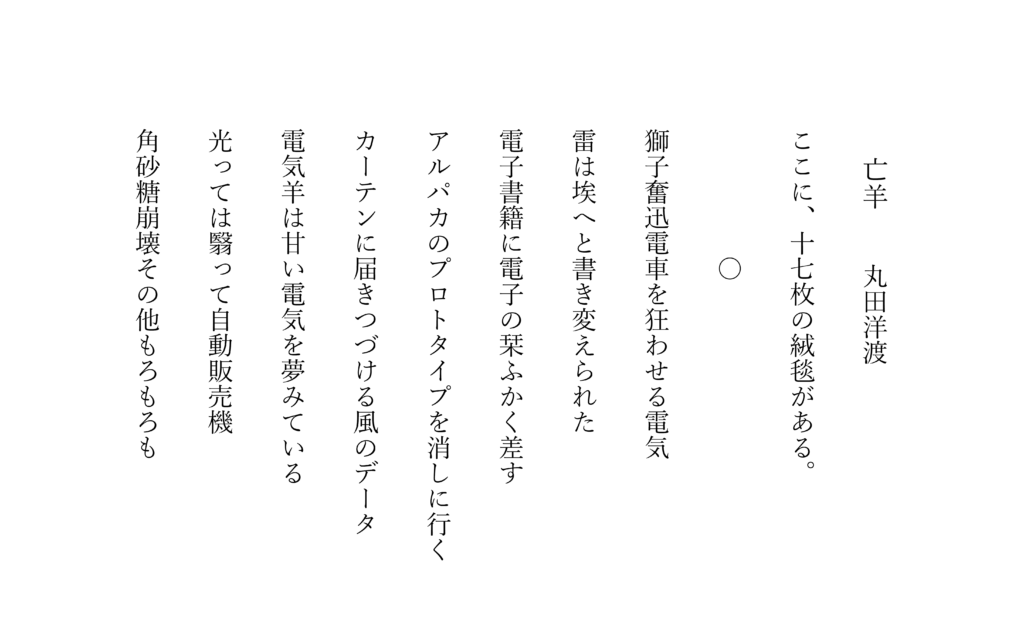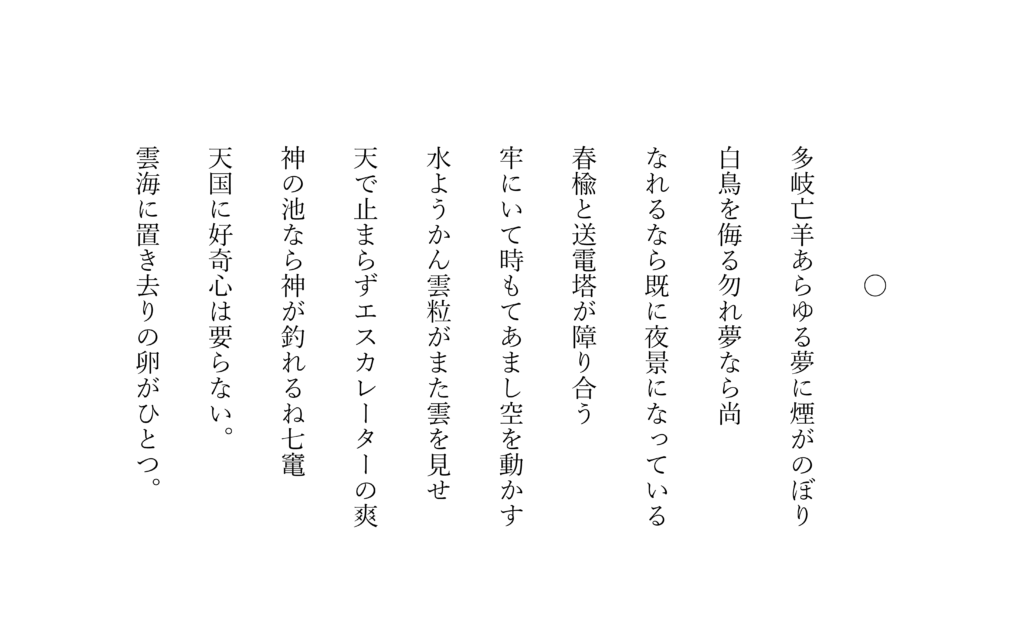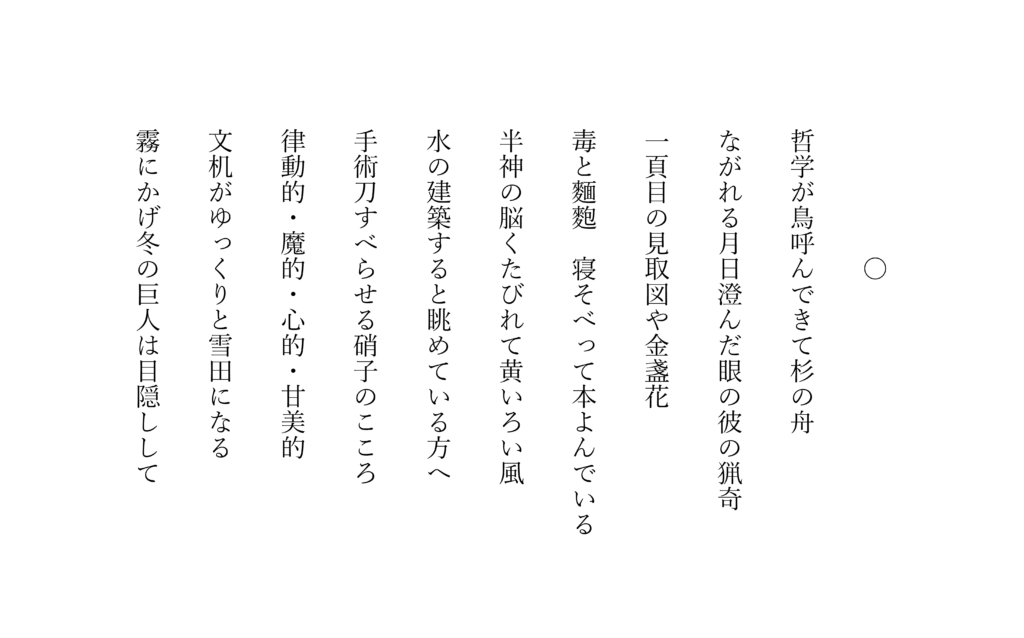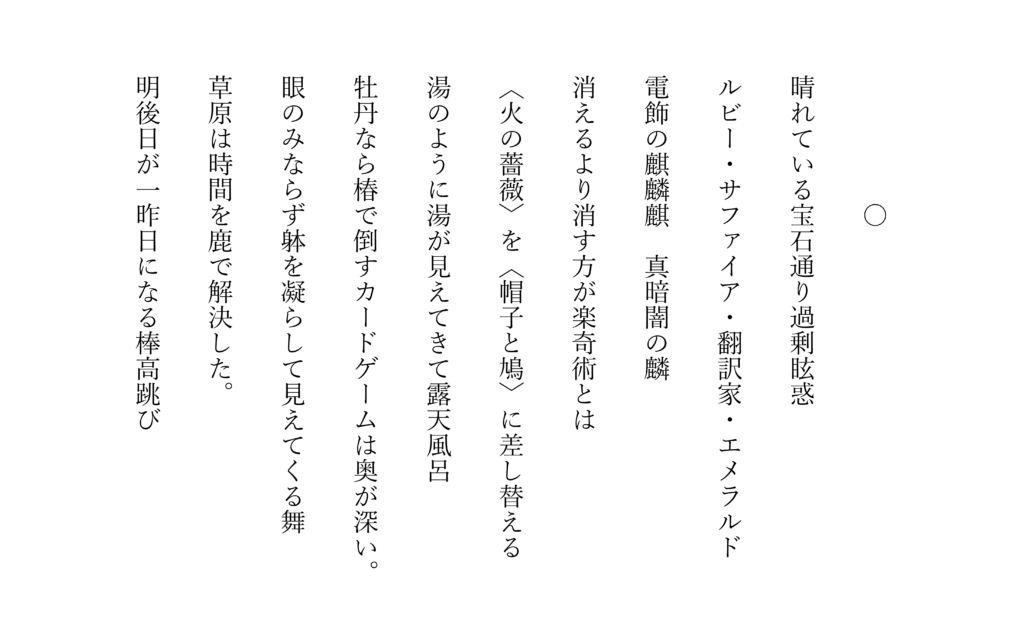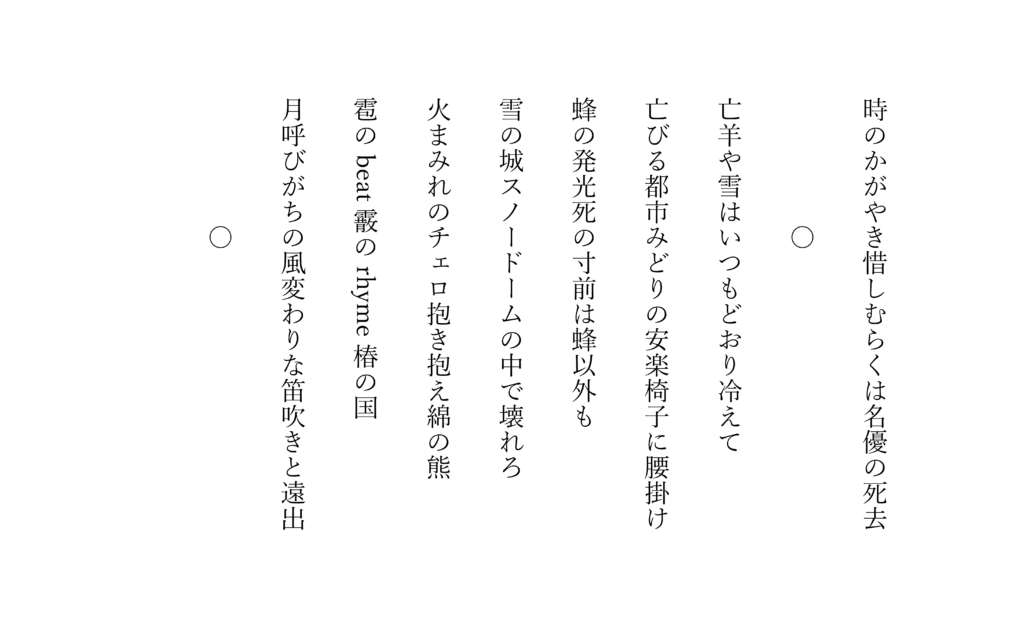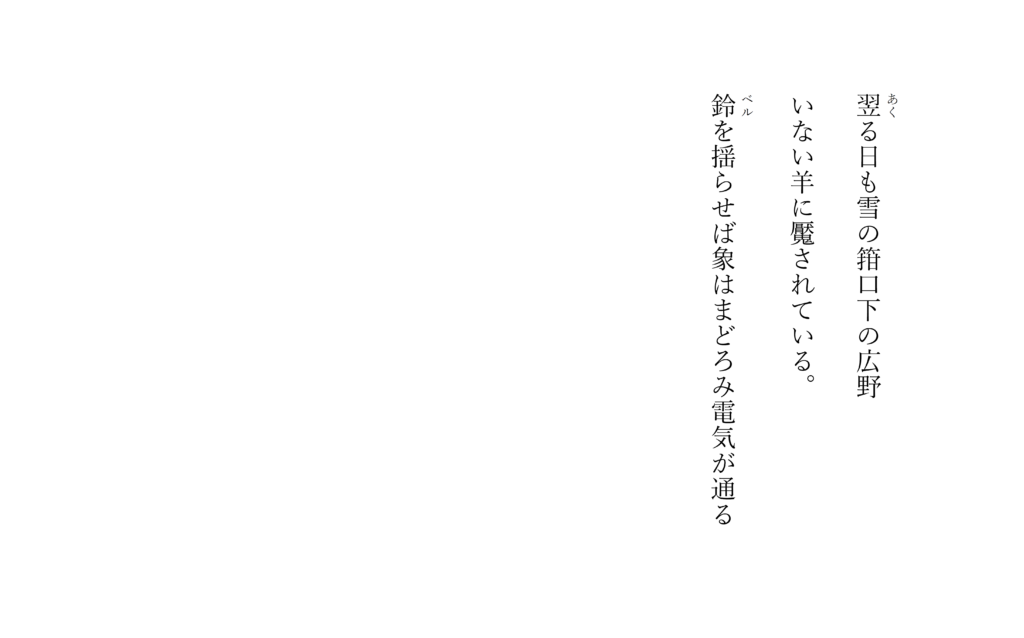所収:「汗の果実」(邑書林・2019)
瀬戸内寂聴氏の訃報に接するにあたって掲句が思い起こされたから、掲句について何がしかを書き留めたくなった。寂聴氏の命日は11月9日、季でいえば初冬であるから季語「空高し」でてふこ氏の秋の掲句を思い起こすのはそぐわないのかもしれない。とはいえ、初冬の青空もまた抜けるような高さを抱え持つものであるし、掲句が自然と思われのだという心の働きを尊重したのだと思って、諸氏にはご海容を乞いたいところである。
さて、〈生前〉という時空間は、死者にのみ許される〈場=トポス〉であって、弔辞の読まれる場面というのは、参列者のこころのうちに、おのずと死者のその〈生前〉の在りようが、〈場=トポス〉として、思い浮かべられているはずである。場合によっては、その人に愛憎や嫉妬の入り混じった感慨を抱くものもあれば、あるいは淡い付き合いながらに何故か葬に参列することになったから、何かこう、こころもちもそれらしくしなければならないと苦労している人間もあるだろう。おそらく人が見送られるときというのは、〈生前〉にどんなに善行を積んだ人間でもそんなものであって、間違いなく、想われながら見送られはするのだけれど、どこか参列者たちの気分の中には、そぞろな気分が、濃淡のありながらも漂っていて、それが非人称的に混ぜ合わさって充満するから、葬というものは、あの、得も言われぬようなさみしさがあるのではないかしらん。
そんなとき、弔辞が空の高さに触れるのであるから、何か膝を打つような気がしないか。その人の〈生前〉の人柄を「空の高さ」が見せてくれるということはもちろんあるのだろうが、というよりもむしろ、何か普遍的に、葬というものが、死者の〈生前〉という〈場=トポス〉を思うことを強いるときの独特の、そぞろな感覚というものに繋がっている気がするのである。参列者の注意散漫とか、そういう咎められる性質のそぞろさではない。秋の澄んだ大気の、薄く濃い青空のことに弔辞が触れるとき、その弔辞に導かれるように、参列者の皆のこころが、葬の場を抜け出して、空を一瞬あおぐような、そういう共同幻想的な体験……。
松本てふこ氏は、昭和56年生まれ。平成12年、早稲田大学入学後に俳句研究会で俳句を始める。平成16年「童子」入会、以降辻桃子に師事。平成23年『俳コレ』に筑紫磐井選による百句入集。平成30年、第五回芝不器男俳句新人賞中村和弘奨励賞受賞。俳句結社「童子」同人。最近はゲームさんぽの動画にも出演されている。第一句集『汗の果実』(邑書林)の購入方法はこちら(購入できる書店などをてふこ氏が紹介してくださっています)。また、個人のブログにおいて数本評論が公開されており、noteから記事を移行中とのこと。
記:柳元