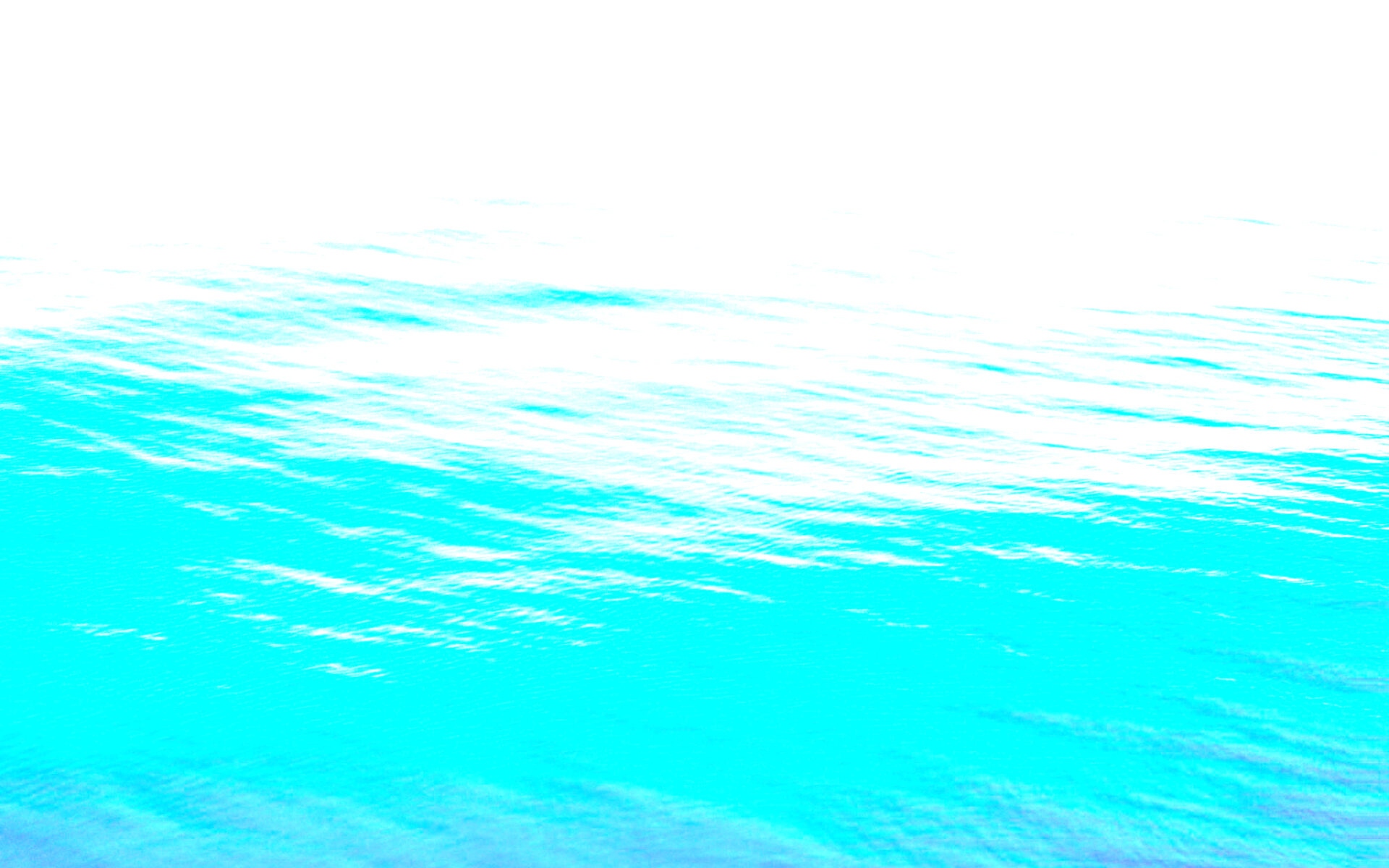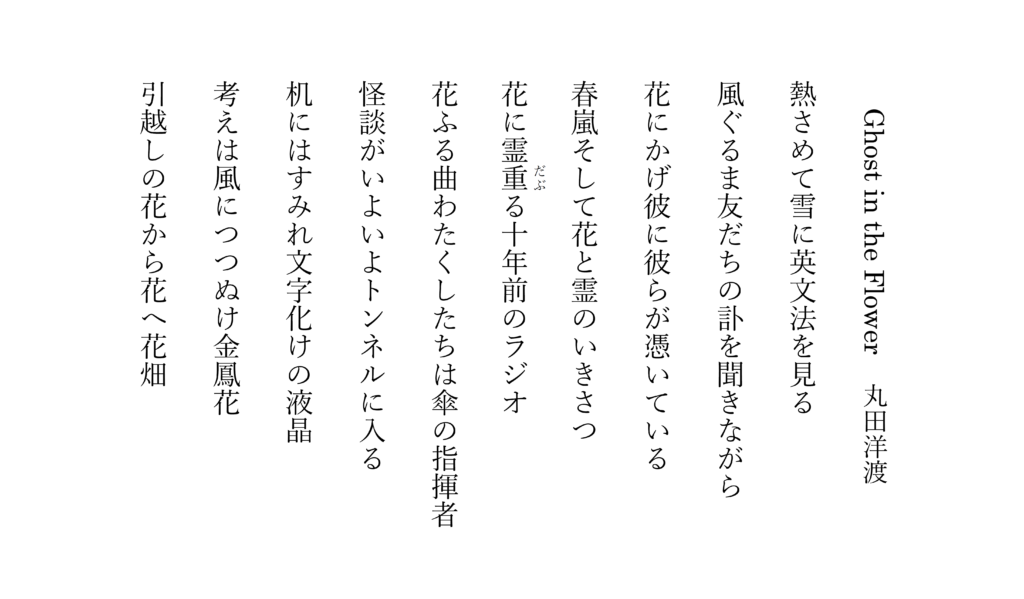柳元佑太
『葡萄木立』(白玉書房、1963)は、葛原妙子の第4歌集である。第1歌集『橙黄』(女人短歌会、昭和25年)、第2歌集『飛行』(白玉書房、昭和29年)第3歌集『原牛』(白玉書房、昭和34年)に次ぐものであるのだけれども、『縄文』(未刊歌集、『葛原妙子歌集』(三一書房、昭和49年)所収)、それから『薔薇窓』(白玉書房、昭和53年)がこれよりも制作時期的に前に当たるので、第6歌集と見做すのが一般的なようである。とはいえ、ぼくとしては世に問われた順を序数とすべきではないかと思うのだが(なぜなら塚本邦雄のように未刊歌集を後出しで何冊も出されてはたまらないからだ)、異議申し立てをするほど立腹していて困難を感じているわけではない。
さて葛原妙子(1907―1985)は東京の本郷の生まれである。塚本邦雄をして「幻視の女王」と云わしめた超越的な(つまり経験的なリアリズムの批評語彙だと語り損ねるような)歌風で知られる、戦後を代表する歌人である。塚本も指摘しているけれども、彼女が太田水穂の「潮音」に1939年に参加していたことは、多くの作家に於いて師系というものが本質的にはほとんど何も語り得ないように、葛原の場合もあまり意味をもたないだろう。
葛原の作品を一読すれば何の無理もなく飲み込めると思うけれども、葛原の歌風というのは徹底的に葛原自身の中で醸成された短歌観の中に根差す具象空間と象徴空間との暗喩を介した一度きりのものである。先行世代の文体を安易に所与のものとすることに因る薄っぺらな写実作品ではない。葛原の身体性があり肉体があり、そこから屹立するものである以上、師系というものが作家の中で安易に幅を利かすことはあり得ない(いったい、その格闘無しに誰が作家たることなんて出来るのだろうか?)。
ぼくが葛原を読んでいて感嘆するのはそういう意味で作家であると感じられるからである。無論短詩という形式を選ぶ以上ある種の作品間での影響関係、時代への隷従からは逃れられないのであろうけれども、良品製造のコードと戯れるだけのおままごととは全く異なった、自分の言語が築くデーモニッシュな世界の強度をいかに練り上げるかという格闘があるように感じる。
そういう意味では『葡萄木立』所収の
なにの輪ぞわれに近づき広がりてまた目の前に閉ざしゆきたり(「魚・魚」より)
こどもようしろをみるなおそろしき雪の吹溜【ふきだまり】蔵王は冷えてゐる(「北の霊」より)
美しき把手ひとつつけよ扉にしづか夜死者のため生者のため(「爪」より)
黒いこども暗い潮に跳ね廻る しかも跳ねゐる音のきこえず(「吃音」より)
光源の真下に毛長き犬あそぶときふと犬のうしなはれたり(「垂毛」より)
椅子にして老いし外科医はまどろみぬ新しき血痕をゆめみむため(「風」より)
わが肺のネガフィルムを透かしみよ一本の黒き柿の木立ちたり(「片手」より)
ふとおもへば性なき胎児胎内にすずしきまなこみひらきにけり(「めざめをりき」より)
くらき壁に鉄塔かすかにあらはれ鉄塔はあらしに呻吟せり(「秋の人」より)
などはさすがに葛原妙子と思わせる凄みは十二分に感じさせるけれども(実際好きな歌もあるけれど)、いかんせん作り物でしかないだろう。この歌に異界はない。異界を引き寄せるコードを保持した語彙と書きぶりによって作られた、いわば異界のテーマパークなのであって、夕暮れに遊園地がその門を閉じれば、読者は異界を摂取し終えた疲労に心地よく浸りながら、親子友人と楽しく語らいながら立ち去ることが出来る。
というのも、存在しないものを存在させたり、存在するものが存在しなかったりするのは歌の世界においてさして困難ではない。であるから、謎の輪に取り巻かれたり、死者生者のためのノブが用意されたり、不気味な子供がいたり、犬が失われたり、不気味な医者がいたり、肺に柿の木があったり、胎児が目を見開いたり、壁に鉄塔があらわれても、それはその歌そのものが怖いのではなくて、その歌が引き寄せる既成の観念が恐ろしいのである。それを歌の手柄といって誉めそやすことには、ぼくには躊躇われる。
歌が異界に扉を繋いだように見えてもその先にあるのはようするにお化け屋敷なのであって、観客を歓待するために造られた富士急ハイランドの戦慄迷宮と大差ないのだ(しかし臆病なぼくにとっては富士急ハイランドの戦慄迷宮が充分恐ろしいように、これらの葛原の歌もそういう意味では十分に恐ろしい。怪談には「テーマパークだと思ったら本当の異界だった」というパターンもあるのだし)。
しかしながら、例えば以下のような歌こそは、本当の異界であろうとぼくは思う。どうだろうか。
厨のくらがりにたれか動きゐて鋭きフォークをしばしば落せり(「爪」より)
厨のくらがりに誰かがいる気配を感知する。繰り返し、繰り返し、金属が床に落ちる音がする。しかし作中主体はなぜかその音をなすものがフォークであることを知っていて、あろうことかそのフォークの鋭さをまでも知っているのである。書きぶりからして既知だからということではなくて直感として知ってしまっているのである。この感覚の神経症的な鋭敏、暗がりの中で繰り返し、繰り返し行われる不気味なフォークの落下。しかしギリギリのところで現に踏みとどまるような無作為さと偶然性を、アリバイということでなしにたっぷりと抱え込んでいる(だからほんとうに怖い)。ここに異界のコードは無いが、そういう意味ではこここそが異界である。つまり、経験的な世界を叙述の仕方をもっていつの間にか異界に変えるということこそがここで行われていることなのだ。
白き午後白き階段かかりゐて人のぼること稀なる時間(「ひとり」より)
あるいはこの歌ならどうだろう。「白き」という形容によっていくぶん抽象化されているといえ、全きうつつの階段でしかないはずであるのに、なぜこんなにも異界めくのか。ここには白昼の異界がある。叙述をもってして経験的な世界を異界に変じる歌にこそ、ぼくは『葡萄木立』最大の魅力を感じた。
他にも好きだった歌を記しておく。
あまたなる弧線入り混り夕光【ゆふかげ】のさかなは水槽の隈にあつまりき(「魚・魚」より)
白鳥は水上の唖者わがかつて白鳥の声を聴きしことなし(「片手」より)
いうびんを受け取るべく窓より差しいづるわが手つねなる片手(「雲ある夕」より)
硝子戸に鍵かけてゐるふとむなし月の夜の硝子に鍵かけること(「爪」より)
晩夏光おとろへし夕 酢は立てり一本の瓶の中にて(「啄木鳥」より)
草の上にゆるやかに犬を引き廻し与えむとす堅きビスケット(「標」より)
メロンの果【くわ】光る匙もてすくひをりメロンは湖よりきたりし種【しゆ】ぞ(「湖の種」より)
白鳥は水上の唖者わがかつて白鳥の声を聴きしことなし(「片手」より)
ぎつしりと燐のあたまの詰まりたるマッチ箱ぬき しづかにわらふこども(「草の上の星」より)
猫の凝視に中心なし まひる薄濁の猫の眼なれば(「草の上の星」より)
それから最後になるけれど、カトリシズムの歌と第三句の欠落(「晩夏光おとろへし夕 酢は立てり一本の瓶の中にて」など)の歌は浅学につき今回触れることが出来なかったので、ここに謝して稿を終えたい。乏しい教養が評を断念させることこそ虚しいことはない。