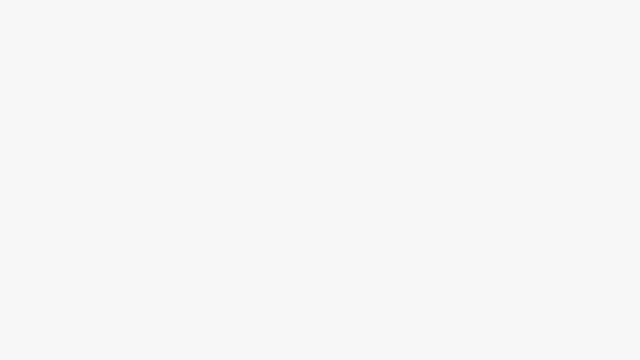所収:『葡萄木立』白玉書房 1963
文字だけで圧倒されそうになる眩しい一首。「午後」や「階段」などの詩的な単語をいくつも入れようとなると、だいたいその語の詩的な雰囲気に追いやられて、一首固有の世界を描けずに終わってしまうことが私はよくある。しかしこの歌は語に負けることなく、むしろ、とことん語の詩的さを増幅するように書かれていて、異様な光量を放っている。
まず上の句、「白き」の連続がぱっと目に入る。白い午後の白と、白い階段の白は、果たしてどれほど近似したものなのだろうと思う。全く同じ白であれば、階段が、午後の白に埋もれて見えなくなってしまうのではないか、そうだとしたら、少し異なる白なのか、もしかして、光の白と色の白なのか……などと考えるうちに、午後(時間帯)と階段(物体)という全く異なるものが白を通じて重なりあっているのが面白いなあ、と感じた。なんだか分からないけど空間もその中のものも白いのだ、ということだけは確かに分かる。
下の句、「稀なる」が巧くできた修辞である。めったにないが少しはある。0ではない。その白い階段を誰かがのぼることはある。ここでは「稀なる時間」と書かれてあるだけだが、この白い現実感が薄れていく光景の中で階段を上っていた人のおもかげがすーっと残る。居ないが居る人の姿によって、白で広がりつづける一首にキレと説得力を与えているように思う。また、漢字が稀薄の稀であることも、一首の立ち上がる光景に好影響を与えている。
私は、幻視的な作品と見ている(意識が遠のくような眩しい、本当に白い世界)が、ふつうの現実の日常風景のように読むこともできるかもしれない(少し眩しい午後、ビルの外にあるような階段にあまり人が通らないなあと思う、というふうに)。ただ、どうしても、人が白い階段を上っていくということに、死や昇天がちらつく。そして「かかりゐて」に、もとからそこに在ったのではなく、白い午後に俄かに架かった感覚が受け取れる。どちらにせよ白と時間のうつくしい余韻を味わいたい。
「白き」の連続、「稀なる」の巧さ、「午後」で始まり「時間」で終わる構成の意識・うつくしさが、読むたびに私を白い世界に誘拐してくれる。
記:丸田