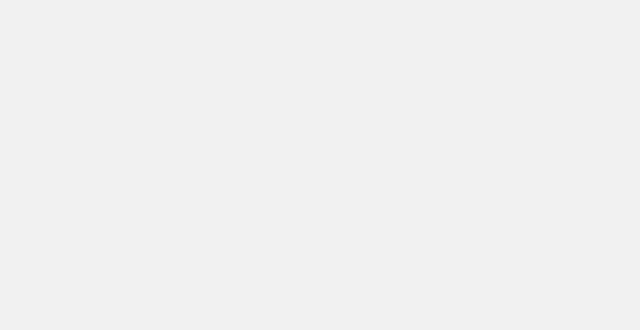所収︰『かわいい海とかわいくない海 end.』書肆侃侃房、2016
内容的にはかなり静かな歌だと思っているが、韻律や歌の展開のさせ方から表現の激しさがうるさく聞こえてくる。深海と水面に起こる荒波の二つを透かして見ているような感覚を抱く。
それぞれ読んでいくが、まず「着古した服に似ている」について。私は、よれていたりどこかがほつれていたりしている服で、でも沢山着てきたから愛着があって愛おしく思う、くらいにイメージしている(愛着、という言葉が、「愛しく着る」に見えてくる)。これを、古びたもの感を強く取って、早く捨てたいとか、早く新しい服に移りたい、と考えることもできる。ここをどうイメージするかによって、景の立ち上がり方が異なってくる。
次の「神秘に出会う人よ」について。「着古した服に似ている」が、「人」に掛かっている可能性も無くはないが、変な人がノーマル神秘に出会うより、「人」が変な神秘に遭遇してしまう事件性の面白さを取りたく、ここでは置いておく(ただ、そういう神秘に出会うのは神秘と同等に特殊な人と捉えることも可能であり、韻律のスピード感も合わせて、最初の措辞を「人」に掛けて読むこともできる、また後述)。
着古した服のような神秘。神秘とはそもそも、人知では届かないような不思議や秘密を指す。「着古した」を愛着と取るとき、人知から離れたものに対して人間的な妙な愛着を感じているのが妙である。「出会う」と初めて遭遇したように言っているのにもかかわらず「着古した」なのは、何度も味わっていたりずっと身につけていたかのようである。デジャヴのような感覚で、見たこともない神秘であるはずなのに何故か懐かしく愛着を覚える、というふうに読むのがいいだろうか。
一方、「着古した」を古ぼけて早く捨てたい、新しいものへ移行したいという感情として取ると、「神秘」がやや皮肉っぽく見えてくる。神秘というと畏れ多かったり綺麗だったり謎めいて素敵! 的な受け入れられ方がされたりする。が、この読み方であれば、例えば旧習であったり古びた価値観であったりを敢えて「神秘」と言い直して、まだそんなものを崇めて服みたいにずっと身につけているのか、と述べているように考えられる。
私は最初、完全に先の愛着の読み方で読んでいた。美しい神秘、それに遭遇する人、それにぶつけられる謎の映像(情報、表現)。しかしそれだと、「人よ」が引っかかることになる。音数的にも、別に「人よ」ではなくて、個人的に自分が神秘に出会って愛着を感じた、という話にしてしまうことは出来る。それを破って他者に拡げていくこと、呼びかける(詠嘆とも読める)ことの必要が、いまいち分からなくなってしまう。
これが、捨てたいものとして考えたとき、「人よ」が分かりやすくなる。そういうある意味神秘的な旧習に好んで出会いに行く人々よ、聞こえているか、と「人」に対して怒りを向けているという読み。だんだん読み返すたびにこちら側寄りで考えるようになった。
ただ、愛着でかつ皮肉にも読むことは出来る。先ほど「〜に似ている」を、「神秘」に掛けるか「人」に掛けるかという話も述べたが、それは感じている人によって分岐する。
分岐をまとめると(ここでは「人」≠主体として)、
①「着古した服」は愛着あるものか、捨てたくて次に移行したいものか。
②「〜に似ている神秘」と感じたのは「人」か主体か。
もちろん「着古した服」への感覚はその二つに限ったことではないため、読みはもっと広がっていくと思われるが、大きく考えるとこの二点で考えられる。
「本人が愛着を感じる神秘と出会った。その人へ」というタイプ、「本人は愛着を感じているある意味神秘的な旧習に、また(好んで)出会おうとしているめでたい人へ言いたいことがある」というタイプ、「私にとってはとっくに古びたものを、明るい神秘として受け止めて出会う人へ」というタイプなどなどが考えられる。
しかし、そもそも「着古した」には愛着も離れたい願望も、どちらとものニュアンスが含まれているであろうし、「神秘」にも素敵さや畏れ、分からないからとりあえず格をあげて謎として無視する、などさまざまなニュアンスがあるため、はっきり分類することは出来ない上に、する意味はほとんど無い。
ただ、上の句の部分に何らかの皮肉や批判の意を汲み取ろうとするならば、「着古した服」か「神秘」の箇所で、主体と「人」の感覚のねじれが生まれていることになることを確認したかった。
そしてようやく「スプーンとスプーンとナイフ」を考える。一字空きがなされてリズムよく並べられる。銀色の食器が(テーブルの上に並んでいるか、同じ場所にしまわれているかなど位置情報を欠いて)現れることを、まったくの美しい光景として読むことも出来るが、明らかに何か意味がありそうな雰囲気と、前半の皮肉の気配から、詳しく考えたくなる。
ナイフよりスプーンの方が多い。例えばフランス料理を食べるときのテーブルを想像したとき、そこにはスプーンよりもナイフが多くある。そしてナイフと同じくらいフォークがある。この歌ではフォークが消えて、スプーンが増え、ナイフが減っている。ただ「ナイフとスプーンとスプーン」ではなく、「スプーンとスプーンとナイフ」。スプーンの多さにも目が行くが、やはりナイフの鋭利さは最後の体言止めによって残っている。それはむしろ強化されているほどである。湖と湖と滝、と言ったら滝の落下のイメージが強くなるように。スプーンにはない切れ味と危険さが特に現れている。
とりあえず具体的にどういう食事風景なのか、と考えていくような歌ではない。食事かどうかすら分からないが、主体は「スプーンとスプーンとナイフ」を発見/想像した、ただそれだけである。それをどう思っているのかまでは分からない。
皮肉や批判という線をここに繋げるとしたら。制度、社会、性、宗教、年齢、文化……。一つ多い「スプーン」は何で、たった一つ未だ切れ味を持つ「ナイフ」は何か。また述べられていない「フォーク」はどうなっているのか。そして前半と繋ぎ合わせたとき、「ナイフ」は武器となって「人」を指すことになるのか、「人」そのものが「ナイフ」であると指摘することになるのか。歌の輝きや勢いは収まっていくのか、増していくのか。
鑑賞としてはそこをどう読むかを明かして語っていくべきなのだろうが、私はそれを固定して語りたくない。「着古した」と「神秘」の揺れと、過剰とも言えるくらいの清潔な「スプーンとスプーンとナイフ」の情報の絞り方が魅力である歌に、何かをどんどん当てはめてパズルのように解くことは、それこそ「着古した」短歌の読み方なのかもしれないと思うからである。なんだか素敵な比喩と神秘と銀のカトラリーからなる歌としても、最後まで皮肉の効いた高潔な歌としても読めうるという、この歌の豊かな魅力を紹介して終わりたい。
記︰丸田