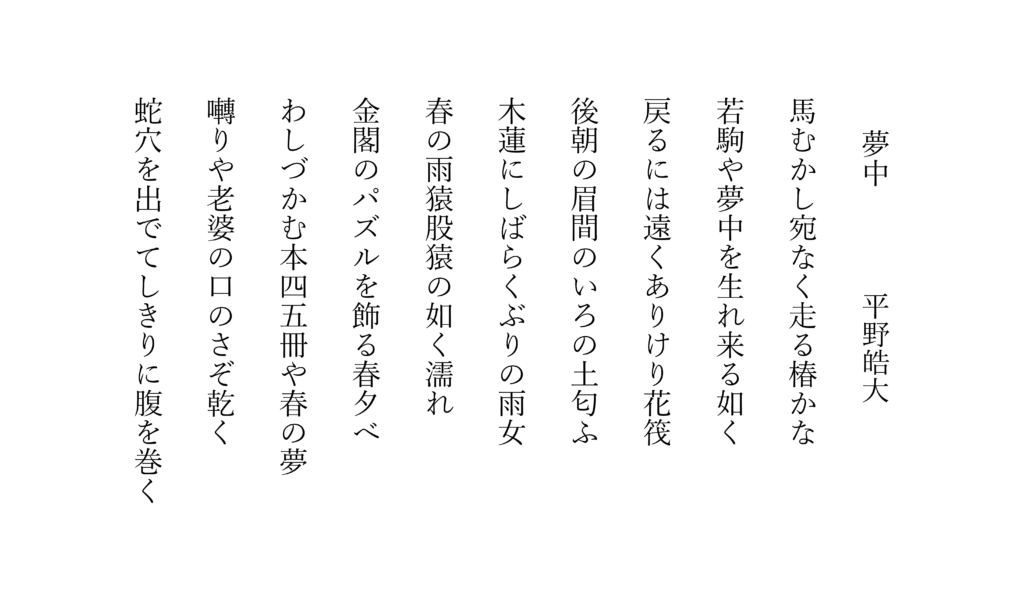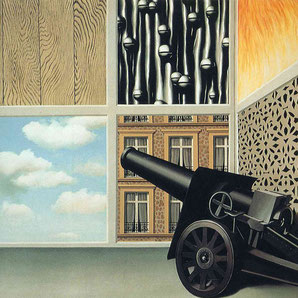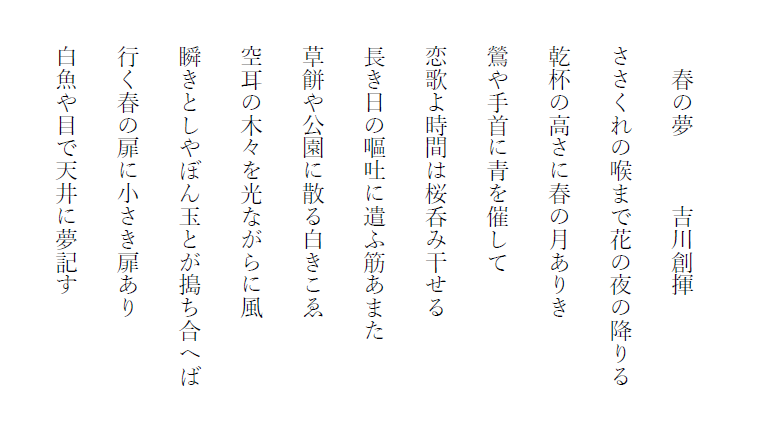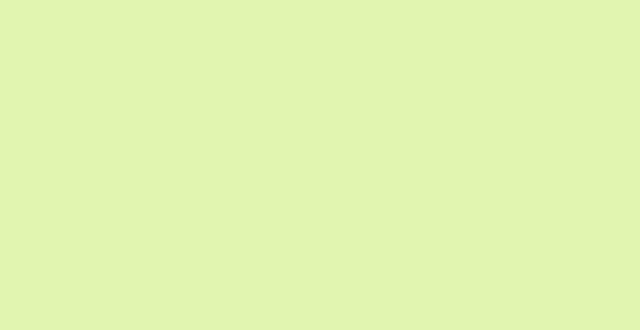所収:小池正博編『はじめまして現代川柳』(書肆侃侃房、2020)
窓化。
革命歌作詞家に凭りかかられてすこしづつ液化してゆくピアノ 塚本邦雄『水葬物語』
こちらは液化。
窓にもたれていると、窓になってしまった。これは一体、どこに要因があるのか。もたれかかってきた人を例外なく取り込んでしまうような驚異的な窓なのか。別に窓になっても良いかもしれない、と主体が油断したからなのか。窓になりそうな凭れ方をしてしまったのか。「沖にある窓」だったからそうなったのか。
なりたくてなったのか、なりたくないのになってしまったのかで、印象は変わってくる。「沖にある」という入り方から、自ら窓の世界に寄り添おうとしている雰囲気(適当に窓を選んでいないというか)があり、窓化してしまってもそこまで嫌な気持ちはしていないのでは、と推測している。
窓化という語のパワーに惚れてこの句を引いたが、句としてはやや粗いように思っている。先に引いた塚本の歌であれば、「すこしづつ」がかなり効いており、実際に無い光景のはずが、本当にピアノが滴ってぐにゃりと液化していく様子が想像できる。一方窓化は、どういうふうに窓化するのかが全く想像できない。主体は人間だとして、体の一部分が物理的に窓に形状が似ていくことを指しているのか、精神的な面で窓になっていくのか、透明という特質が伝染って透けてくるのか、まるきり窓に変身してしまうのかが、分からない。そこが分からないのもまた良さで、とも思うものの、ここにもう少し具体性があるほうが個人的には好みだった。
「液化してゆく」に対し「窓化する」とある。「する」、とはその経緯がすっかり省略されている。ゆっくり窓になったのか、一瞬にして窓になったのか分からない。
ここで思うのは、これが一瞬にして窓、だったらつまらないなということである。確かに、その方が窓っぽく、「窓化する」と間を省いた言い方にも合ってくる。ただ、それなら「沖にある」はのんびりし過ぎている。突然変異的に、押入れを開けたら異世界に繋がっていた的なことなら、その窓がどこにあろうとさほど変わらないと思う。「沖」があまりに雰囲気でしかなくなってしまう。
この「沖にある窓」を選んで、さらに眺めるだけでなくて「凭れ」た、その時点で、かなり思考は「窓化」しているように思われる。かなりゆっくり窓化した、それを窓側でも主体側でも許しあっていた、とそのような空間を想起した方が、「沖にある」が効いてくるのではないか。
川柳を読んでいて度々思うことだが、(もちろんストーリー性のあるものもあり、長律で展開までつけるものもあるが)それが奇想であり、その出発点であればそれでいい、そして単語選びやその接続が独特であればまた良い、という心で作られた作品がかなり多い気がしている。短いためその後まで言えないからそうなっているというのは十分承知しているが、そういう飛び道具的なものは個人的にそこまで記憶に残らない。どちらかというとこの筒井の句もそういう句になると思われるが、「沖にある」が最後までそう読ませるのをとどまらせてくれた。窓化という単語の発明のみに終わっていない、その窓化が行われた空間と時間、そして「その」窓と主体の関係性を思わせるきっかけが用意されている、優しく飛んだ句であると思う。
読みようによって駄句と良句に分かれる、その幅が(俳句や短歌よりも)非常に大きいのが(良くも悪くも)川柳だと私は思っている。少なくとも川柳の鑑賞においては、できるだけその句が良くなるように、という気持で読んでいきたいと思っている。
窓化したあと、主体はいつまで窓であるのか。もし戻るのなら、どうやって戻ったか。窓になる時と逆向きに戻ったのか、違うものを経由して戻ったのか。戻らないなら、主体はどんな気持ちでいるのか。周りから誰かが見ていないか。
まだ色を塗っていない塗り絵のようで、まだまだ多くの可能性が考えられる。過剰に読み過ぎるのも良くないかもしれないが、この句については、読み過ぎるほど「窓化」がより良くなっていくのだろうと確信めいた感覚を抱いている。
記:丸田